| |
| 自分の家が友達のそれと比べてどこか変だと感じてはいたものの、チビの頃の俺はその
件に関しては特に何も考えていなかったように思う。 だから、その時の質問も、もちろん母親を困らせる意図などなかったし、それが重大な転 機になろうなどとはたった5才の俺に予想できるはずはなかったのだ。 北海道ふらの市。4月の末頃だった。俺は幼稚園の年長組にあがって、近所の友達とあ たりを駆け回りながら毎日せっせと遊びに精出していた。 姉の遥は小学校の2年で、もう俺たちのようなチビはてんで相手にしなかった。学校の女 の子たちと遊ぶほうがずっと高尚だと信じていたのだろう。 ともあれ、その日も俺は幼稚園から帰った後の長い午後を、近所の遊び仲間と川べりで過 ごしていた。網を持っていたのは春男だけだったし、川の水はまだまだ冷たかったので、俺 たちは岸の草に座って石投げか何かをしていた。と、向こう岸の国道を大きなトレーラーが 走って来るのが見えた。巨大な荷台にはこれまたバカでかいブルドーザーが乗せてあっ た。俺たちはすっかり魅入られてしまって、そのトレーラーが轟音を立てて行き過ぎるのを口 を開けて見送った。 「知ってっか、こーじの父ちゃん、あんなでっかいトラック運転してんだぜ。俺、こないだこーじ と一緒に乗っけてもらったんだ!」 その時、いかにも得意そうに叫んだのは隣の和正だった。へーぇ、すげえなあ…、などと声 があがり、どの目も好奇心と興奮にギラギラし始めた。 「俺の父ちゃんはよぉ、馬持ってんだぞー。下フラヌイのほうのホテルあんだろ、あそこで乗 るんだ。でっけーんだぞー」 「正則だって知ってっさ。俺んとこの父ちゃんは札幌まで会社のバス運転したんだからな。ゴ ルフの会社の札幌だかんな」 まあ、そんな調子ですっかり父親自慢で盛り上がったのだ。お互い父親の働く場というの は、大人世界への憧れを一番に反映するものだったのだろう。 俺はその時、ふー、とかへーとかうなっているだけだったと思う。そして家に帰るなり、母親 に尋ねたのだった。 「母ちゃん、俺の父ちゃんって、どこにいるんだ?」 台所に立っていた母は、ぱっと俺を振り返った。俺がまっすぐ見つめる視線が母の顔をちょ っと変化させたようだった。母は鍋の火を止め、エプロンで手を拭いた。それから俺の前に来 てしゃがむと、真面目な顔で俺の肩を抱き込んだ。 「俺、父ちゃんを見たことない。うちにはどうして父ちゃんがいないんだ?」 なおも尋ねる俺に、母はしばらく言葉を選んでいるようだったが、やがてゆっくりと話し始め た。 「光、おまえの父ちゃんはね、よその父ちゃんと違っておまえと遊んだり一緒にご飯を食べた りはしないけれど、いつだっておまえのことを考えていてくれてるのよ。おまえは父ちゃんを 見ることはできないけれど、父ちゃんはお空の上からいつでもおまえを見守ってくれるんだ からね」 「父ちゃん、お空の上にいるの?」 「そうよ、光。おまえがもっと大きくなったら、父ちゃんにも会えるわ、きっと」 きっと…、と母は最後にもう一度口の中で繰り返した。母は笑顔ではあったが、なんだかと ても寂しそうに見えてしまった俺は、もうそれ以上父のことは訊かなかった。 そう、それまで俺は父を見たことがなかったのだ。友達の家にはいる父ちゃんがどうして自 分にはいないのか。 確かに俺の家には4人分の椅子があった。父ちゃんの分の茶碗もあったし、玄関には大き な黒い革の靴がそろえて置いてあったりもしたのだ。なのにその本体だけがなかった。どこ にも。 大きくなったら、と母は言った。大きくなるのはいつなのだろう。父ちゃんに会えるまでどれ くらい待つのだろう。チビはチビなりに、俺はそんな疑問を心の中に飼い続けることになった のだった。 |
| それからしばらくたったある日の夕方だった。俺は泣きべそをかいて一人で川べりに立っ
ていた。最初は心配げに俺を取り囲んでいた和正たちも、俺が泣きながらものすごい剣幕
で追い払ったので、ぽつりぽつりと散っていったのだった。 「バカヤロ…、ちくしょー」 俺は何度もそうつぶやき、そのうち岸にしゃがみ込んだ。何がそんなに悲しかったのか、 あるいは口惜しかったのか、泣いているうちによくわからなくなっていた。俺はめったに泣く 子供ではなかったし、こうして人前で思い切り泣くというそのことで、かえって怒りのようなも のを表現したかったのかもしれなかった。 発端は別になんでもないようないさかいだった。園庭に出してあった机を戻そうとして一人 で奮闘していたところへ同じ組のこーじが手を貸そうとして、それが俺の気に触ったのだ。俺 は一人でできると思って始めたのだし、一人でやり遂げたかった。もちろんこーじは単に手 伝おうと思っただけでそれ以上のことは考えていなかったろうし、俺が怒ったことで逆に腹を 立てたのも当然だった。 「ほらほら、そんなことで喧嘩しないのよ」 そして先生は『そんなこと』と言ったのだ。 「ねえ、あなたたちはまだ小さいんだから、先生に言えばやってあげたのよ」 『まだ小さいから』――俺が本当に我を忘れて泣き叫んだのは、きっとその言葉のせいだ った。 俺は自分がまだ小さいことを知っていたし、それが自分にとってどうにもできないことももち ろん知っていた。だが、それは俺のせいではないのだ。大人は自分の「今」が肯定できるの に、俺は「今でないいつか」を待つしかない。何か自分では手出しのできない大きな力に常 に押さえつけられている――そんな重苦しいイラ立ちがその頃の俺の心に渦巻いていたの だった。自分が無力だとは思いたくなかった。だがそれをまた目の前に見せつけられて、俺 は口惜しさより怒りが、怒りより悲しさがこみ上げたのだった。 「ひーかるー!」 その時、橋のところで遠慮がちに声がした。和正と春男だった。振り向くと二人してこわご わ手を振っていた。俺は立ち上がって二人の方に向き直った。 「はるちゃんが、迎えに来たよぉ!」 俺はちょっとぎくっとした。姉にも母にも自分が泣いているところを見せたくなかった。急い で腕で顔をぬぐった。 伸び上がると国道の横断歩道で姉がきょろきょろ左右を見ているのが目に入った。和正た ちが呼びに行ったのだろうか。 と、その姉の背後から二人ほど同級生らしい女の子が駆けて来た。呼ばれて気づいたらし い姉が振り返る。 「あ――――っ!」 橋の上の和正と春男が同時に叫んだ。右手から白い乗用車が猛スピードで走って来たか と思うと、姉のほうに突っ込んで行ったのだ。俺はとっさに飛び上がり、橋に向かって駆け出 した。 「はるちゃーん!」 「…姉ちゃんっ!!」 急ブレーキの音が右から左へと走った。…と同時に腹に響くような大きな衝撃音が俺たち の耳をつんざいた。 俺たちはその場にすくんでしまった。動こうとしても足が言うことをきかなかった。幅の広い 国道の向こう側で、乗用車が横転するかっこうで歩道に乗り上げ、ちょうどそこにあった標 識柱にめり込んで止まっていた。エンジンがまだ奇妙な音をたてていた。 「――あ」 俺は目をこらした。ひしゃげた車の向こう側で何か動くのが見えたのだ。 「…ちゃん、かなこちゃん…!!」 姉の声だった。上ずった涙声で叫んでいる。 「かなこちゃん、しっかりして…!」 後から来た車が2台ほど事故に気づいて停車し、ばらばらと人が飛び出して来た。 「大丈夫か――!」 俺ははっと我に返り、同じように駆け出した。 大人たちの隙間から、姉ともう一人の女の子が歩道に座り込んでいるのが見えた。二人と も泣きじゃくりながら、もう一人、車と標識の間に倒れている子にとりすがっている。 「姉ちゃん!!」 俺が大声を出すと、前にいたおじさんが道を開けてくれた。 「動かすな、すぐ救急車を呼ぶから…!」 「腕が…腕がはさまれてるんだ!」 大人たちもおろおろと立ったりかがんだりしていた。姉は俺の声にも気づかない様子で、 意識を失ったままの友達の名を呼び続けている。 俺は歯を食いしばった。現実のような気がしなかった。目の前がぼおっとかすんでいった。 横で俺の手をぎゅっと握っている和正の手がやけに冷たかった。 それからの数分間はよく覚えていない。救急車より先に、近所の医者が駆けつけてきた。 続いて救急隊がパトカーと前後して到着した。姉は歩道の脇の植え込みに運ばれて、膝な どの傷を消毒してもらっていた。幸い、軽い打ち身程度で済んだらしく、俺にも心配しないよ うに言ってくれた。 ふと気づくと大人たちが当惑した様子でざわめいていた。姉の友達はようやくはさまれてい た場所から助け出され、担架で救急車の中に運び込まれたのだったが、白衣の救急隊員と 警察官が眉をひそめて何やら低い声で話をしているのだった。 その時、誰かが叫んだ。 「…松山だ!」 俺も姉もぎくりと顔を上げてしまった。 「やっと来たぞ!」 大人たちが南東の空を仰いでいる。俺もあわててそちらに目をやった。 最初、それは空にできた小さいしみのようだった。が、かすかに低いエンジン音が耳に届 き始め、その点はやがてはっきりと飛行機の形をとった。 俺はさっきからの夢がまだ続いているような気分だった。そのセスナ機はゆっくりと機首を 北寄りに向けると高度を落とし始め、国道に平行に針路を定めた。そのまま徐々に徐々に地 上に近づき、――セスナは俺たちの数十メートル手前で停止した。 西日がセスナの翼を金色に染めていた。俺はもう頭がぼおっとして、中から誰かが降りて 来た時も、それに救急隊員たちが駆け寄って行った時も、ただ大きく目を見開いているだけ だった。同じように立ち上がっていた姉が浮かされたように、 「父ちゃん…」 とつぶやいた。 ――父ちゃん、父ちゃん? それは呪文のように俺の頭の中をぐるぐる回り続けた。姉の友達が担架の上で点滴のビ ンとつながったまま急いでセスナに運ばれる。それとすれ違いながら、そのパイロットが俺 に近づいて来た。 「光…」 俺は呆然と立っていた。 「おまえ、父ちゃんと来るか?」 俺は何も考えず、反射的にこっくりとうなづいた。俺の目は父ちゃんの胸の銀色のバッジに 釘づけになっていたのだ。 乗り込んでみるとセスナの内部は意外と狭かった。一番前の右側の席に父ちゃんが座っ た。後ろのシートに姉の友達が毛布にくるまれて横たわっている。そのさらに後ろのスペー スには大きな郵袋が2つほど転がっていた。俺がどきまぎしていると、父ちゃんは優しく笑っ て自分の隣のシートを指さした。 「ちょっと窮屈だがな、おまえ、この姉さんのことちゃんと見ててくれ。いいか、大事な役だ ぞ。できるな?」 セスナが動き始めると俺の心臓はますます高鳴った。横目でうかがうと父ちゃんはもうす っかり真剣な顔をして西の空をにらんでいる。夕日が父ちゃんと、俺と、機の内部をすっかり 同じ色に染めていた。 そしてセスナは空に飛び上がった。父ちゃんは無線でどこかと交信して、それから俺に言 った。 「急がないとこの姉さんは指が使えなくなっちまうんだ。いいな、そのビン、落とすなよ」 「…うん」 俺はやっとのことで父ちゃんに返事ができた。手にぐるぐる包帯を巻いて青白い顔で目を 閉じている姉の友達を見ているのはなんだか怖かったが、父ちゃんの声が俺を落ち着かせ てくれた。父ちゃんの声――父ちゃんの声は初めて聞くはずなのに、俺はずっと前から確か に知っている気がしたのだ。 「ん、何だ、光?」 俺がじっと見つめているので父ちゃんが振り返った。 「…その、バッジ」 「ああ、こいつな」 父ちゃんは笑った。笑って俺の顔を見る。〒のマークのついた銀色のそのバッジは、去年 のクリスマスに俺がプレゼントにもらったのと同じだったのだ。 「おまえ、寝ぼけちまって、これがどうしても欲しいって離さなかったんだもんな。父ちゃん、 呆れたぞ。おまえのしぶといのには」 俺、覚えてない、そんなの。俺、父ちゃんと話したことなんてない。会ったことだってないん だ。 俺は心の中でそう叫んだが、口にしたのは一言だけだった。 「父ちゃん…」 「なんだ?」 俺、父ちゃんに会いたかった。 「そら、しっかり持ってないとビンが落ちるぞ」 父ちゃんは俺のこと、ちゃんと知っていた。 「札幌までまだ20分以上かかるんだからな」 父ちゃんは偉いんだ。そして、俺、父ちゃんの飛行機に乗ってるんだ! 俺はもう黙りこくったまま時々父ちゃんの横顔を見ているだけだった。父ちゃんはやっぱり 黙って、太陽が沈みかけている金色の空を見ていた。空の上では夜はゆっくり来るんだ。 後で俺は姉ちゃんを問いつめたものだ。 「姉ちゃんは父ちゃんと会ったことあったのか?」 「そりゃあったわよ」 でも、夜遅くに時々だったから、と姉ちゃんは付け加えた。 父ちゃんは毎日夜が明ける前に家を出て、真夜中近くに帰って来ていたんだ。母ちゃんは 俺が札幌から帰った夜にそう話してくれた。俺は父ちゃんに会おうと、その夜はもちろん、そ の後も何度か眠気と闘った。だけど、気がつくといつも朝になっていて、そして父ちゃんはい なかった。 「母ちゃんはズルイ!」 俺はそう言って母ちゃんに何度もやつ当たりしたものだ。 でも、もう俺は「まだ小さい」自分に腹を立てたりしない。「いつか大きくなったら」でないと 手に入らないものにイライラしたりしない。だって俺は父ちゃんに会ったんだから。そして父ち ゃんはやっぱり俺の父ちゃんだったのだ。 《終》
――愛すべきフライング・ポストマンとその一家に捧ぐ
|
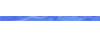 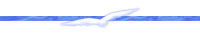 |
| 作者コメント: |
| 恐るべき幼稚園児、と言いますか、こんな子がいたらち ょっと大変かも。フライング・ポストマンのデビューはこの 話でした。 |
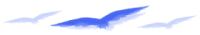 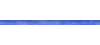 |