| この島には特別な風が吹く。 命ある者には触れない風。ストップモーションで、ビル裏の決して閉じない窓に 潜んで。 破れた夢と、これから動き出す夢の一瞬の落差の中にじっと身を縮めて。 こちらを窺っている眼。その瞬きの昏さ。 風が、それらを、見えない頭上からわずかに揺らす。 ……夜はいつもそんなふうに始まった。 『あっちだ! 逃がすな、向こうから追い込むんだ!』 『畜生、ふざけやがって! ぶっ殺してやる!』 バイクをふかす音が夜の街を引き裂いた。ヘッドライトの光の輪が、いくつも重 なりながら靴音を追う。 「……若島津?」 怒号に瓶の割れる音が重なり、その向こうでいくつもの人影がもみ合ってい る。クラクションの響き、アスファルトに叩きつけられる鈍い衝撃音。 「どこだ、若島津……!」 激しい動線からはわずかに離れた所、暗い気配が影から影へと音もなく動い ていた。 表通りからほんの1本裏手の石畳。小さく四角く建物に囲まれた吹き溜まりの ようなスクエア。 風はそこでとどまっていた。 『う…わあああっ!』 『なんだ、これはっ… !? 』 壁に悲鳴が這い上がった。追っていた男達だった。 『ひ、ひでえ……』 それは血の匂い、立ちのぼる死の匂いだった。 歩道から縁にかけてまさに海のようになった血溜まりに、俯せに人が倒れて いる。その背は間違いなくつい一瞬前まで男達が視界に捕らえていたものだっ た。 『…誰なんだ、やったのは !? 』 『お、俺、ヤツがこの角を回るとこはっきり見てた! 回りながら、まだ背中が見 えてるまま、倒れたんだ……悲鳴さえ上げずによ』 『誰も、いなかったぜ、こっち側からは……』 声がうわずる。互いに目をそらすようにおどおどと周囲を見渡す。この同じ瞬間 に、自分自身がその血の中に横たわるのを見てしまったかのように。 『なあ、あの噂…』 『アッパーのほうで、もう5人以上殺られてるんだろう? 殺ったヤツも殺った現 場もわからねえって…』 誰も動かない。ただ、放心する。遠く警察のサイレンが響き始めても。 だが、風はそのすぐ上、彼らには決して届かない頭上に吹いていた。 「ここだったのか、若島津」 反響するサイレンの重なりを背に負って、黒い人影がゆっくりと近づいた。 「また、おまえだな?」 廃ビルとなって久しい黒ずんだ壁の、煉瓦の剥げ落ちかけたあたり、近づいて きた声に引かれるようにその闇が音もなく揺れた。 「無茶しやがって。ここいらの連中はなんだかんだ言っても皆身内意識が強い んだ。どいつも顔見知りだけで世界を作って暮らしてる。下手に目立つと狩り出 されるだけだぞ」 日向は壁の前に立った。風が、行き場を失ってそこだけに渦を作っていた。 「だから……?」 低く、声がした。伏せていた顔が上げられ、黒い髪の間から視線が閃いた。 「自重しようとしまいと、どうせ俺たちは異分子ですよ。どこへ行ったって最後に は弾き出されるんだ。そうでしょう」 「若島津……」 膝をついて、日向は同じ高さで向き合った。かたくなな表情、何も映さない凍っ た瞳がそこにあった。 「無茶をするなと言ったのは、おまえの体のことだ。自分で動くことはねえ。血が 欲しけりゃ俺が何とかする。おまえは早く回復することだけ考えろ、いいな」 「やめてくれよ……」 吐き出すような、投げやりな声が闇に響いた。 「あんたまで俺に付き合うことはないんだ。昼間の世界から逃げ出して、こんな 街までやってきて……俺のためだなんてあんたに言ってほしくないよ!」 「逃げ出したわけじゃねえ」 日向は薄く笑った。 「俺は俺のやりたいことだけをやる、それだけだ。やりたくもねえことを俺がわざ わざやると思うか? たとえおまえのためでもな」 「ただの馬鹿だよ、あんたは」 若島津は目を閉じた。乱れた髪が長く顔にかかって、また陰を深くする。 不規則な鼓動。細い息。意識はまだ半ば闇に沈んだままだ。 「おい」 日向はじれたように声を掛けた。 「まだ足りねえんだろ、手を、出せよ」 「……いいよ」 「意地張るんじゃねえ、まだ半分死人のくせに」 小さく怒気が弾けたが、日向は構わず手をつかんだ。冷たいその手の甲を自 分の口元に引き寄せながら、すぐ前の、無表情な瞳からは目を離さない。 「俺はこの街が気に入ってる」 舌先を触れ、唇でたどり、手首まで達する。 「この街は眠らない街だ。何もかもがごた混ぜで、いつでもピンと張り詰めてて、 住んでる奴等のエネルギーを吸い上げ続けてる……。俺が、街に食われるか、 街が俺に食われるか、そういう闘いなんだ」 手首に口付けながら、意識がふわりと上空に舞い上がるのを日向は感じた。 自分の周囲で、風が動き始めている。髪が風にあおられ、毛先が宙に躍るのが わかる。 凍りついた夜景。沈黙する高層ビルの群れ。規則的に交差を重ねる街路には 光が流れ続けるが、しかし俯瞰の高さからは何も聞こえては来ない。何も動か ない。 「……若島津?」 握り締めていた手に、ぐいっと力が加わった。意識は瞬時に地上へ、この一点 へと戻る。 唇を離して、日向は顔を上げた。そのまま、手も振り払われる。 「負ける気はないくせに」 石畳に座り込んだまま、若島津は気怠そうに首を振った。闇から抜け出たよう な長い髪が、その動きでばらばらと肩に散る。 「どうせ、あんたは最初から負ける気なんかないくせに」 肩で大きく息を吐き出してから、若島津はまっすぐ日向を見返した。 「そういう、何とでも張り合いたがるクセはなんとかしてもらいたいですね。俺の ほうは伊達や酔狂じゃすまないんだ。あんたの都合に合わせてる余裕なんかな いんだから」 「そうだな、でも……」 日向は少し考え込んだ。 「死ぬのはほどほどにしておけよ」 「俺だって好きで死んでるんじゃありません。俺の体はあんたみたいに容量が 多くないんだ。だからすぐ酸欠になるんですよ」 「貧血だろ」 大まじめに日向は訂正した。 同じブロック、壁を何枚か隔てたあたりで、慌ただしい動きはまだ続いていた。 車のドアが何度も閉まる音、悲鳴、それに救急車のサイレン……すべては彼ら のすぐ背中合わせに同時進行している出来事だった。 「しかし不死身ってのも不便なもんだな。いちいち溶けちまうんだから」 「他人事みたいに言わないでください。あんただってそうでしょう」 「まあ、帰って来るならいいけどな」 日向はまじまじと相手の顔を見つめた。 「……?」 「もっとも、おまえがどこに消えちまおうと、俺は必ず見つけてやるぜ。俺から逃 げようとしたって、絶対に逃がしゃしねえ」 「……そりゃ、どうも」 若島津は困ったように眉を寄せた。なるほど、相槌の打ちにくい話である。 「若島津、ちょっと耳を貸せ」 「なんです」 振り向こうとして若島津は不意を突かれた。肩をいきなりぐいっと引き寄せられ たかと思うと、日向の腕に抱きすくめられる。 すぐに、言葉にはならなかった。痺れのように全身を捕らえ、そしてゆっくりと 染み渡っていくものがある。 波……。その響きに似た遠い記憶。 若島津にとって、それは誰とも分かち合えないものだった。共有できない…… してはならないものだった。 「俺のこの命は、どこからどこまで自分のものなんでしょうね。他人の血を奪っ て、他人の命を食い尽くして……これを命と呼べるのかどうかさえわからないな んて」 血を求めなければ肉体すら保てない存在。都会の闇をぬってただ貪り続け る。決して癒されない渇きを抱いて。 それが運命だとしても、自分の運命だ。他の誰のものでもなく、他の誰に肩代 わりできるものでもなく。 「なあに、俺が決めてやるさ」 自分の胸に親指を突き立て、あっさりと、日向は宣言した。 「おまえがここにいて、俺といるうちは、かわりに俺が決めてやる。わかったな」 若島津はちょっと目を見開いた。 深い森に似た都市。垂直に連なる窓の灯が、命ある木々のように夜にそそり 立つ。 それはどこまでも底のない空間だ。何もかもを飲み込んで。あるいは何もかも を突き放して。 「……確かに似た者同士かもしれないですね、この街も、あんたも。その何の根 拠もない自信で突っ走っちまって、ハタ迷惑ざんまいの挙句やっぱり一人勝ちし ちまうこととかね」 「誉めてんのか、それ」 日向はにやりとした。先に立ち上がり、腕を取って引っ張り上げてやる。 「そうですよ。嬉しいでしょ」 眠らない街の、終わりの時刻。そして始まりの時刻。 マンハッタン午前0時。 「俺は、でも、似た者同士で心中する気はねえからな」 「……想像すると怖いな」 風が流れ始める。摩天楼さえも夜空の闇と溶け合いながらその風に耳を傾け る。 街はそんな夢の複合体なのだ。無数の道が無数の方向に絡まり、争い、また 別れていく。 影が二つ、姿を消した。闇に溶けて、音もなく。 この街に飼われた悪夢の、わずかな断片のように……。 《END》
|
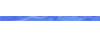 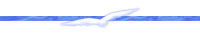 |
| 作者コメント: |
| なぜニューヨークなのか、何才くらいの時なのか…など 疑問は尽きないと思いますが、すべては雰囲気優先と いうことで。でも、溶けた若島津って…想像したくない |
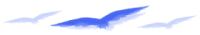 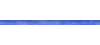 |