| 岬と三杉は恋人同士だった。 だが、誰もそれを信じようとしなかった。 と言うよりも、認めるだけの勇気と精神力が足りなかったのかもしれないが、とにかく誰も信じようとし ないのだった。 「岬が、シャーベットを作ったって!」 その日も、だから噂は最初からある種の危機をはらんでいた。 「あの岬が!」 「シャーベット?」 むろん彼らの動揺は岬の趣味や料理の腕に対するものではなく、その方向性、つまり意図のほうに あった。 「おっ、うまそー」 「駄目だよ、これは三杉くんに作ったんだから」 ぴしゃりと言われて、さすがに食い意地の張った――なおかつ岬の恋人が誰であれさほど意に介さ ない傾向のある南葛メンバーの一員の――石崎も、伸ばしかけた手もそのままに凍りついてしまっ た。 「三杉くんのためだけにね」 石崎だけではない。騒ぎに吸い寄せられてついその場に立ち会ってしまっていた選手諸君は、今や どうやってこの場を離れようかと必死に思案を巡らせていた。 いきなり窓の外に目をやって『おお、雨が降りそうだ、洗濯物を入れておこう』などと叫んで足早に去 る者が出たかと思うと、誰もいない廊下に向かって『なんだ、○○じゃないか。いつ来たんだ』と呼び掛 けて一人芝居をしながら消えてしまったり、ただひたすら壁に向かって鼻歌を歌い続けるという行為に 出たり――さりげなさを装おうとすればするほど、不自然さが目立つという悪循環であった。 「それより、さあ、シャーベット」 岬はしかし、それらすべての雑音を視界から外しているのか、ただまっすぐ三杉を見つめてそう言っ た。 「食べてくれるよね、三杉くん」 「僕に?」 一方の三杉も、周囲の緊迫感には全く注意を払っていないという態度で、やはりまっすぐに岬を見つ め返した。 「君のために、心を込めて作ったんだよ、三杉くん」 「それは、嬉しいな、岬くん」 二人は動かない。間のテーブルにはカットグラスの上に丸く盛られたパステルグリーンのシャーベット が乗っている。 座っている岬。テーブル越しに立って見下ろす三杉。 二人は永遠にそうやって見つめ合っているかに思えたが、さすがにシャーベットという室温では寿命 に限りのある食品が介在する以上あまり引っ張ることはできなかった。 三杉はふっと視線を落とすと、立ったまま手を伸ばし、シャーベットのグラスを取り上げた。 「きれいな色だね。ああ、ミントの香りがする」 「毒は入っていないからね、三杉くん」 やはり柔らかく微笑みながら、岬は言った。 「なんだ、入ってるかと思ったのに、岬くん」 二人の口調は春の昼下がりのようにふんわりと暖かい穏やかさを漂わせている。野の花の咲き乱れ る上を漂う白い蝶、その上に降り注ぐやさしい陽射し…。 「じゃあ、いただこうかな」 三杉が椅子に掛けると、反対側からすっと手が伸びた。スプーンがひとさじの氷の断層をすくい取る。 「口を開けて。三杉くん」 クリスタルガラスの透明な断面のように、静かな声だった。三杉の口元にスプーンが寄せられる。 微かな冷気が唇に触れ、三杉は反射的に目を閉じた。 「どう?」 触れた瞬間、三杉はわずかに眉を寄せる。スプーンから滑り込んできたその感触が、唇から舌先 へ、順に伝わっていくのを確かめるかのように。 「三杉くん?」 岬の声に促されて目を開いた三杉は、無意識に小さく溜息をついた。 「味はどうかな?」 「――冷たくて、よくわからなかった」 視線が、スプーンの丸い反射光から、ゆっくり動いた。その向こう側に岬の顔がある。 「そう? じゃ、もっと食べてみて」 「ありがとう」 手渡されたスプーンを今度は自分で運ぶ。ゆっくりと、一口ずつ。 「なんだか、僕たちみたいだね、三杉くん」 「ん?」 頬杖をついて三杉を見守っていた岬は、嬉しそうに言った。 「ほんとの味はわからないんだ。冷たすぎて」 「そうだね」 三杉は微笑んでスプーンを目の高さに上げた。 「冷たいけれど、でもおいしいよ」 「ふふふ」 シャーベットをすくって今度は岬に差し出す。そのひとさじを口に含むと、岬は小さく声を立てて笑っ た。 「よかった、気に入ってくれて。だって、たくさん作ったんだもの、いろんな種類をね。もっともっと食べて よね、三杉くん」 「ロシアン・ルーレット、かな」 空になったグラスにちりんと音を立ててスプーンが置かれ、二人の視線がまっすぐに対峙した。 「その中に、君が食べないグラスがきっと一つある、とかね」 瞳がきらりと光る。もう一方でも。 「恋愛は賭けだよ、三杉くん。僕たちだって例外じゃないさ」 「『世界中のどの恋人たちとも同じに』」 三杉はふと破顔すると、プレヴェールの詩の一節をささやいた。それは、岬の好きなシャンソンのリフ レインだった。 「うん」 岬は満足そうに目を閉じた。 「世界中のどの恋人たちとも同じ、だよ、僕たち」 そうだろうか。 本当の本当にそうだろうか。 なおまだその場から立ち去れないまま凍り鬼となってしまったチームメイトたちは、必死に、そう考え 続けていた。 〔おわり〕
|
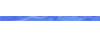 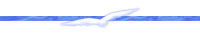 |
|
| 作者コメント: | |
| 代表チームのメンバーたちが被害者のようで案外共犯者 なのは今後の展開(?)で徐々に明らかに…(笑)。 時期とかはあいまいにしてますが、十代なのは確か。 |
|
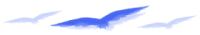 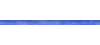 |