フレンチ・アペリティフ
| 岬と三杉は恋人同士だった。 だが、誰もが見て見ぬふりを続けていた。 と言うよりも、自らの精神安定を第一にしたいというのがチームメイト達の本音であり、触ら ぬ神に祟りなし、言わぬが花、知らぬが仏、とばかりに、とにかく誰もが見て見ぬふりの放任 主義に徹していたのだった。 「ねえ、三杉くん、今夜ヒマ?」 しかし聞きたくない時ほど聞こえてしまうのが世の常。しかも公衆の面前、つまり練習を終 えてぞろぞろ引き揚げてきたその場では、どうにも避けようがなかったのである。 人の流れをせきとめる川の中州と化した二人は向かい合ったまま動かない。一度合わせ てしまった視線が、どちらからも外せなくなったらしく、完全停止状態となっている。 もちろんそれは露骨な睨み合いなどというものとはほど遠く、かと言って情感豊かな心温ま るものでもなかったが、どちらにしても第三者の介入は断固避けたくなるような種類のもの だった。 「ヒマだったら付き合ってよ。いいでしょ」 先に動きを見せたのはやはり声を掛けた岬のほうだった。しかし、いいでしょ、という態度 ではない。 「…確かに予定は別にないよ」 「よかった」 抱擁、と言うには過激すぎた。いいでしょ、の途端に岬の手は胸元をつかんでいたのだ。 そのまま体当たりするように壁に押し付けられた三杉は、一瞬のうちに逃れようのない状態 に陥る。 クラブハウスの廊下の途中でそんな光景に遭遇してしまった選手達には、当然衝撃が走っ たはずだ。しかし…顔を伏せて、あるいは首を不自然に曲げ、変に声高に会話しつつ快速列 車のごとく通過していく。彼らなりの学習の成果だった。 しかし例外というのはあるもので、そんな仲間達とは対照的にわざわざ足を止め、壁の前 で恐怖の抱擁を続けている二人をじーっと覗き込む人物があった。 「ねえ、何してるの、二人で」 「…やあ、翼くん」 三杉の声が少々かすれたのは別にあせったからではなく、単に呼吸困難のためだった。 「何でも…ないよ。僕達、愛を語らっているだけさ」 「なんだ、そうか」 翼は安心したようににっこりした。背後から伸びた腕が必死に引き止めようとしているのに もまだ気づいていない。保護者役の井沢だって、決死の覚悟で引き返して来たのだろうに。 「俺、殺そうとしてるのかと思ったよ。よかった」 「大丈夫だよ、翼くん。三杉くんはこんなことくらいで死んだりしないから」 岬も振り返って笑顔を見せる。翼はともかく、その背後でついそれを目にしてしまった井沢 は一瞬石と化しそうになった。 「ボク達ね、今夜の約束をしてたところなんだ」 「ふーん、そう」 ちなみに翼もある意味で不死身であった。 そもそも岬と三杉の間のいわく言いがたい関係を生み出した火種なのを忘れて、さらにそ の火に油を注いで回るというのだから恋のキューピッドの資格は十分すぎる。 「だってボク達、こんな時しか会えないんだもの。少しの時間でも一緒にいたいよね、三杉く ん」 また向き直って視線をグサグサと突き刺し合う恋人達であった。 「そうだね、君と二人っきりでいると、胸がどきどきして冷静でいられなくなるし」 「うん、ボクもキミと話してると、すぐかーっと熱くなって自分でも何を言ってるかわかんなくな るし」 緊迫感あふれる愛である。 「すごいねー、ほんとに気が合うんだ、岬くん三杉くん」 感心していないで早く逃げなさい。 「岬くん、愛してるよ」 わずかな呼吸の余地を確保しながら三杉はささやいた。 「君の面影、君の言葉がトゲのようにいつも心に突き刺さっているんだ。胸の奥がちくちく痛 んで、夜も眠れないくらいだよ」 「ボクも、キミの顔を見るだけで胸が張り裂けそうになるよ。いっそキミをこの手で殺したいく らい、愛してる」 三杉の喉元に、指がまたじわりと迫った。突き付けたナイフのように。あるいは、大切に、 いとおしむように。 比喩が比喩でなくなりそうで、さすがに翼も心配になったらしい。さっき否定されたものの、 割り込むようにして三杉の青ざめた顔を覗き込んできた。 「…三杉くん? どーして抵抗しないの?」 三杉はまだ命のある証拠に、目を開いて絞り出すような細い息をついだ。岬の手が動いた ことで、襟元がわずかに楽になったようだった。 「岬くんを喜ばせたくないからさ」 なるほど、無抵抗の抵抗だったとは。岬の目の輝きが微妙に変化した。 「ボク、キミのそういうとこ、大好きだよ」 「ね、今度は何? 何する気なの?」 心配なのか期待しているのか難しいところだったが、とにかく翼はとことん熱心だった。保 護者達はとっくにさじを投げて逃亡したので、もう常識の出番はない。 「――ん」 頬に伸びてきた指から逃れようとしたのか、わずかな動きに三杉の髪がふわりと揺れた。 「味見だよ」 しかし岬はやめるつもりはなさそうだった。 「食前酒(アペリティフ)、にね」 ネクタイが解かれ、ボタンが一つずつ外された。 三杉は再び目を閉じて、岬の手を受け入れる。肩に掛けられていただけのチームジャージ が壁を伝って片側に滑り落ちていった。 「だから近寄っちゃ駄目だって言ったんだ」 敵前逃亡した負い目もあっておろおろと出迎えた井沢が声を低めた。 「あーあ、結局ただのおのろけだったんだ。見せつけられちゃったよ」 そんな平和なもんじゃないと思いますけど…という顔をその場の全員がしているのに背を 向けて、翼はソファーに勢いよく飛び込んだ。 「愛がなくっても気持ちいいならいいんだろうけど。でもどうせなら、あれくらい両想いがいー なぁ」 「つ、翼っ、なんつー発言をっ!」 保護者として聞き捨てならぬという勢いで井沢がさえぎった。赤面は余計だけどね。翼はく るりと首を振り向けると、にこーっと笑顔を見せた。 「ねー、井沢? 気持ちいいの、好き?」 「わ、わわわ…」 これはこれで井沢の幸福かもしれなかった。 「でも岬くんってさ、あれでけっこうマゾなんだよね。うん、両マゾ状態だ、あの二人」 ここまで見切れないうちは、まだ修行が足りないのかもしれない。 「それとも…両サドかな?」 当人達にしかわからない幸福もあれば、第三者によってのみ認知される幸福もある。 でもとにかく二人は幸福だった。 なにしろ、二人はまぎれもなく恋人同士だったからである。 「…ねえ、三杉くん」 誰にも邪魔されない時間、そして空間に彼らはいた。 「うん?」 手を伸ばせば、白く闇に浮き上がる肌に触れることもできる。支えきれないほどの熱い吐 息をぬって。 「もう一度、試していい?」 「僕の命は一つだけだよ、岬くん」 「一つくらいいいじゃない、ボクにくれたって」 今日何度目かの生命の危機を思って、三杉はくすりと笑った。 「そうか…。でも、必ず返してもらうからね」 「了解」 二人の恋人達は、幸福だった。 そうは見えなくても、とにかくやっぱり幸福だった。 〔END〕
|
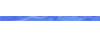 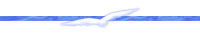 |
| 作者コメント: |
このシリーズ、ますます過激な道に入り込んでます…
(笑)。R指定まで行くのか、ギリギリの線かと思うので
すが。二人がすごい悪人に見えるかもしれませんが、そ
うではなく、愛におぼれて自分を見失っているだけなの
で、責めないであげてください。
|
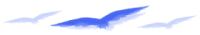 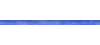 |