アラビアン・ナイトメア
| 岬と三杉は傍若無人に恋をしていた。それぞれ誰に恋しているのかは秘密だったが、ま
さに無敵な恋をしていた。
ここはいつもの国籍不明な合宿所。 午後の練習が終わってグラウンドから引き上げてきた選手たちの中に、一人、どことなく 足取りの重い者がいた。 「どうしたんだ、岬。体調でも悪いのか?」 「いえ」 監督の声に、岬ははっとしたように顔を上げた。 「そういうわけじゃないんです」 「しかし朝からどうも元気がなかったぞ。まあ、プレイにはさほど影響はなかったようだった が」 岬の側を行き過ぎようとしていた他の選手たちがその会話になにやらびくびくと反応して いるのに監督は気づいた。が、その意味を追及する前に、彼はこのレギュラー選手の悩み を解決しようという使命感を優先させてしまったのである。 「何か問題があるなら言ってみろ。相談に乗るぞ」 「……」 何かと自己主張の強い選手たちの中で、比較的おとなしくて優しい、しかししっかりした 選手…つまり安心安全な優等生というのが、賀茂監督の岬に対する評価だった。 しかし、この物静かな少年の口から出たその返答は、監督を絶句させた。 「恋わずらい、なんです。監督」 サッカー一筋の体育会系、で通してきた彼には、よりによってこの岬からこういう言葉が 出て来るとは予想できなかったらしい。買いかぶり、というのとはちょっと違うが、世代のギ ャップに少々鈍いところがあるだけに。 「そ、そうか。…若いうちにはいろいろあるだろうな、うん。悩みもあって当然だ。そうか… そうだな」 視線を宙に彷徨わせながら、まるで自分に言い聞かせるように最後は独り言となってフ ェイドアウトしていく。自分から相談を受けて立った以上、守備範囲でないからとあっさり突 き放すことができなくなったのだ。 「いえ、悩みというほどじゃないんですが、ただ、いつも胸がときめいて苦しいんです」 口調はあくまで淡々と、いっそ客観的に過ぎるほどだったが、面と向かってこういう台詞 を、しかも「少年の純粋な目」で見つめられながら聞かされては、ますます冷や汗が流れ る。 「あっ、…そ、そうなのか。それは大変だな。…ええと、片想いとか、――まさか、不倫なん かじゃないだろうな」 「違いますよ。僕たちはずっと両想いです。ご心配なく」 取り乱して変な方向に口を滑らせている監督に、岬はまたもきっぱりと答えた。 「でも、一緒にいても、自分の気持ちがよくわからなくて時々とても落ち込んでしまったりす るんです」 「な、るほど…」 うーむ、いかにも青春真っ只中らしい繊細な悩みだ…と監督は思ったものの、だからこれ にどう応えるべきか、それが一番の問題だった。 途方に暮れて視線を外した監督は、そこでようやく周囲に充満している緊迫感に気づい たようだった。 二人が向かい合って立っているのは、ロッカールーム前の通路であったが、その近辺に は選手たちが、こっちを見るでもなくかと言って立ち去るでもなく落ち着かない様子でうろ うろしているのだ。 「なんだ?」 監督はもちろん知らなかったが、彼らはこれでも期待半分、そして同情半分でコトの成り 行きをそれとなく見守っているのだった。 「岬、そう言えば他の連中にはおまえ、相談したりしていないのか?」 例えば大空翼にとか…と言おうとしてさすがにそれはためらったようだ。ちなみに今回、 翼は不参加ということになっている。 「いいえ、個人的なことを持ち込みたくはないですし、誰にも打ち明けてません」 つまり監督が唯一の頼みなんです…と言わんばかりにまた視線が切なく…なったように 監督には見えてしまった。 「どーこーが!」 と無言の抗議が背中に突き刺さっていることにはもちろん気づかずに。 いやそれは確かに岬は自分の恋について周囲に話したり相談したりはしていない。しか し、合宿や遠征のたびに容赦なく見せつけられているチームメイトたちの精神的ダメージ は積もり積もってもはや快感になるまでに至っていたのである。 「そうか。いや、もちろん俺だって力にはなってやるがな、同世代のやつの意見てのも大 事だぞ。一度話してみたらどうだ。な?」 「そうでしょうか」 既に逃げに入っている監督であった。が、いちはやく気配を察した選手たちは、監督が 振り返ろうとした時にはもうめいめいの方向に消えた後だった。 「お、いいところに来てくれた」 ということで、監督がつかまえることができたのはたった一人だったのである。 「三杉、すまんがちょっと来てくれ」 「はい」 皆より少し遅れてそこに現われた三杉は、いつもの落ち着いた態度で監督と岬の前に立 った。と同時に、消えたはずの野次馬たちがわさわさと復活して、いっせいに視線が集ま る。 「突然ですまんが、今、岬から悩みごとを聞いていてな。ちょっとおまえも聞いてやってくれ んか」 三杉はさして表情を変えずに、黙って岬を見た。もちろん、岬のほうも黙ったままで、その 視線には反応しない。 「岬くんにも悩みがあるとは意外ですね。もちろん僕でできることでしたら、協力します」 こちらはさらに輪をかけた優等生、賀茂監督がここで大いに安堵したのは言うまでもな い。 「いや、本人はなんでもないって言うんだが、ここのところ元気がないようだったし、大会ま でに少しでも解決しておいたほうがいいと思ってなあ。…それがその、恋の悩みなんだそ うだ」 「それは大変ですね」 何かと。 「僕じゃあまり役に立てないかも…」 「一緒に聞いててやるだけでいいから」 賀茂監督にそう懇願されて、ロッカールームの向かいにあるミーティングルームに3人は 移動した。 「ふだんあまり会えないから、たまに会えるともう舞い上がっちゃって、心にもないことを言 ったりするんですよね」 「たとえば?」 監督は怖いもの知らずである。 「愛してる、とか」 「そ、それ、心にもないことなのか…?」 「はい」 確か熱愛の両想いだとか言ってなかったか? 「つい、抱き締めちゃったりとか」 それも心にもないこと…? 監督の疑問がどんどん膨らむ。 「あ、あーと、それはつまり純情だって、そういうこと、だよな」 「そうですか? …たとえばこんなふうに」 岬は隣に座っていた三杉を、いきなり壁にどしんと押し付けた。ぎくりとしたのは監督だけ である。 「愛の深さが腕力に反映されてしまうっていうか…」 三杉のほうは別段驚くでもなく、抗議する様子さえ見せなかった。ただ黙ってされるまま になっているのを監督ははらはらと見やったが、岬の話はそれに構わず続いていく。 「暴力ってほどじゃないんですけど、なんかこう、思う通りにコントロールできないんです。 ベッドでも…」 「う…!」 妙な声を上げたのは監督だった。 「ベッ…ド、だって !? 」 「監督、僕だって健康な体を持ってるんですよ」 三杉の襟首を押さえたまま、岬は律儀に監督を振り返った。 「は、はい」 どうも立場が逆転し始めたようだ。 岬は説明を続けながら、三杉の喉元にじわり、と力を加える。 「やっぱり歯止めがきかなくて…」 「……」 自分より少し背の高い三杉を引き寄せるようにして、岬は思いっきりウルトラスーパーグ レートに熱いキスをした。 数十秒の空白。 しかし賀茂監督には数時間にも感じられたことと思う。ご愁傷さま。 「…っていうふうに深入りしちゃって」 うーん、危ない表現であった。 「それはいったい…悩みなのか?」 監督の肩が徐々に下がっていく。頭を抱えて叫び出したいところをなんとかこらえている のは、相談のアシスタントとして同席し、実に無防備かつ無抵抗を貫いている三杉への恐 怖にも似た疑問符のおかげだった。 「お、俺にはよく…わからないんだが」 「そうですね」 ここで初めて三杉が声を発した。ゆっくりと体を起こすと、まずひとつ大きく深呼吸をする。 どうやら酸素の補給をしたらしい。それから「協力」を頼んだ立場からも指導者としても非常 にマズイ状況に置かれてしまった監督の動揺には見向きもせずに、あくまで平然と着衣の 乱れを直す。 「岬くんの自己分析が正しいかどうかはともかく、客観的に見て…」 ここで三杉は監督と岬を交互に見やった。 「この場合は相手の反応というのをもう少し考慮してみてはどうかな」 「て言うと?」 岬の目に、ちょっぴり鋭いものが光った。 「君は自分の言動をコントロールし切れないことを悩んでいるわけだろう? だとしたら、相 手が果たしてそういうコントロールを望んでいるのか、望んでいるとすればどの程度必要 なのか、君のほうだけの判断では決められないってことだ」 「愛してる、って言葉も?」 「そうなるね」 二人の視界に、もはや監督の存在はないようだった。 「君は自分のその言葉を信じていない。なら反対に、その言葉自体に裏切られているかも しれない」 「ふうん、試してみようか?」 「どうぞ」 やはり監督の存在は消されているらしい。 岬は今度はわざとゆっくりと手を伸ばし、三杉の頬をとらえた。その動きに促されるように 三杉が目を閉じる。 「僕が、欲しい?」 低く、からまるように岬の声が響いた。親指が唇の上をかすめて触れて行く。封印をする かのように。 「愛してるよ。君を…この手で殺したいくらいに」 監督は、もうとっくに逃げるべきだったのだ。が、彼ははっきり言って腰を抜かしていたに 違いない。会話のカヤの外にされていてさえ、背筋がぞぞぞーっとするくらいのインパクト がある。ありすぎる。 「…岬くん」 その名を呼んでから三杉は静かに目を開いた。自分に触れている岬の手を逆にからめと るように自分からも腕を伸ばし、岬の首をとらえる。 「君の真実は言葉にはないんだ。どこか奥深くで眠りについているのかもしれない」 「イバラに包まれた中で、王子様のキスを待ちながら?」 岬は、ふっと口元だけで笑った。輝くように。 「でも、永遠に目を覚まさないままだったりして」 「…それはそれで美学だね」 三杉は今度は自分から唇を寄せて、さっきと負けないくらいの熱くヘビィなキスを贈った。 岬もそれに応えて熱がうねる。 だから、誰かとめなさい、って言うのに。 「でもそれが僕の真実かも」 「うん、そうかもしれない。…そうでないかもしれない」 抱擁を解く前に、三杉は謎を一つ、その微笑の中に溶かし込んだ。 「監督?」 難破船のごとく座礁している賀茂監督に、三杉は席を立ちながら声を掛けた。 「大会のことでしたら心配はありませんよ。岬くんはそんなにヤワじゃないですから。恋の 行方がどうなったとしても」 むしろヤワなのは周辺の皆さんかもしれない。 「ふわ…」 と、首を力なく振った後、監督はいきなり正気に戻ったようだった。 「あ、おい、三杉。そんな結論で、ほんとにいいのか?」 「シミュレーションは万全ですよ。後は岬くんに任せましょう。じゃ、僕はこれで」 「み…!」 と、監督の伸ばした手は、引き止めかなわず空しく宙に彷徨っただけだった。 「相手の反応か…」 その横でもう一人の「み」がつぶやいた。どことなく嬉しそうである。 「よし、今夜さっそく試してみよう」 「―― !! 」 岬は絶句している監督ににっこりと笑いかけた。そう、純情な優等生の顔で。 「こ、こ、今夜って…ことは、つまり…?」 「監督、相談に乗ってくださって本当にありがとうございました。もうご心配かけないようにし ます」 廊下からじーっと覗き込んでいたチームメイトたちが自然に両側によける中を、岬は元気 いっぱいに出て行った。 日本ユース代表チーム。おそらく次の大会もぶっちぎりの活躍を見せることだろう。 しかし…。 「こっちのほうが人生相談必要だな、次は」 「見上さんを呼んでおくかぁ? もう使いモンにならねーかも、この人」 選手たちの同情は、完全に沈没してしまった監督にではなく、やっぱり自分たちに向けら れているのだった。 〔END〕
|
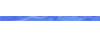 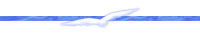 |
| 作者コメント: |
シリーズ3作目、さらに過激さが増しております…(笑)。
ラブラブなのはいつものことですが、今回は監督をあえ
て被害者にしてみました。ちょっとした意趣返しかな。
初出時のより少しだけソフトに改訂しています。
|
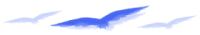 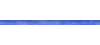 |