| レジで支払いをすませた三杉が振り返ると、カウンターの一番端で岬が何か
を覗き込んでいた。 掌に乗るほどの大きさのガラス製の白い円筒形。その上部には雪の結晶形の 切り込みが入っている。いくつか並んだ一つ一つが、少しずつ違う向きにトン ネル状の口を開いていた。 「ああ、雪ランタンですよ、そりゃあ」 主人は愛想よくうなづいた。 冬のさなかの小さな祭り。雪に埋もれた庭や道端のあちこちに並ぶ氷のラン タンは、子供達がそれぞれに小型のバケツで器用に作るのだと言う。日が落ち た後、ランタンにはろうそくが灯され、子供達はその灯の間を賛美歌を歌いな がら教会に向かう。この地方ではクリスマスと並んで子供達が楽しみにしてい る行事だった。 店でこうして売られているのは、それを模して装飾用に作られたマスコット なのだと、主人は説明した。 「昨夜、また若い娘が襲われたそうだ…」 入れ違いにカウンターに近づいた一人の客の声が、彼らの背後で響いた。近 所の住人らしいその男は、カウンター越しに老主人に声をかけている。 「今度も血がすっかり抜けちまってたって話じゃないかね。やっぱり悪魔の仕 業だって、隣町じゃ教会で祈祷式をするらしいぞ」 「よしなよ、ハワード。迷信だって」 「でもな、今年のランタン祭りは中止にすべきだって、町議会でももめてるん だ。このままじゃあな…」 のどかな田舎町にも、忌まわしい噂話はあるものらしい。 二人はちょっと目を上げて視線を交わしたが、黙って店を後にした。ドアが 背後で音をたてて閉まり、二人は凍てついた空気に包まれる。 岬はちょっと目を細め、街灯の青白い光に小さなランタンを透かした。その 肩をぽんと叩いて、三杉は先に立つ。 「君も、ランタンを作ってみるつもり?」 「まさか」 茶色の紙袋を後ろの座席に無造作に投げ込み、二人はランドローバーに乗り 込んだ。 「僕たち、昨夜も誰かを襲ったらしいよ」 「身に覚えはないけど…。夢遊病にでもなったかい、君?」 「なんで僕に訊くのさ。君だって有資格者だろ」 「だって僕は君のお相手しすぎたせいで動けなかったんだよ、朝まで」 「へ、変な言い方しないでよね!」 人聞きの悪い…と言っても、車内にいる以上もう誰も聞き耳をたててはいな いのだが。 「こんな小さな町ばかり回るから、実際誰も襲えないんじゃないか! 都会な ら一人や二人消したって目立たないのに」 「当分、僕で我慢するんだね。大都会はまだ数百キロ彼方だ」 睨みつけていた三杉からぷいと顔をそむけ、岬はヘッドライトの先に黙って 目をやった。 一度やんでいた雪がまた舞い始めていた。買い物のために立ち寄ったこの小 さな町は、東海岸へ通じる幹線ハイウェイからは少しそれた位置にある。常緑 樹に囲まれた住宅が並ぶメインストリートをまっすぐ進めば、教会の角がもう 町外れだった。 この先はゆったりとした登りになり、左右に農地が広がる見晴らしのよい道 のりだが、もう既に夜も更けてその風景は闇に塗り込められている。遠く点在 する農場の灯が、木立ちの陰に時折ちらちらと目をかすめるばかりである。 横風にあおられるように、雪は勢いを増し始めていた。対向車は1台もな い。雪道に時々小さくバウンドする他は、単調なエンジン音だけが車内を満た していた。 「ん?」 「………」 助手席の岬が、深くもたれていたシートから黙って体を起こした。しばらく 息を詰め、ハンドルを持つ三杉の手にそっと指を触れる。 「ねえ、限界だよ。…三杉くん、止めて」 「わかった」 顔色までは見えないものの、苦しそうな息づかいと、触れた指の異様な冷た さが岬の変調を物語っていた。車を路肩に寄せてライトを消す。周囲は完全な 闇になった。その闇を白く包んで、雪明かりだけが鈍く反射する。 「待って…、今、外すから」 結んでいたタイをほどき、襟を開く。その三杉の手をもどかしげに払いのけ て、岬は白い首筋に唇を寄せた。 細かな痙攣のような震えが、触れ合う体全体から伝わる。生命の確かなぬく もりとは隔たった不安定な物体――一個の物体として抱かずにはいられない不安 の暗黒を三杉は思った。 音もなく、窓に吹き付けてくる雪片。 落ちて、滲み、ガラスの傾斜に重量を預ける…。その上にさらに叩きつけら れる次の雪片。絶え間のない繰り返しが、三杉の視界から霞んでいく。 聞こえない落下。聞こえない最期の叫び。 それは言葉ではなく、まして、音楽でもなく。 「…雪が純白なんて、嘘だね」 岬の小さなつぶやきが、意識の輪郭を浮かび上がらせた。 自分の首に小さな余熱を感じながら、三杉は顔を上げる。 「岬くん?」 「白くなんかない、自分はちっとも白くなんかないって、知っていて、それを 隠すためだけに降り続けるんだ。自分に嘘をつき通すために…」 岬はまるで引き離されるのを恐れているかのように、両腕でしっかりと三杉 を抱えていた。 「もう、大丈夫かい?」 そうして抱えられたまま、三杉はほんのわずか体を動かした。気怠い痺れが 全身を包み、吐く息の熱さが自分でも感じられる。 岬の返事はなかった。代わりに指先にまたぐいっと力が加わる。 「誰かの生命の切れ端をかすめとってでないと生きていけないなんて…。君 の、君の体まであてにしなくちゃやっていけないなんて、僕は…」 泣き声とも笑い声ともつかない細い嗚咽だった。 不安定な体。不安定な心。 「それでも生きていくしかないさ…」 「嫌だ、もう」 ずるずると三杉の胸へと上体を沈めて、岬は首を振った。 「知ってる? 僕は君が嫌いなんだ、大嫌いなんだ」 「…知ってるよ」 三杉は闇に目が慣れてきたことを知った。闇の中に、自分と岬と、そして降 り積もる雪が浮かび上がる。 窓には、なおも叩き付けてくる雪片。途絶えることなく。 「でも僕らは出会ってしまった。そうだろ? 僕らは僕らから逃れられないん だ、もう」 岬の体がぴくりと動いた。三杉をつかんだ腕にぐっと力が加わり、相手を引 き寄せるようにして身を起こす。伸び上がると、互いの視線がまっすぐ向き合 った。 その時…。岬がはっと首を振り向ける。 「今、悲鳴が…!? 」 外で、とつぶやいて、岬はドアに手を掛けた。が、その前に突然ドアが強く 引かれ、岬は車外に弾き出される。 「岬くんっ!?」 道路下の斜面にごろごろと転がった岬は、降り積もったばかりの細かな雪に 全身まみれて、自分の上に、大きな黒い人影が近寄るのを見上げた。 |
| 「なんだぁ? ガキが2人かよ。こんなとこで停まってちゃ、車ごと凍りつい
ちまうぜ」 がっしりとした肩幅の大男だった。濃い色の縮れた髪に、無造作な顎鬚。古 びたマウンテンパーカーにジーンズという姿はこの地方のどこにでもいそうな 男だったが、ただ、声にどこか異様な響きがある。 「そら、来なよ」 岬を追おうと身を乗り出した三杉の襟首を乱暴につかむと、男は力任せに引 きずり出す。三杉は抵抗しようともがいたが、岬に血を与えた直後の体では思 うに任せない。 「へえ…」 男の目が光った。 「お楽しみの途中だったってわけか。そいつは悪いことをしたな。だが、俺も 急いでるんでね、この車はもらってくぜ」 三杉の鼻先に、べっとりと赤く濡れた刃先が突き出された。男は薄笑いを浮 かべたままその大きなアーミーナイフをぐるりと回してみせる。三杉はひるむ 様子もなく、ただ嫌悪の表情で相手を睨み返した。 「おまえも、こいつに食われたいか? そんな顔をするもんじゃないぜ。もっと 怯えてみせろよ。震えて泣き叫ぶんだ。さあ…」 目にははっきりと狂気があった。人間のそれと言うよりは、野獣の狂気だっ た。 「生きた人間の肌にナイフを入れる感触って、わかるか? よーく冷えたバタ ーをな、ナイフで切るあの感じなんだ、手応えがな」 「やめろっ!」 岬が跳ね起きたのと、三杉の足が閃いたのが同時だった。 雪が舞い上がった。三杉が道路脇に放り出されたのだ。 男は呻いた。蹴り上げられた利き腕を押さえて、顔が苦痛に歪む。それはす ぐに激しい怒りの表情に変わった。 「こ、こいつ…!」 ナイフを握り直して男が一歩踏み出す。だが、それは男の最期の一歩だっ た。背後から気配が近づき、男の意識はそこで永遠に途切れる。 「まったく、無茶だよ、君は…」 男の首筋から指を離し、岬はその体が大きく崩れるに任せた。そちらには目 もくれず、雪の上に投げ出されている三杉に歩み寄る。 「…三杉、くん?」 返事はなかった。三杉は仰向けになったまま動かない。その周囲の雪が滲み ながら赤く染まっていくのを見て、岬は顔をしかめた。 「もう、ほんとに、バカなんだから!」 「ああ…」 目を閉じたまま、三杉は微かに口を動かした。微笑もうとしたらしかった。 「平気だよ。もう少しじっとしてれば、傷は消えるから」 「だ、だからって、君はね…!」 注意深く三杉の体をさぐって傷の場所を確かめると、岬はそっと手を添え た。 「岬くん」 「なに?」 岬は首を巡らして三杉の顔を見る。ゆっくりと、三杉が目を開こうとしてい た。 「君は特別だったんだ。君だけが他の誰とも違っていた。僕は君に会ってしま ったことを後悔したよ。もう、引き返せない、と」 「……」 「…僕はわかったんだ、君が何者なのか。僕に唯一思うままにできない君が、 何なのか。…君は僕自身だったんだよ。周囲の誰をごまかせても、自分さえも ごまかした気でいても、本当はどうにもできない自分自身、それが君だった」 また目を伏せて、三杉は小さく息をついた。 「僕は弱い、僕は無力だ、何より、自分自身に対して。…君は鏡のように、そ んな僕の姿を突きつけてくる。僕は君を憎むことで、かろうじて踏みこたえて いたんだ」 「だから僕を、生かし続けるの? 君の体さえ与えて」 「どうかな…」 岬の言葉に少し目を見開いて、それから三杉は困ったような笑顔になった。 「だから、僕は告白するよ。…僕は、君が大嫌いだって」 「バカ…!」 3回目のバカはそれ以上続かなかった。唇を噛み、顔を背けてしまう。そし てそのまま頭を抱え、やがて岬は笑い出した。 「それなら、いいよ、三杉くん。どうせ僕らは離れられないなら、諦めるしか ないなら、それでいいよ」 「そうだね」 三杉も笑い、それからゆっくりと慎重に体を起こした。岬がはっとして手を 貸そうとしたが、三杉はそれをさえぎった。 「あの『血に飢えた殺人鬼』から、たっぷりいただいたんだろう?」 顔を近づけて、内緒話をするようにささやきかける。 「僕にも少し分けてほしいな。さっき君にあげたばかりでこんなにこぼしてし まったんだ。もう空っぽだよ」 「残念でした。僕は美食家だからね。あんな奴の血は一滴だって願い下げだ よ」 男を倒したのは、血を取ったのではなく生気を抜いたのだ、と岬は種明かし した。 「とんだ悪魔だよ。僕らが間違われるなんて、いい迷惑さ」 雪にまみれている三杉の頭をぱんぱんとはたいておいて、岬はふと手を止め た。目に、微かな影が浮かぶ。 「じゃ、目を閉じてて」 声を落として、岬は静かに言った。 素直に、三杉は目を閉じた。呼吸一つの間をおいて、冷たい気配が唇に伝わ る。 降りしきる雪の幻影…。 自らが落下するのではなく、自分と入れ違いに逆に世界のすべてを虚空へと 引き込み続ける、雪。 その中に微かに灯る光があった。穏やかな光が、ゆらめいて一つの流れにな る。力強い熱い流れが体の奥へと渦巻くように注ぎ込み、それはそのまま三杉 に託された。 「君って時々…意表をつく人だね」 「そう?」 三杉から離れると、岬はもういつもの顔に戻っていた。 道路の反対側に歩いて行き、見えるはずのない夜の奥底をじっと凝視する。 「雪は自分を――自分だけは隠せないんだ」 落ちてくる雪を顔に受けながら、岬は夜空を仰いだ。 「世界の何もかもを自分の白さの中に埋めて覆い隠してしまうくせに、自分だ けは、絶対に隠せないんだ…」 「岬くん、これ」 先にシートに戻った三杉が、ダッシュボードの上から雪ランタンを取り上げ た。 「ああ、うん…」 岬はランタンを目の前にかざすと、指先をその中央にそっと寄せた。 ぽっ、と青白い光がランタンに灯る。 岬は足元の雪の上に、それを静かに置いた。 ハンドルにもたれかかったまま、三杉は横目で岬を見た。 「同情なんてしてないくせに」 「死んだ人に興味はないよ。死んだ血にもね」 この夜また殺人鬼の手にかかった一人の女性。岬が灯したのはその命の最後 の残像だった。 「さあ、もう早く行こうよ。先は長いんだし」 「君が運転してくれるのかい?」 「冗談でしょ。僕は無免許だよ」 うねるような丘陵を、ハイウェイに向かってランドローバーは走り始めてい た。 「僕もそうなんだけどね、岬くん」 ヘッドライトに照らし出される雪道と、そして降り続く雪。走り始めた車の 背後、すべては闇に飲み込まれた。ランタンの灯も、既に見えない。 「残せるものが、あるだけ、いいよね」 バックミラーを見つめながら、岬がつぶやいた。 雪に覆われた、ほの白い闇の世界に向かって。 《END》
|
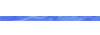 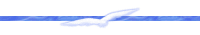 |
| 作者コメント: |
| 外国のようですが、国は不明。北米大陸のどこかという ことにしてください。英語を話しているようですが。ちなみ にこんなランタン祭がほんとにあるかは不明です(笑)。 |
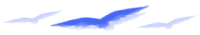  |