| 雨は降り続いていた。重い、緑色の雨だった。 病院の新しい建物の中で改装を待ってここだけ最後に残った古めかしい内装の木造二階建ての病棟であ る。敷地の一番奥手にあたり、周囲を多くの木々に囲まれて、梅雨のこの時期はどうしても暗い印象になって しまうようだ。 松山は足元で鈍くきしむ床を一歩ずつ意識しながら、目指す病室に向かっていた。 1階の16号室。廊下のつきあたりだった。ノックをしようとしてためらい、松山はそっとドアを開ける。 三杉は眠っていた。音を立てないように入って来た松山は、その寝顔が思ったより静かなのを見て安心し た。危険な状態はもう過ぎた、と聞かされてはいたのだが、こうして自分の目で確かめてようやく納得できる。 夢を見ている顔だ、と松山は一人考えた。 部屋には他に誰もいなかった。三杉の母とは医局の前で偶然顔を合わせ、挨拶をした。夕食の時間前に戻 ります、と告げて三杉の母は病院を出て行った。 松山は部屋を一通り見渡し、そしてベッドから離れて窓辺に歩み寄った。暮色が雨に溶けたかのように、風 景が青くにじんでいる。ガラス越しに、それは完全に音のない世界だった。 松山の耳にはまだあのホイッス ルがこびりついていた。三杉が倒れた時、そのすぐそばにいたのが彼だった。カウンターで攻め上がってよう やくもぎ取った決勝の1点。すべての目がゴールに集まったその瞬間だった。 松山の耳に小さな悲鳴が――確かに小さな子供の悲鳴が聞こえたのだ。が、振り返った彼の目に映ったの は、崩れるようにフィールドに倒れていく三杉の姿だった。ゴールを告げるホイッスルが響くその中で…。 松山はぎょっとした。ぼんやりと雨を見ていた彼の思考を打ち破るかのように、高い鐘の音が雨模様の夕景 に響いたのだ。 反射的に松山は振り向いた。 ベッドの上の三杉がゆっくりと目を開く。わずかに頭を動かし、それから松山の視線に目を合わせた。 「…やあ」 いつもの微笑が形作られるまでほんの一瞬の躊躇があった。彼は、驚いたのだった。もっとも松山のほうは それに気がついた様子はない。 「やっぱり起きちまったか。どこの教会だ、まったく。病院のそばででかい音を鳴らすのは…。せっかくよく眠っ てたのにな」 「…ああ、あの鐘は夢じゃなかったのか。僕にも、聞こえたよ」 三杉はわずかに身じろぎした。松山ははっと眉を寄せる。 「おい、そのままでいいよ。起きるなってば!」 「大丈夫なのに…」 「おまえの大丈夫なんぞ、信じるもんか」 苦笑気味の三杉の言葉に渋い顔を返しながら、松山はベッドに近づいた。 「まだこっちにいたんだね。もうとっくに帰ったかと思ってたよ」 「今日な、最終便で帰る」 少しぎこちなく、松山は笑った。 「気分は、どうだ?」 「君を見て、少し良くなった」 「おい…!」 ちゃんと答えろ、とむきになる松山に、くすくすと笑いをもらして、それから三杉は真顔になった。 「まだ僕に、やり残したことはあるだろうか」 「三杉!」 松山の声が鋭くなった。 「どういう意味だよ、それは」 「一人でここにいるとね、色々と考えなくてもいいことまで考えてしまってね」 「三杉…」 見上げる視線は何を告げようとしているのか…。松山は戸惑い、目を逸らそうとした。 それを察して、三杉も窓の外に目を移す。 「…ここは、僕が最初の手術をした所なんだ。あの時の医師(せんせい)がまだここにいらしてね、この古い病 棟もあの頃のままで懐かしいよ」 雨に包まれた緑の庭。だが、三杉の目がとらえているものはそれよりももっとずっと遠くにあるようで、松山は あいまいな不安を覚えた。 「今もね、その夢を見ていたよ。僕はこの向こうの小児病棟にいたんだ。手術は、ちょうど今と同じ頃…梅雨の 頃だった。もう、12年も前になるんだね」 三杉は、静かに語り続けた。幼かった自分が、手術を恐れてなかなか承諾しなかったこと、部屋が広くて一 日のうちのわずかでも母親の姿が消えると心細かったこと、三杉は細かなところまで実によく記憶していた。 「手術の数日前だった。あの日も雨で、なんだか薄暗かったよ。夕方眠って目を覚ますと母が席を外していて、 僕は一人だった。その時聞こえたんだよ。さっき聞いたあの鐘の音だ。僕は急に部屋の外に出てみたくなった んだ。そんなことはそれまで一度だって思ったことはなかったのに」 三杉は目を閉じて、何かを思い出そうとしている様子だった。 「廊下では誰とも出会わなかった。看護婦さんや、母にさえ見つかりたくなかった。何もかもが恐ろしげで、でも 何かどきどきしたよ。何か、どうしてもそうせずにはいられない気分だった。誰かが、何かが待っていて、僕を 呼んでいるような…」 松山が目を丸くしているのに気づいて、三杉は微笑んだ。 「変な話だと思うかい? でも、僕はあの日のことはよく覚えているよ。だって、あの人は本当に待っていたん だ。ずいぶん廊下を歩いて、角を何度も曲がって、とうとう僕はそこに着いた――廊下のつきあたりのドアの前 に」 「三杉…?」 松山は息をのんだ。音が、聞こえたのだ。病室の外で微かな足音が、廊下を軋ませながら近づいてくる。 三杉も同時に振り向いた。ゆっくりと表情が変わる。 足音はドアの前で止まった。少しの間を置いて、小さくノックが響く。 松山は、三杉のその時の表情を決して忘れないだろう。 わずかな躊躇があり、三杉は 「どうぞ」 と、言った。 ドアがゆっくりと押し開かれた。 そこに立っていたのは、パジャマ姿の小さい少年だった。まぶしそうに室内を見回し、そしてベッドの三杉と、 その横に立つ松山に気づく。 「あの…」 少年は5、6才くらいか、もう少し上のようにも思えた。体は小さく、手足も細かった。思いつめたような表情を して、しかし不思議に静かな瞳で、三杉を見つめている。 「お兄さんも、しゅじゅつ、するの?」 「いや、僕はまだわからない。先生が、決めてくれるから」 少年は一歩前に踏み出した。真剣な顔で問う。 「ぼくはしゅじゅつ、嫌なんだ。しゅじゅつって、こわい?」 「こわくないよ」 三杉は、微笑み返した。 「先生や看護婦さんが、きっと上手にやってくれる。君は待っているだけでいい。目が覚めたら、君はそのこと がわかる」 「……」 少年はまっすぐ顔を上げ、ぎゅっと拳を握った。表情は真剣なままである。 「ほんとうにこわいのはね、たぶんその先かもしれない。先生や、お父さんやお母さんが君にしてあげられない ことが、きっとある。君は、それを自分でやらなくてはいけない。君はそのことを、手術よりもっとこわく思うかも しれない。でも、君にしか、それはできないことなんだ」 少年の口が、微かに動いた。松山はそれに気づく。 それは、何?…と、少年は問おうとしたのだ。 三杉は黙って少年を見つめ、その問いにうなづいた。 「こわいけれど、君にはできる。君だけが、できるんだ」 「…お兄さんにも、あるの? こわいこと…」 「あるよ」 三杉は、また穏やかに微笑んだ。 「でもね、大好きな、大切な人たちのことを考えるとね、それは勇気になる。こわいことにも立ち向かえるんだ。 自分は一人でも、ほんとうは一人じゃないんだよ」 「…うん」 拳を握ったまま、少年はうなづいた。うなづいて、ゆっくりと三杉のベッドに歩いて来る。 「お兄さん、また会える? ぼくの、しゅじゅつ、終わってから」 背伸びするように手を差し出して、少年は三杉の手を握った。三杉の瞳が微かに揺れたように松山には見え た。 「すぐには無理かな。でも、きっとまた会えるよ。きっとね」 少し不思議そうにうなづいて、少年は部屋を出て行った。廊下を行く足音が遠ざかり、そして消える。 窓の外はまだ静かに雨が降り続いていた。青から青紫へと、またわずかに色調が変化している。 三杉が、その時ようやく肩から力を抜いた。少年と対している間、ずっと体を緊張させていたらしい。松山は その肩に手を置いた。 「僕は、うまくやれたかな」 「三杉?」 肩に置かれた手にさらに自分の手を重ねて、三杉は松山を見上げた。 「あの時僕を待っていた人が話してくれたように、僕はあの子にうまく話せただろうか、ほんとうに…」 三杉はまた大きな息をついた。表情がしんから和らいでいる。目覚めた後の青ざめたような顔とはすっかり 変わっていた。 「あの人が、僕を待っていた理由がやっとわかったよ。僕が、でなく、あの人のほうが待っていた理由がね」 「何だって?」 松山は唖然とした。 「おまえ、あの子が来ることを知ってたのか? あれは…」 あれは誰だったんだ。そう言おうとして、松山はためらった。 「あれは…あの子は、どこかおまえに似てたな、三杉」 「そうかい?」 三杉は目を閉じた。 「君が一緒にいてくれて、よかったよ。ありがとう」 礼を言われる理由が思い当たらず、松山がうろたえた時、三杉の母が戻って来た。まもなく夕食の時間にな っていた。 |
| 正面よりも裏門のほうが自分の乗るバス路線に近いと聞いて、松山は病院の中庭を通って裏門に出た。
雨はまだやむ様子はなかったが、松山の心は軽かった。傘をひょいと上げて、病棟を振り返る。木立ちに
囲まれた木造病棟はすっかり闇に包まれて、代わりに窓に灯る明かりが暖かかった。 三杉は別れ際に、もう一度感謝の言葉を口にした。 「必ず、戻るからね」 と、付け加えて。 何度でも戻って来ればいい。待つことは苦痛ではない。三杉自身が希望を捨ててさえいなければ。 「あの子に会ったせいなんだ」 三杉が少年に語った言葉は、そのまま、彼が自分に語った言葉だったはずだ。 松山はあの不思議な瞬間を思い出しながら、しかし幸せな気分を味わった。 「あれっ?」 裏門の外、すぐそばに教会の塔が闇の空にそびえていた。石造りの古びた教会だった。鐘の音はここか ら響いたに違いない。 「これか。こんな近くにあったんだ」 「…どうかしましたか?」 足を止めて塔を見上げている松山に、向かいの家から出て来た老人が不思議そうに声を掛けてきた。 「鐘…?」 松山の言葉に、老人は首をひねる。 「ここの鐘は、もうずいぶん昔からカラのままだよ。戦時中に、供出されてそのままだから」 「まさか…!?」 松山は息をのむ。 さっき自分が聞いた鐘の音、十数年前に、幼かった三杉が聞いた鐘の音、そして訪ねてきたあの子供が 聞いた鐘の音は…。 答える者はいない。 雨だけが、世界のすべてを包もうとするかのようにただ降り続ける。 鐘は、待っているのかもしれない。 《END》
|
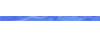 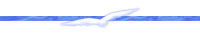 |
| 作者コメント: |
| 世にも奇妙な物語風…のつもりで読んでくださいね。い つ頃の二人かはあまり追及しないで…(笑)。2004年の 松淳祭に参加させていただいた話です。 |
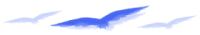 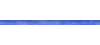 |