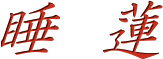
| 夏の闇は、昼間の余熱を静かに抱いていた。夜風が今はただシルエットとなった木々の
間を吹き抜けて、激しかった陽光の記憶を運んでくる。 「どこかに、行っちゃいたい」 頬杖をついて目を閉じていた岬が、ぽつんと言った。 窓の外で、また微かな物音がした。岬の、その言葉に呼応するかのように。 三杉は顔を振り向けた。 「どこかって?」 「たぶん、君なら知ってるんだよね」 「岬…くん?」 ソファーのへりから身を乗り出して、岬は腕を伸ばしてきた。 三杉は一瞬体を引きかけたが、岬のほうがわずかに早くその退路を塞ぐ。 そこが、終点だった。二人分の重みに、ソファーが小さくぎしりと鳴った。 「僕が、何を知ってるって?」 三杉の声がかすれる。もう、岬の強引な腕の中だった。 「――!」 重なった唇は、互いを強く求め合う。問いに対する答えのように。それとも答えに対する問 いのように。 「ねえ…」 「…ん」 舌先を緩めては、ただささやきを漏らす。痺れる思考の中で、言葉はもはや意味さえ持た なくなり始めていた。 岬の手が動いて、ネクタイを引き抜き、次にベルトへ移動していく。 「そんな束縛、君にはいらないよ…」 深い抱擁に身をすくめると、耳元にまたささやきが吹き込まれた。 じらすようなキスに、体の奥底で熱が脈打ち始める。それは岬のいつもの悪戯だった。ま るでゲームのように一手を探りながら、仕掛けてはかわし、その駆け引きを楽しむ。 「――っ」 「三杉くん?」 敏感な反応を確かめながら、岬は低く呼びかけた。二人だけの時間はいつも長くはない。 まして、触れ合っていられる時間は。 「もっと、欲しいの?」 答えるかわりに、三杉はただ首を振る。もどかしいのはどちらも同じだった。岬はそんな三 杉を引き寄せ、柔らかに抱きしめる。キスは、やさしく荒々しく繰り返され、それは終わるこ とのない歌のように流れていった。 そんな瞬間、視界の果てに三杉はきらりと閃くものを見る。自分を包んで、湧き出しあふ れてくる水の…幻を。 その水面に浮かび漂うのは無数の睡蓮…。 ひたひたと水音が耳を浸す。 岬の動きと、彼自身の動きが大きくうねって、その波の感触にふわりと体が浮き上がっ た。 触れている指先の熱さが、点々と感覚を刺激していく。それを意識した次の瞬間、水のう ねりが頭からざぶりと大きく襲いかかった。 むせて息を乱す三杉に一瞬驚いた顔を見せるものの、岬はそれが何かを知らない。ただ 高まる熱にすべてを委ねて、突き動かされるように強く腕に抱きしめる。 睡蓮が波にもまれて激しく上下するのがわかった。 「岬くん…」 苦しさに声を上げようとすると水は喉を埋め、体ごとまた深く水底へと引き込まれていく。 その重さ、強引な圧迫感がただ苦しくて、三杉は懸命にもがいた。 水しぶきが上がる。それが水面を打って、幾重にも波紋が重なる。睡蓮の色が水の反射 ににじんで揺れているのを、三杉は感じた。閉じた瞼の向こうに、鮮やかに光を弾く花の 色。…その色に、確かにどこかで覚えがあったのだ。 「泣いてるの?」 波の中に、古いサイレント映画の画面のように岬の顔が二重映しになる。 まとわりつく水の感触、それとも岬の…? 視界が薄らぎ、息が遠くなる。 「力を抜いて…、もっと――」 聞こえてくるのはただ水の渦巻く音だけだ。 三杉はその音に集中した。 体が熱い。すべてがその熱さに向かって溶け出して行く。 「――っ」 三杉は知っていた。岬の求める答えはここにはない。ないことを知りながら岬は彼に問い 続ける。いつか、必ず、と責める。そしてそれこそが、二人の絆でもあったのだ。 波が体を打つ。 睡蓮の長い水茎が、もまれ、もつれしながら、緑に陰る水の中を躍る。繋ぎ止められた思 い。願いは空へ、水の外へと伸びながら、その根は深い泥の下にある。 岬の見えない腕が、背中を抱く形に重なっていた。それが、波立つ。 ごぼっと泡が大きく砕けて、体が押し返された。 「――!」 睡蓮の深紅の色が、目の前いっぱいに弾ける。 「待って…!」 反射的に、手が伸びた。 泡がゆらゆらと水面に上がって行く。半透明の意識の中で、それは矢印のように道を指し 示す。 「三杉くん…」 …岬くん。 呼び合えばそれは溶けるように、遠い記憶に反響した。 そんなふうに幾度となく、訪れてくる姿がある。 陽を透かすほど薄く頼りなく、そして鮮やかな花のひと塊。それが遠く近く、夢見るように 漂っている。はるか岸辺が霞む水の上いっぱいに。 気がつくと、すべては静まって三杉を取り囲んでいた。 高い空の光。頬に触れていく風。 そう感じたのが、自分を包む生きた体温だと気付く。 「岬くん。いたんだね」 手を伸ばした先にわずかなぬくもりが触れた。睡蓮の花の一つに見えた光の重なりが、 焦点を結んで岬の顔になる。岬はかぶさるように三杉を覗き込んでいた。 「だって、ぼくを、呼んでたじゃない?」 「ああ…」 まだぼんやりしたまま指先で髪に触れる。岬はくすぐったそうに肩をすくめた。 「どこかに行ってしまいたいのは、僕のほうだったのかな、岬くん」 「だめだよ」 岬はその三杉の手を上から押さえた。 「君には行かせないよ。君はここにいるんだ」 ささやきながらその手を引き寄せ、指先に軽く口付ける。岬の目がじっと見下ろしている のを黙って受け止めて、三杉はふと思った。 あの色は、記憶ではなく、予感だったのかもしれない。 見つけられない答えのありかを、三杉はこっそりと疑った。 「岬くん…」 再びの抱擁に顔を埋めて、三杉はつぶやく。 秘密を秘密のままにしておくために。 「なに?」 「好きだよ」 一瞬手を止めた後、岬の顔に薄い笑みが浮かぶ。 「…嘘つき」 ゆらゆらと、二人の夢が漂う。 夏の闇。その暗幕の背後で、睡蓮の色が揺れ続けていた。 〔終〕
|
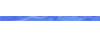 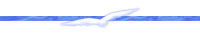 |
| 作者コメント: |
| いや、ただ、それだけ…というのもいっそいさぎよいか と。睡蓮は池の中で見るとなかなか凄みがあります、経 験上。これでもやっぱりラブラブな二人… |
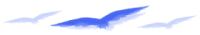 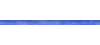 |