CONVERSATION
都心の高層マンション。
まもなく深夜の時報が鳴ろうかという頃、玄関がノックされる。
「君んちの留守番電話はいつも故障なわけ?」
ドアを開けたとたんの挨拶がそれだった。
「いつかけても留守です、留守にしています、ばかりで、ぼくの伝言は伝えてくれないじゃ
ないか。返事くれって何回入れたと思う?」
「ごめん、忙しかったんだ。君が帰国中なのはわかってたんだが」
久しぶりの再会だったが、岬のペースはいつもと変わらない。三杉の弁解は聞き流して部
屋に入って来ると、キッチンテーブルにどん、とボトルを置く。
「疲れてるなら疲れてるって顔すれば? 待たされたぼくの立場がないだろ」
「君も、またとんぼ返りだろう? 忙しいのはお互いさまだよ」
旅の多い岬と、役職をいくつも抱えた三杉。出会える機会はめったに持てない。
「これ、飲んで」
勝手に出したグラスにワインを注ぐ。岬が差し出した深紅の液体が、光を反射して揺れて
いる。
「毒かい?」
「君にはね」
岬は真顔で答えた。自分の分も注ぎながら。
「体をゆっくりとほぐしてくれるよ。どんなに頑なな体でも」
「頑なな心も、かな」
「うん、たぶん」
岬はいつになく素直に三杉の言葉を肯定した。
「正気のままじゃやってられないからさ。君の恋人でいるなんて」
「同情するよ、岬くん」
三杉はグラスを口にすると、静かに飲み干した。
「ふうん。毒のわりにはいい味だね」
「だと思うよ。なにしろ君をどうにかしようなんて毒なんだから、なまじのレベルじゃない
ことだけは保証する」
三杉は空になったグラスをくるりと回して眺めていたが、岬のその言葉にちらりと視線を
投げ掛けてきた。
「効き目はいつ現われるのかな」
「もう、すぐさ」
岬も空になったグラスを置いた。
「ぼくは無駄足を踏む気はないからね」
部屋の片側を支配している陰が、その、かたん、という硬い反響を包み込んでいく。
風にめくれていくページを追いかけるかのように。
「…岬くん?」
視線の高さが突然逆転した。
立ち上がった岬と、ソファーに掛けたまま見上げる三杉とで。穏やかな言葉のやりとりに
はぐらかされてきた感情が、ここで初めて透明な火花を散らした。
「……」
しばらくの沈黙の後、三杉の目がふっと細められた。その微笑が相手を誘い込む色になる。
だが岬はそれを無視した。三杉の挑発に乗る気はない。これはあくまで自分の意志なのだ、
と自らに確認する。
岬は不機嫌そうに三杉の髪に手を触れた。ぐいと引き寄せ、いくらか乱暴に唇を合わせる。
冷たい感触だった。冷たさにまだ少し麻痺したまま、岬の唇はその下の三杉の微かな動きを
味わう。それはいつものように、くやしいほど形式的な抵抗だった。
だが抵抗は弱い。難なく唇を開かせ、ワインのひんやりした香りを舌先に探り当てる。深
く、激しく、二人の間に凍結していたものが溶け始める。
「苦しいよ…」
軽く首を振って、三杉は逃れた。ソファーに背を預け、目の前に覆いかぶさっている岬を
まぶしそうに見上げる。
「毒で…もう死にそうだ」
「どうぞ、ぼくは別に止めないから」
自分で自分の逃げ道を狭めてしまった三杉をさらに追い詰めて、岬はぶっきらぼうな返事
をした。
「君がとどめを刺してくれるなら、そうするけど」
そんな岬を楽しそうに見上げて、三杉は笑う。ソファーに片膝を乗せたまま、岬は怒った
ように顔をしかめた。
「あっちに、移動する?」
再び両腕に抱き寄せながら目でベッドを指す。三杉はかぶりを振った。
「ここでいいよ」
影が重なり合った。吐息が絡まり、闇に溶けていく。
ブラインドを下ろした窓の向こうに、眠りを知らない巨大都市の夜景が冷たく広がってい
た。四角く切り取られた水槽の、青く澱んだ人工照明の水底を熱帯魚が交差する。
「柔らかいね…」
途切れがちになる三杉の呼吸の間をぬって、岬はつぶやいた。魂(こころ)の手触り。そ
れがこんなに柔らかい。
キメの細かい肌が上気し始める。岬の熱に促されて。
「柔らかくて、そのくせ凍るように冷たくて…」
岬の舌はさっきのワインの味をゆっくりと思い出していた。ふと、泣き出したいような衝
動に駆られる。馬鹿な、と自分で自分を笑い飛ばそうとしても、もうコントロールはできな
い。実際に触れている三杉の体から、意識は半ば宙に浮き上がろうとしている。
冷たい。この魂はいつだって凍っている。だからこそ岬の手を求めるのだ。同じ冷たさを
知る岬の容赦ない手を。
おそらくは誰にも触れさせたことのない魂。その凍りつく冷たさを知られるのを何より拒
む魂。なのに彼は岬だけを受け入れる。ゲームのように簡単に。自らを傷つけるために?
それとも相手を?
「…みすぎ、くん…」
その名を呼ぼうとして、岬は自分がそこにいないことに気づく。呼ばれているのは逆に自
分のほうだった。
――そうだ、ぼくは、夢を見ているんだ。
冷たい感触だけが妙に生々しい夢だ。岬は夢の中の自分を呆然と見下ろした。
「どうしてだろう」
「――ん?」
早朝のまだ青ざめた空気の中。わずかな音が硬質に響く。うつぶせている背中で光が弾け
るのを、岬はぼんやりと見つめていた。
「自己嫌悪って、二日酔いみたいなものかな」
「起き抜けにしちゃ哲学的だね…」
三杉は顔だけを少しずらして岬を見ようとした。が、その前に岬はソファーから滑り降り
る。
「迎え酒?」
「何か、冷たいものあるかな」
岬はキッチンに歩いて行くと、冷蔵庫を開けて覗き込んでいる。
「これ、ネクタリン? もらうよ」
中にあったつややかな果実を岬は手に取った。
「う、酸っぱいや」
「…岬、くん?」
シャツを身に着けながら、三杉は振り返った。ネクタリンを手にしたまま、岬がうつむい
ている。三杉はゆっくりと歩み寄ってきた。
「泣くほど、おいしかった?」
「…ばか」
肩に置かれた手を振り払いかけて、そのまま顔を上げる。
「三杉くん、ぼくのこと愛してる?」
「うん、不本意ながらね」
唐突な問いに、それともあまりに真摯な問いに驚いたように、三杉はあいまいに微笑んだ。
「おかげで僕は最高に不幸だけどね。でも、幸せなことに僕たちはこうして一緒に過ごすこ
ともできる。君を愛してしまったことが不幸でも、同時に幸せでいられるんだ」
「そう…、それ聞いて安心した。君を不幸にできたぼく自身にね」
三杉を見上げて、岬は複雑な微笑を浮かべた。視線は、あくまでまっすぐである。
「だからさ、三杉くん、ぼくも君を愛してるよ」
ネクタリンの酸味、それともその冷たさ。
言葉はいつも、ほんのわずかな不安に揺れ続けて。
「このまま、全部忘れてしまえる毒があったらね」
岬の腕を受け入れながら、深い息をつく。
別れの時間は迫っていた。
「君のことも全部」
「ぼくが、その毒かもしれないよ」
背けたままの顔をゆっくりと伏せて、岬は小さくつぶやいた。痛みとともに思い出す相手
のために。
「きっと、そうなんだ」
〔END〕
MENU
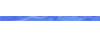 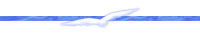 |
|
| 作者コメント: | |
| みーみーの中でも最終段階に入っている二人です。
恋人として行き着くところまで来てるって感じですね。 年齢は不詳です。いくつでもお好きな設定でどうぞ (笑)。 |
|
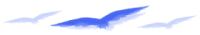 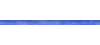 |