
| 月のない闇夜にその花は咲き始める。白い、星のような形をして。
闇に閉ざされて、その姿は見えない。しかし闇よりもさらに重く、花の甘い香りが流れて くる。ねっとりと、まとわりつくように。 気候は文化と、実は密接な相関関係があるらしい。赤道直下のこの熱帯の地には、つまり 熱帯の文化以外のものはありえない。熱帯の言語、熱帯の芸術、そして熱帯の情念。それら が、大地から生え出たかのように生きて呼吸しているのだ。 まもなくやってくるスコールを前に、肌に触れる風にはひんやりした湿り気がわずかに加 わった。ヒンズー神話の彫像に囲まれた軒下のバルコニーで、岬は昼寝のベッドから身を起 こした。 誰かに名を呼ばれた気がしたのだったが、それは夢の外だったか内だったか。ラタンのコ ーチベッドは岬の動きで微かな軋みを響かせた。 アジアサッカー連盟主催の役員会議が予定を一日上回る盛会ぶりとなり(それは主に次期 会長候補選出の手続きを巡って意見が二分されたことによる…)、その埋め合わせも兼ね て、二人はジャワ島のメガロポリス、ジャカルタから一気にここバリ島へと飛んで来たのだ った。東京からはもちろん帰国命令が出ていたが、そこは三杉の常套手段がものを言って、 彼らは期限のない休暇をまんまと手に入れたのだった。 「体調不良のため数週間の療養が必要…だなんて、よく言うよ」 口の中でぶつぶつと文句を言いながら、岬は庭を見渡す。 色濃い緑が重なり合うように、低木が地を覆い、またその上に階層を成して中高木が枝を 伸ばしている。陽がかげってやや薄暗いこんな中でも、その緑の鮮やかさはさすがに日本の 木々とは比較にならなかった。 ケケ…と細く甲高い声がどこからか響く。 姿は見えないが、それはおそらく軒下のどこか、たぶん壁の高いあたりに張り付いている ヤモリ、トッケイだ。夜に活動する彼らだが、スコールの来るこの時間を夕暮れと間違えて いるのかもしれない。 そもそもヤモリが鳴くなんてことは岬も想像したことはなかったが、それは日本でならた とえば庭のどこかから蛙の鳴き声がするのと同じだと考えればいいのだろうか。もっとも夜 遅くに窓ガラスの外側に赤い腹を見せてくっついている大きな姿を見た時はぎょっとしなく もなかったが。 まるで前触れのように風が一瞬止まる。 次の瞬間にいきなり雨がなだれ落ち始めた。まさにどこかで水門が開いたかのような勢い だ。庭の木々の枝も、草も、その雨に激しく打たれてたちまち身を低くしてしまったが、し かしそれでも見る見る潤っていくのを楽しんでいるかに見える。 その雨音に紛れるように、バルコニーに足音がした。 「ああ、降り始めたね」 「…おかえり」 遅かったじゃない、と続けかけて、岬は急いでやめた。それでは待っていたように聞こえ てしまうから。 三杉はホテルの本棟から外廊下を通ってやってきたのだろう、雨に濡れた様子はない。岬 のいるコーチベッドの背後に立ったまま、やはりのんびりと庭に目をやる。 雨はますます激しく強く白いしぶきを上げて地を打ち、庭の土を掘り返さんばかりだ。 「病人がそんな遠出してていいわけ?」 「ははは」 三杉は小さく笑った。 岬が伸ばした指先が冷たい頬に触れる。 「これ、おみやげ」 「え?」 目の前に差し出されたそれは、ガラスの風鈴のような形をしていた。細い革ひもで吊るす ようになっているのもそっくりだ。 「ほんとは、ここの主人が貸してくれたんだ。今夜は月夜だからって」 「月夜って…」 岬は呆れたようにまた庭に目をやる。ほんの小一時間でやむとわかっていても、この激し い降り方を見ているとそういうイメージがよくつかめない。 「ここに吊るせるね」 三杉は背伸びをしてベランダの上の梁にそれを吊した。雨の勢いが起こすひやりとした風 が、重そうにそれを揺らす。 「このホテルに以前滞在していた工芸家が残していったんだそうだよ。記念に、って」 「音が出るわけじゃないんだ」 「いや」 三杉は意味ありげにゆっくりと首を振った。 「月が出ればわかるって言ってたよ。夜になればね」 雨の音に混じってまたトッケイの甲高い声が聞こえる。まるで、その夜を待ちかねて叫ん でいるかのように。 |
| 終わりのない時間がここにある。
熱帯の秘密めいた闇の中に。決して、人間の手の届かないところに。 淡い照明に反射する天井の飾り彫りを見るともなしに眺めながら、岬はそんな夢を思い出 した。悲しいわけではない。むしろ、そんな存在をどこかに感知することで、人間はその限 りある生命を慈しむことができるのだろう。 ぱたん、と寝返りを打つと、左手の先が三杉に触れた。はっと目が冴える。 「起きてた?」 「ああ」 三杉はうつぶせのまま、こちらを見ていた。先に目覚めたのか。それともずっと眠らずに いたのか。 「ねえ、聞こえる?」 「え?」 言われて、岬は耳を澄ませた。 しっとりと湿った空気を震わせる微かな持続音。そんなふうに聞こえた。気紛れに時々途 切れたりしつつ、部屋の中に染み透っていく。 「あれ、月の音色だよ」 「え?」 岬は思い出した。夕方、スコールの中で吊したあの風鈴のような球体。 「あれが…?」 岬は起き上がってベランダのほうに目をやった。カーテンの隙間から、思いがけず濃い月 光が差している。 「月の鈴っていう名前だそうだよ」 岬は裸足でベッドから滑り降り、ベランダのカーテンを開いた。そうして思わぬ光景に目 を見張る。 「うそ…」 握り拳くらいのガラスの球が、内側からぼうっと光を放っていた。その奥から、あの微か な音色が響いてきているのだ。 「きれいだね。そのままドアを開けておいてくれるかい」 「うん」 ベッドから、三杉は目を細めてそれを見ていた。きらきらとした反射が、その目に映って いるようだった。 「レンズの屈折を利用して、月光を中へ中へと集めるように作ってあるんだろう。いわば光 の罠になっているんだね」 「…罠」 岬はその鈴から目が離せなくなった。 「でもこの音はどうやって出るっていうの。光なのに」 「僕もわからないけど。でも、光も粒子だから、うんと細かなところでは物体として何か作 用するかもしれない」 「細かい、ってそれ、限度があるよ」 しかし理屈は確かにどうでもよかった。鈴の中の光が揺れるように見えるのは、月が刻々 と位置を変えていくからか、鈴そのものの作用なのか。 「花の香りがするね。昼間よりずっと強く」 生き物の目のような赤い反射はベランダの脇にあるブーゲンビリアだ。しんと黙り込んだ まま揃ってこちらを凝視している。 「もう、閉めようか? 明るすぎるから」 「いや、いいよ。このままがいい」 振り返ると、三杉は食い入るようにベランダの外を見つめていた。 「僕に似ている、あの鈴」 「え?」 三杉はその光に触れようとするかのように手をかざした。岬はぎょっとする。 月明かりの強いコントラストのせいか、その姿が一瞬消えたように見えたのだ。 「身体のここに、欠けているものがあって、その、どうしても埋められない空白のせいだっ たんだ。その分いつも完璧でいられるように、と思うようになったのは。そうやって覆い隠 して、厚着していって、でもやっぱりその内側には穴が一つぽっかりと開いてるんだ。それ はもうどうしようもないことではあるんだけれどね」 三杉は岬を見上げて微笑んだ。 「時々、自覚することあるよ。その空洞で何か風のような音が聞こえてくるんだ。ね、あの 月の鈴みたいに」 「三杉くん…」 答えるかわりに、腕を伸ばして頭を抱き寄せる。光と一緒に飲み込まれそうで。 「何かが欠けてない人間なんていやしない。ボクだって、誰だって、欠けてるからじたばた しながら生きてるんじゃないか。そんな音、聞いてる暇あるもんか」 「どうしたんだい、岬くん。僕は逃げやしないよ」 いつまでもきつく抱きしめ続ける岬に、とうとう三杉が音を上げた。体をねじって向き直 り、まっすぐ顔を覗き込む。 「わかってる。欠けた所で鳴っているあの音は悲しい音なんかじゃないからね。欠けている ものこそを僕らは望んで、焦がれて……夢見るんだ。それが、あんなふうに光を呼び込んで 輝くんだよ」 「そんなの、ボクはいらない!」 岬は叫んだ。 「なくしたものは戻らない。それでいいんだ、ボクは。なくしてしまったものよりも、今、 こうして残ってる部分のほうがずっと大事なんだから」 「…大事?」 三杉の目が期待しているものにハッと気づいて、岬は思わず顔を赤くした。これではその まま愛の告白じゃないか。 「違うよ。ボクが言いたかったのは…」 「ありがとう。それで十分だよ」 窓の外では月の鈴が鳴り続けている。 「もっとここでこうしていたいね」 「ほんと、東京にいるのとは全然違うものね、時間の過ぎ方が」 月が傾くまで、二人は眠らないことにしたらしい。もっとも中庭の西側は深い竹薮になっ ているため、朝を待たずに月は隠れることだろう。 「でもさ、あんまりここに長くいると頭が溶けてきちゃいそうでさ、ボク」 「虎のバター?」 三杉はくすくすと笑い出した。水底にいるようだった青白い反射光も、次第に薄れ始めて いる。 「それなら君、今夜僕がバターになりそうなくらい激しかったのはどうするんだい?」 「…知らないなあ」 岬はそっぽを向いた。確かに、そんなことをいちいち反省していたら累積警告はどれくら いになるか。 「僕が探していた僕は、君だったのかな」 そしてもしかすると…。 「君のカケラ、僕が持っているのかもしれない」 「え? 何か言った?」 楽園には、そんな秘密がいくつも隠れている。 月が気紛れないたずらをしてみせる夜に。 〔END〕
|
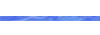 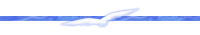 |
|
| 作者コメント: | |
| また外国にいる二人です。今回は熱帯編。バリ島のウブ
ドあたりにいると思われます。さて、年齢はいくつくらいか な。役職を持っているようですが、私の頭の中ではみー みーは常にハタチ前のままなんで。 虎のバターが何かは言わないでおきます。(笑) |
|
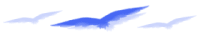 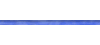 |