| 「ちょっと三杉くん、さっきから…何やってんの」
「んー」 まさに生返事。岬は自分の足元でごろごろと懐いている三杉を手で押し戻そうとするが、あいにくこの体 勢ではたいした力は働かない。 「ビデオ観てるだけだけど」 「じゃなくてー!」 岬はさらに声を尖らせるが、三杉の言葉も嘘ではない。ビデオのリモコンを片手に、早送りに巻き戻しを 繰り返しながら同じ試合を飽きずに眺めているのだ。 「なんでそんなにくっつきたがるの、って言ってるんだよ」 「だって君の部屋ってベッド一つしかないし、テレビ観るのはここが一番いいだろ? だから膝枕するしか なかったんだけど」 そう屈託なく答えて、三杉は仰向けに岬を見上げた。そのさかさまの笑顔が岬には癪の種となる。 「他人(ひと)の部屋に馴染みすぎだよ、まったく」 セーヌの岸からサン・ミシェル通りをずっと上がっていったあたり、つまり学生街の真ん中にこの古い建 物はあった。裏通りはそれはもう同じような建物ばかりが続いて、慣れないうちはどれが自分のアパルト マンか、迷いそうになるほどだ。 しかし岬の住まいはその中でもひときわ古くてしかも奇妙に奥行きのある特徴的な建物だったため、見 つけるのはそう難しくはない。難しいのはむしろ中に入ってから、という噂だ。廊下は迷路状態だし、階に よってはいったん非常階段に出てまた建物に戻るなんてこともアリなのだ。岬の住む最上階へのルート がどれくらい複雑怪奇かはご想像いただきたい。 「でも、僕はここが好きだよ。気持ちいいくらいなーんにもなくて、でも日当たりは良くて、その日当たりだ けで部屋がいっぱいになって」 三杉はリモコンを置くと、そこでくるりと起き上がった。 「それに、何よりここには君がいるからね」 「あ…そ」 岬は一瞬何かためらった。が、すぐに怒ったようにそのリモコンを取り上げ、パチンと切る。 「ほんとに、だからってホテルにも泊まらないでいつも僕を当てにするの、やめてくれる? 宿泊費浮かせ るため、っていうならまだ可愛いのに」 ぶつぶつ言いながら岬はベッドから足を下ろして靴ひもを結び直し始める。 「なんかさ、君といるともう何が来ても驚かないって言うか、こうなったら矢でも鉄砲でも持って来い、って 言うか、ヤケだよね。僕、自分で自分が信じられないよ」 三杉はまた笑顔になった。 「それって、すごーく愛してるってことだね」 「……」 睨んでおいて立ち上がる。キッチンの壁にかかっていた大きな袋を肩に掛け、ドアまで行ってから岬は 振り返った。 「夕食の買い出し、手伝って。暇つぶしになるよ」 「喜んで」 サマータイムになったばかりなので、時間の感覚がまだぎくしゃくしている。街はそんな雰囲気で動いて いた。仕事帰りの男女が、寄り道するでもなくしかし帰宅を急ぐべきかさえ決めかねたように通りでうろう ろしていたりした。 商店の並ぶ表通りまで来て、岬はやや足を早めた。 「すぐに売り切れちゃう店があるんだ。そこから行くよ」 「ふうん、楽しみだな。君の料理の腕にはいつも期待してるんだよ」 「あのね、君がいるせいで僕まできちんと三食とっちゃうじゃない。かえって体調崩しそうだよ」 旧型の冷蔵庫はあるものの買い置きと言うものをほとんどしない岬は、外出のついでにその時その時 の食料を買ってくるようにしている。ついでがなければ、または気が乗らなければ何日でもそのまま、とい うのは本当らしい。 「それはなんだか壮絶な話だね。でもそれだったらチームで行動してる時なんてどうなるんだい? 三食 規則正しく、だよ」 「ああいうのはいいんだ。食べるだけだから。三食きちんと作るっていうのが問題なんだってば」 「…確かに、その差は大きいねえ」 前方向から街の活気がひたひたと押し寄せてくる。いや、彼らがそんな方向に向かっているのだ。人通 りが特に増えたわけではないが、人々の動き、表情に力があふれている。 「おいしい店って、人を引き寄せるんだよね。見えない力でね」 岬はその通りの店の一つを指差した。 「あそこ、あのお惣菜屋さんだよ」 「本当だ、列ができてる」 店のドアを入ったそこに並んでいる人たちは焼きたてのローストチキンが目当てらしい。毎日のことな ので時間を見計らってやって来るのだろう、「どう? できた?」などと声をかけているおばさんもいる。 白い仕事着をだぼっと着た店員が、そういう客を次々さばきながら、しかしおしゃべりにも応じてそれは 見ていても大忙しというところだ。 「オリーブだけでこんなに?」 陶器のボウルに入ったオリーブは色も大きさもまちまちに何種類も並んでいる。その隣では真っ赤な色 の唐辛子ソースの瓶詰の上にハムやソーセージが下がっているし、お買い得の札のついたワインの瓶も ある。 「チーズと、あとはええと、あのパテにしようかな。肉と魚はどうしよう…」 珍しがっている三杉の横で、岬は思案中だった。オードブルからメインディッシュ、それにデザート類ま でないものはないという店内では迷うなと言っても無理である。せっかく決めたのに、前の人が買った生 ハムが美味しそうに見えて気が変わったり、それはもう忙しい。 厚紙でできた四角いケースに選んだものを入れてもらい、これでやっと一息。この紙ケース、見ている と一人用からパーティ用の大きなものまでサイズが揃って、なかなか合理的だ。 しかしこのケースにはフタはなく、そのままくるりと紙でくるんだだけで渡されるため、こぼれないように 家まで持ち帰るのが鉄則となる。 「そうか、二人なら倍運べるね」 「そうだよ。あ、そっち気をつけてね。曲がってる」 などと声を掛け合いながら二人は家を目指す。 途中、角を曲がったところに野菜の露店があり、岬は足を止めた。 「マンゴーの青いの、ちょうだい。これサラダにするといいんだよね」 おじさんは手馴れたもので、両手のふさがった岬の右ポケットから小銭を取り出し、左のポケットにぎゅ うぎゅうとマンゴーを押し込んだ。 「ありがと」 これで買い物は全部終わり。一人暮らしの岬には便利な街である。 「うちの近所にもああいうのがあるといいなあ」 部屋に戻っても、三杉はまだ目を輝かせていた。 「このへんは多国籍だからね。その分食べ物だって同じに賑やかなんだ。僕みたいなのも全然珍しくない し」 鍋に沸かした熱湯に塩をたっぷり。ツイストマカロニをざらざらと入れる。マンゴーを剥いて種も取って、 サラミソーセージを薄切りに。性格が気短だと料理の手順も早くなるものらしい。 「…見てないで手伝ってよ。昨日の野菜スープのお鍋、火にかけて暖め直して。一晩置いて味がよくなっ てるはずだよ」 塩と油と黒コショウ。味つけはこれだけである。要は素材。日本人にはわかりやすいコンセプトかもしれ ない。 「いい塩を使うのが肝心なんだ。オリーブ油もね。これだけで味が倍良くなるから」 夕食は、ワインを開けた分だけ豪華版となった。マンゴーとサラミのマカロニサラダ。野菜スープ・翌日 風味。キノコ入りパテ。そしてチーズ。 「二人だと、味が倍良くなるんじゃないのかい?」 「相手次第だよ」 食事の最後にもう一度ワイングラスを満たして、岬は憂鬱そうにそれを眺めた。 「それに、まだ足りない気がする。僕は」 「……」 三杉はグラスを置いて、岬へと視線を戻した。 何が、と問い返すほど野暮ではない。しかしタイミングというものがありはしないか。 「大丈夫、ゆっくりウォーミングアップするからさ」 「それはそれで大変じゃないのかな」 飲みさしのワインを、三杉は惜しそうに振り返った。長年の付き合いだけに、そういう予感はしっかり当 たってしまうのだった。 |
| 「どうしてかな」
「……ん?」 うつぶせている背中が光を弾くのを、岬はぼんやりと見つめていた。 「僕、君を困らせることなら何だってやってみたい」 「それ、殺し文句のつもりかな」 三杉は肩越しに視線を投げ返してきた。 「君が本当にサディスティックな性格なら、意味は違ってくるけど」 「三杉くん、僕を見くびってるでしょ」 「どうかな」 「いいかい、僕は…そして君もさ、サディスティックなんかじゃないんだ、ちょっとばかり、他の人よりルナテ ィックなんだ」 ルナティック。 それは岬が好んで使う形容詞だった。 少し自虐的に、そして大いに誇らしげに。 「でなきゃ、どうして僕たちこんなふうに恋人なんてやってられる? 僕は君が嫌いだし、君だって僕が嫌 いなくせに」 「そうだね」 ゆっくりと、三杉は顔を上げた。 「なかなか会えない恋人って、肝心な時に肝心なことを忘れたりして、それで帳尻を合わせてるんだね。 だから僕たちもそれでいいんだよ。ルナティックな関係で」 「じゃあ、愛してる?」 「それは秘密」 三杉は起き上がると、向こうにそのままになっているテーブルを見た。彼のグラスはまだそこにある。 「ふうん、僕は秘密になんかしないよ。全部君にぶつけちゃうからね」 「愛してるって、言ってくれたことあったっけ」 「あるもんか」 岬はにこっと笑う。指先で三杉の髪をいたずらして、それからするっとベッドを抜け出す。 「飲み直す? ワインならまだ何本もあるんだ」 「嬉しいな。でも、明日、立てるかな」 「保証はしないよ。僕もよく我を忘れちゃうからね」 それはどういう意味か、聞き返す暇も必要もなかった。 岬は早速キッチンの棚に潜り込んで、目当てのボトルを探し当てている。 「さあ、グラスこっちに渡して。ロゼだよ、今度は」 窓の外はすっかり暮れて、風も少し強くなってきているようだ。窓ガラスが時折がたがたと音を立ててい る。 「ねえ、僕たちって…」 「なに?」 テーブル越しに視線を合わせる。 「結局いつも先に進まないね。進んでも困るけどさ」 「半分だから」 三杉はグラスを挙げて微笑んだ。 「僕は君の、君は僕の半分なんだ。だからだよ」 「……」 岬が沈黙したのは、その言葉の意味を考えようとしたかららしかった。が、すぐに首を振る。 「…意味わかんない。酔ってきたのかな。まさか」 「それとも僕が嘘つきか。どちらかだね」 「両方」 岬は元気よく、そう宣言したのだった。 〔おしまい〕
|
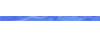 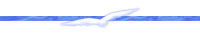 |
| 作者コメント: |
| これはとっても珍しい、ひたすらラブラブなみーみー。他 の話でも三杉くんはこの部屋によく来ているようですが、 今回は特に事件性もなく、日常の甘いひととき、ってとこ ろです。パリで自炊…なんだか女性誌の記事っぽいかも |
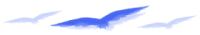 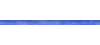 |