[ Tommy February6 ]
|
| 今日も飽きずに、若林はこの部屋に来ていた。たとえ、どんな扱いを受けようと。
「なあ、岬」 練習も終わって、いつもの自由時間。 「こっち向けよ」 「いやだ」 その反応もいつもと同じだった。 「今、忙しい」 「忙しいって、雑誌読んでるだけじゃないか」 確かに、岬が手にしているのはサッカーのグラフィック誌であった。ちなみにフラン ス語なので記事は若林には読めない。 「読むのに忙しい」 目も上げずに答える岬に、若林は大きなため息をついた。 「しょうがねえなあ。じゃ、勝手に待ってるからな」 岬が座っているデスクの隣のソファーに、若林は一応素直に腰を下ろした。アームに 頬杖をついて、黙って岬を眺めることにしたようだ。 岬は、穏やかな目で、ページの写真を順に見ている。 この目は、誰にも向いていない時に一番優しい。 そんな横顔をじっと見つめていた若林がふと身を起こし、岬に近づいた。背後からそ っと顔を寄せ、頬にキスをしようとする。が、寸止めで、岬の手が押し返した。 「じろり」 若林は両手を途中まで上げてホールドアップの体勢をとる。が、顔は緩んだまま。 「ほら、待ってるだろ。おとなしく」 「どこがおとなしいの」 睨んでおいてから、岬はまた雑誌に目を落とす。 もっと怒ってくれるなら、まだ望みはあるのに。 「おまえは冷たいよ。俺がこんなに真剣に口説いてるのに」 「真剣なわけないだろ。毎日毎日よくもまあ飽きないね」 答える代わりに行動で、と、若林は懲りずにまた近づく。今度はまんまとその頬にキ スをしたが、岬は完全無視。もう顔も上げない。 「あ〜あ、拒絶もしない代わりに受け入れもしないってか」 若林は背後から腕を回して、岬の背をふわっと包んだ。 「おまえ、もしかして…、俺以外に、好きなヤツがいるってことか?」 「そういうこと。わかったら放してくれる?」 「そうか…」 若林は大げさにため息をついた。 「三杉とできてるってのは、本当だったのか」 ばこっ! 何もゴミ箱で殴らなくても。 「今度そんなバカ言ったら君の心臓が止まるからね」 「違うのか?」 これでもなおダメージは受けていないらしい。 「風の噂で聞いたんだがなあ」 「冗談じゃない。いいからもうどっか行ってて」 諦めるつもりも懲りる様子もない若林に、岬はついに宣言してみせた。 「いい、僕が好きなのは翼くんなんだから。間違えないの!」 「あ、そうか…」 ぽん、と手を打たない、そこ。 「そりゃ、片想いだけどさ」 岬はしぶしぶそう口にして、また若林をにらむ。 「若林くんだって、片想いしてんじゃない、翼くんに」 「言われてみればそんな気もする…」 なぜだか嬉しそうな顔になる若林だった。 「…つまり、俺たちは仲間ってことだ」 「仲間じゃない。ライバル」 「可能性がないならライバルにもなれないと思うが。ほら、競争相手って意味だぞ?」 その言葉に、岬はぴくっと反応した。可能性がない。それが事実だから。 「そうだよね…、翼くんの本命は人間じゃないから」 「うんうん」 若林は殴られるのも承知の上でまた頬にキスを落とす。一回り小さい岬の体はすっか りこの男の腕の中だ。この体勢でも、岬は厳しい視線だけでそれに応じる。 「わざと音を立ててキスしないの!」 「触り心地いいんだよな、おまえって」 そこまで言われては岬も黙っていない。ガタン、と椅子から立ち上がる。腕を振り払 って。 「おい…」 「松山っ!」 は? 若林の目が点になる。 「助けて、若林くんがまた狼藉を…!」 岬が飛びついていったのは、ちょうどドアのところに現われた松山だった。 「おー、岬。大丈夫か。よしよし」 「よしよし?」 あの難物の岬を、まるで身内のように見つめてにこにこしていられるこの男って。 自分も追おうとした若林が途中で固まってしまったのも無理はなかった。 「もう大丈夫だぞ。若林は俺が連行してくから」 「ま、松山…?」 岬を離して背後にかばうと、松山はこちらに同じ笑顔を向けた。 「な、若林、わかったろ?」 「な…何が…?」 なぜかうろたえてしまう若林だった。 |
| 「おまえは恋愛対象にはならねえの。岬にはな」
「そ、そうなのか、やっぱり」 やっぱりは余計だ、若林。 「なら岬、おまえは俺のことどう思ってんだ」 「そうだなあ、強いて言うと…」 安全圏に入って、岬は落ち着き払っている。もっとも最初から動揺などしていなかっ たわけだが。 「弟・・・」 「そんな〜!」 哀れな叫びを残して若林が部屋から押し出される。松山は、廊下に出るとそんな若林 の背をぽん、と叩いた。 「よかったな、若林。赤の他人じゃなくて」 そうだろうか。珍しくがっくりする若林に対し、松山は明るい顔だ。 「弟以上恋人未満、ってとこから始めればいいだろ」 「なんだよ、それ」 「そのまんまだよ」 松山はにやりとした。 「可能性はある。そうだろ?」 「うー」 気持ちの切り替えに時間はかかるかもしれないが、とりあえず若林は納得することに したらしい。 「あと1回くらいキスしとけばよかった。ダメもとでもっと強烈なのを」 「そうか?」 松山は足を止めて振り返った。つられて立ち止まった若林の顔を見つめながら肩に手 を掛けて、軽くとん、と壁に追いやる。 「えっ…?」 と思った時には若林は目の前に迫る松山に追いつめられた形になっていて。 「ま、松山?」 「しっ」 下から捕まって引き寄せられる。 重なった唇がゆるりと動いて、まるで何かを語りかけるように舌が唇をたどる。こち らからは何もできないうちに息ごと奪われて、若林は頭が真っ白になりかけた。 「ま…待て!」 最後の最後に残った理性で若林は松山を引き剥がした。松山はきょとんと目を見開い てそんな若林を不思議そうに見上げている。 「なんのつもりだ、おっ、おまえ!」 「え? だから、ハードでディープで強烈なキスがいい、っておまえ言っただろ」 まだ途中だったけど、と松山はごく当たり前のことのように答えた。 「いいならいいけどよ。岬にことづけてやろうと思ったのに」 「ななななんだって!?」 愕然とする。 「じゃあ、おまえが岬と…できてた、とか?」 「まさか」 松山はけらけらと笑いながら若林を離し、先に立って歩き始めた。 「俺の親切」 「待てって! 本当に岬は誰とも付き合ってないのか? どうなんだ!」 「……やれやれ」 廊下で騒いでいる声にドアを開けた若島津が、その二人が階下へ去って行くのを見送 っていた。 「悪者め」 誰のことかは、言うまでもない。 「いくらからかい甲斐があるからって」 しかし、自分が巻き込まれないなら、そのへんは関知しない、いや、したくない若島 津は、再び音もなく自室に消えたのだった。 【 END 】
|
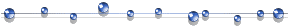 |
| |
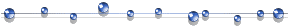 |