| 約束の時間よりいくらか早くジノは広場に姿を見せた。 中央の噴水をぐるっと回る環状交差点(ロータリー)になっているそこは、 5本もの道路が放射状に合流する交通量の多い場所だった。 ヘルメットのシールドを上げて周囲を見渡し、それから広場を出る。東向き のサンマリアノ通りに入ってすぐの所で歩道沿いにバイクを停めた。 この先はゆるい上り坂になっていて、下りて来る車はかなり向こうの分まで 見通せる。 近くの教会の鐘が響いて、ジノは腕時計を見た。指定された時間のぴったり 15分前。 坂を見上げると、3台連なった黒いセダンがこちらに向かって下りて来るの が見えた。先頭の車のボンネットに白いリボンで飾られたオレンジの花のブー ケがあるのを確認してバイクを発進する。 一度すれ違っておいてからその先でUターンし、今度は同じ方向から車の列 に追いつく。3台目、2台目、そして先頭の車…と順に追い越しながら、ジノ はちらりと視線を投げた。後部座席に白い花嫁衣裳の姿がある。確かに教会で 見たあの顔だった。 それを確かめると一気に加速して車線を変え、そのまま広場へと走り込ん だ。 今度は長い鐘の音。正時の鐘である。 さっきの車がロータリーに入りながら噴水に近づき、そして窓がすっと下り た。きらりと何かが光を反射する。 ジノは白い手袋が小さな包みを投げるのを見た。バイクを走らせながら手を 伸ばし、宙でキャッチする。 車は南へ走り去り、そしてジノのバイクは反対に北向きにロータリーを出 た。 そのまま市の外環道路を巡るように走って行くと、あのサンタマルグレ教会 に出る。 バイクを教会の下で停めて、ジノは階段の前に立った。 静かなざわめきが教会を包んでいる。大きな葬儀があるらしく、その準備が 進んでいるところだった。喪章をつけたいかつい顔の男たちの間をどんどん抜 けて、ジノは教会の扉を押し開く。2日前に訪れた時と同じ、美しいアーチに 縁取られたドームがその空間を天高く広げている。 そのドームの下、祭壇の前に、黒衣の女性がひざまづいていた。キリスト像 に向かって手を組み、いっしんに何ごとかを祈っている。 「やっぱりここでしたね、マリア」 ジノの声に女性はゆっくりと振り向いた。一瞬大きく目が見開かれたが、や がて驚きは微笑の中に消えていった。 「どうしておわかりになったの?」 「新聞ですよ。先日急死なさったあなたの父上の死亡記事が載っていました。 喪主である一人娘の名前もね、マリア・イザベッラ・デル・マデルノ」 ジノはポケットから2日前に拾った白いベールを出した。 「あなたはこれをわざと落として行ったでしょう? 僕に拾わせるために」 「ええ…、その通りです」 差し出されたベールには紋章が編み込まれている。その紋章にじっと目を落 とし、女性は硬い表情でうなづいた。 「婚礼があるタルシーニ家の紋章を僕に見せたのは、あの依頼が花嫁本人のも のだと信じさせるためですね」 「あ、あの、それで受け取っていただけましたか? もう処分はしていただけ ました?」 「ええ、もちろん」 ジノが朗らかにうなづいたので、女性はいくらかほっとしたようだった。 「花嫁の顔も見えましたよ。本当に瓜二つなんですね、あなたがた姉妹は」 「どこまでお調べになったかわかりませんが…」 小さくため息をついてから女性は話し始める。 「私たちは生まれてすぐに別れ別れに育ちました。妹は養女に行ったんです、 タルシーニ家へ。でも数年前に母が亡くなった時に初めてそのことを知らされ て、私たちは密かに出会うようになりました。嬉しかったですわ、双子の妹が いたなんて思ってもいませんでしたから」 「その妹さんが結婚の日に渡そうとしているものをあなたは処分してくれとお っしゃった。あれでよかったんですか、本当に」 「ええ、ええ、もちろんです! 妹の気持ちは嬉しいですけれど、こうするの が一番だと…」 「マリアお嬢さま、すみません、ちょっと…」 「あ、はい?」 準備に動き回っている男たちの中から、一人が慌ただしく近づいてきた。 「花がまだ届いていません。花屋はちゃんと手配したと言っているんですが」 「まあ、どこかで配達車が渋滞にかかってるのかしら。事故だったりしたら大 変だわ」 「もう一度電話してみます」 男はまた歩み去っていった。心配そうな顔で自分もその出口のほうへ一歩を 踏み出しかけた女性の背に、ジノの声が投げかけられる。 「それにしても見事な当主ぶりですね、名家の令嬢からいきなり裏ビジネス界 の最前線というのは大変だと思いますが」 「――!」 今度こそ、本当に驚いた顔で、女性は振り返った。 「あなたはマリア・イザベッラではなく、マリア・ヴィットリアです。あなた が落として行かれたベールは本物だったわけですよね、タルシーニ家の。姉に すりかわった妹が、その妹のふりをしていた…というわけだ。ややこしいな」 「あなた、どうして――」 女性は息を飲んで、それからはっと気を取り直すと、ジノの手を引っ張るよ うにして教会の外に出た。 「誰かにこのことを話したりしてませんよね」 「もちろんですよ。僕も今朝花嫁を見てやっとのみこめたばかりですし」 ファサードの階段をゆっくりと降りながら、マリアは首を振った。 「姉には結婚を誓った恋人がいたのに、父は認めませんでした。自分が決める 後継者と結婚させるつもりだったんですね。それで私の名で父をごまかしてさ っさと結婚するように私が提案したんです。相手の人は仕事ですぐにアメリカ に赴任することになっていましたし、父が後で気づいてももう手遅れ、ってこ とになりますから」 「ところがその矢先に亡くなってしまったというわけですね」 マリアはジノを見上げてうなづいた。 「本当に、亡くなってしまったらそのほうが大変だって、考えるべきでした。 生きている相手なら気が変わるまで説得もできますけれど、亡くなってしまえ ば絶対に変えられませんものね」 「それで結婚式のために入れ替わっていたあなたが泣く泣く引き受けることに なってしまった…」 「いいえいいえ! 違います!」 マリア・ヴィットリアは必死な目でジノを見つめた。 「私が、自分で決めたことです。姉が閉じ込められるようにして育ってきた 間、私のほうは苦労知らずで好き勝手に生きて来た。私がその姉で、姉が私だ ったかもしれないのに」 「でもねえ、マリア・イザベッラは最後まであなたをそうさせまいとしたじゃ ないですか。違いますか?」 「ええ、そうです。姉は私の提案を認めずに一緒に家を出ようと言ってききま せんでした。でないなら自分も結婚は諦める、と。姉を納得させるために―― そう、あなたを騙して利用したんです、私」 「僕のことなら全然構いませんけどね」 ジノは階段の下まで来ると自分のバイクに近寄り、置いてあったヘルメット をいきなりマリアにかぶせてしまった。 「何してるんだ、おまえ!」 「花を探して来ます。ご心配なく」 外にいた男たちが慌てて走って来る。が、ジノは驚いているマリアをバイク に乗せるとその男たちに手を振って急発進した。 「止まれって言ってるんだ!! 」 道路に数人が飛び出したが、ジノはハンドルを切りながらチラッと階段の上 に視線を投げた。と、そこに高く積んであった梱包用の箱が突然崩れ、道路ま で次々と転げ落ちてきた。行く手を完全にブロックされて右往左往する男たち が背後に残される。 「な、何なの、今のは…!? 」 「さあねえ」 ジノはただ愉快そうにそう答えただけだった。 |
| 指定場所だった広場に戻ってみると、何やら大騒ぎになっていた。歩行者は立
ち止まってがやがやと話し合っているし、ロータリーに入ってくる車はその光
景に目がくぎづけになって渋滞をさらにひどくしている。 「こ、これは…!」 マリアはバイクから下り立って絶句した。広場の噴水が真っ白に埋もれてい るのだ。ユリが山のように積み上げられて、噴水がそのまま巨大な水盤がわり になっている。 「これ、お葬式の花なの? あなた、まさか…」 「花に罪はないですからね。配達の人から受け取って、とりあえずここに預か ったんですよ」 二人は花のそばに立った。 「花屋さんは渋ってましたが、喪主の希望だって言ったらあっさり置いていっ てくれました。デル・マデルノの名前は効きますねえ」 「――でも、どうして」 マリアは呆れたようにジノを見上げた。たまたま出会った通りすがりの男を 利用しただけのはずが、いつのまにかどんどん変な方向に転んでしまってい る。 「もちろん僕からのお祝いのつもりです。ユリだって葬儀の花になるよりも、 あなたと、あなたのお姉さんに捧げられるほうが嬉しいと思いますよ」 ジノは内ポケットから包みを取り出した。 「まあ、これは…! 処分したとおっしゃったじゃありませんか!」 包みを手にして、マリアは叫んだ。中からパスポートと航空券が出てくる。 一緒に国を出ようと、姉が手配したものだった。 「亡くなった方は亡くなった方同士、天国で楽しく暮らしますよ。生きている あなたがわざわざ不幸になることはありません。なあに、デル・マデルノがも しこれで空中分解したって悲しむ人はいないですから」 「そんな…。なんて人なの、あなたって!」 じっと包みに目を落としていたマリアは、やがて笑い出した。 「知っているでしょう、マリア・ヴィットリア。ユリは聖母の象徴ですよ。二 人のマリアにはぴったりでしょう? もっとも僕はガブリエルじゃないですけ どね」 澄ました顔で受胎告知のポーズをまねてみせるジノに、マリアは笑うのをや めてそっと涙を拭いた。 「それは確かにまだ気が早すぎるわね。でも、その時には本当に舞い下りてき てほしいわ」 「いいですよ。監督が許してくれればいつでも」 少なくとも今は許してくれそうにないなあ、とジノは心の中でつぶやいてい た。 「なんだ、おまえ、ジノっ! その格好は!? 」 お馴染みの怒鳴り声はその監督のものだった。 「練習に来ないと思ったら――その、その花は何だ!」 緑に囲まれたグラウンドに突然現われたユリの巨大な花束。それを両腕いっ ぱいに抱えてにこにこしているのはもちろんジノ・ヘルナンデスだ。 監督も、もちろん選手たちを含めたその場の全員が目を点にしてその光景を 見つめている。言葉もない、とはこのことだった。 「遅れてすみません。結婚式と葬式をはしごしてたもんで」 「まったくおまえって奴は…」 それ以上怒る気が失せたのか、監督からあっさり解放されて、ジノはその格 好のままクラブハウスに向かう。目が合ったコンティが無言でこぶしを作って 見せた。 「冗談だけで生きていけると思うなよ。まったく付き合いきれないよ!」 フェンスの向こうで見学していたファンがきゃーきゃー言いながらそのユリ の花を投げてもらっている。 「ほんとなんだってば。もっとあったんだけどバイクで運ぶには限度があって さ、残りはそのへんの人にあげてきたんだ。はい、コンティにも1本」 残った最後のユリを差し出す。コンティはびっくりしたようにそれを見つ め、しぶしぶ受け取った。 「同じ咲くなら幸せに咲くのがいいよね、コンティ」 「な、なんだそりゃ! ――おまえは、ほんとにまったく反省の色がない!! 」 コンティが振り上げた手でユリが大きく首を揺らす。 ジノがジノである限り、その通り、と言うしかなさそうだった。 〔おわり〕 |
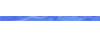 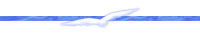 |
| 作者コメント: |
| ジノって、どうしてこういうキャラになってしまったんでしょ う、うちでは。最初は確かに原作通りのできた人だった のに。たぶんひいきの引き倒しというやつですね…。原 作に逆らって同じミラノでもACミランに入れてしまいまし た。 |
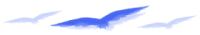 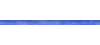 |