| 光が、一つぽつんと見える。
若林が最初に思ったことはそれだった。 そして水音。それ以外は何もわからない。ただ真っ暗な中にいるばかりだ。 「マリー」 自分の声が、どこか遠くで反響したように感じた。 「誰?」 同じくらい遠くで返事があった。若林はほっと力が抜ける。マリーの返事だ。 「今誰か呼んだかしら。ねえ?」 他に誰かいるのか? 若林が不審に思った時、ニャー、と短い声が響く。その 声を頼りに、若林はじっと目を凝らした。 「そうねえ、気のせいよね」 さっき光に見えた小さい点、それがマリーだった。闇は闇だが、さっきよりい くらか見えてきた気がする。 ――下水道だ! 湿った匂い、そして流れる水の音。天井の丸い輪郭がぼんやりとわかる。マリ ーはその下で座り込んでいた。膝の上に抱いているのは猫だ。 「マリー」 今度は声に力を込める。猫が顔を上げて振り向いた。 「どうしたの? ネズミでもいるの?」 ネズミ呼ばわりされて若林はがっくりする。だが、これでわかった。マリーに はまだ若林の声が聞こえていない。つまりここにいる自分は実体ではなく、おそ らく意識だけ、ということなのだろう。猫だけがその本能で気配を感じているら しかった。 「もう少し待ってましょ。そしたら足の痛いのもよくなって歩いて行けるわ。ど こか出口までね」 さっき電話を通じて聞こえていたマリーの言葉は、猫に話しかけていたものだ ったのだ。若林は納得した。不安な時ほど、声に出すことで気持ちが少しは休ま るものだ。 「おまえ、あったかいね。私、落ちたときに濡れちゃったからなあ。ちょっと ね、寒いのよ。ここにいてね」 足を傷めているということは、ここはもしかして事故現場の真下なのだろう か。若林はふわりと体を、いや、意識を移動させた。 ――これだな。 マリーがいる場所からわずかにずれたあたり、縦坑が上に続いてマンホールに なっていた。意識を集中させておいて、えいっとばかりにその鉄製のフタを突き 抜ける。 ――おいおい、こういうことだったのか。 事故現場はロープで囲われて警察の現場検証が行なわれていた。例のトレーラ ーがまだその場に残されていることを考えても、そう時間は経過していないはず だ。事故に巻き込まれた被害者たちはもちろん病院に運ばれた後だが、行方不明 1名、という事実が警官たちを今だ緊張させているようだった。 その様子を空中まで上がって見下ろす若林の――意識だけの――目に映ったの は、よりによってマンホールを上からふさいで横転しているトレーラーの荷台だ った。これでは簡単に発見できないのは当然だ。車体の下はもちろん確認したの だろうが、そのさらに下、下水道にまでチェックは届かなかったのだ。 ――まずは知らせないと。 若林は地上の状況をざっと見渡した上で、再び地下へと意識を引き戻した。 「おい、猫」 マリーの前まで来て若林が呼ぶと、猫はまたぴくりと顔を向けた。猫が空中に 幽霊を見る、という迷信もなるほどこれならうなづけるな、と思うくらいの反応 だった。 「悪いがちょいとおまえの体、借りるからな」 ニャー、と鳴いたその声は、もしかすると不満を訴えていたかもしれなかっ た。 「よかったよなあ、シュナイダー」 「……」 肩をたたかれて振り向いたその顔はさすがにほっとしているようだった。 「でも虫の知らせかねえ、別の用でたまたま帰ってきてたなんて」 ハンブルガーSVでの元チームメイト、カルツが隣でうなづいている。シュナ イダーは病室のほうにもう一度目をやってから廊下のベンチに腰を下ろした。 「あんな大きな事故だったし、最後の救出者だったって聞いて胆冷やしたぜ」 「足の捻挫くらいだから明日はもう帰っていいそうだ」 シュナイダーは確認するようにそう答える。久しぶりの再会がこういう大事件 になってさぞ驚いたのだろうが、それが見た目に反映されないのはいつものこと だ。 「あの猫、いいのか、病室に入れたりして」 「ああ、命の恩人だから今だけならって言われてた」 地下から救い出されて病院に運ばれる間も、マリーはその黒猫を離さなかっ た。マンホールの中から大きな声で鳴いて警官が気づいたのが救出のきっかけだ ったのだが、動けないでいたマリーのところまでまるで案内するかのようだっ た、という救急隊員の証言もあって、すっかり有名になってしまったのだ。 しかも無事に地上に出てきたマリーがびしょ濡れで奮闘したその猫に感謝のキ スをする場面が地元の新聞に速報で載ってしまって、まさにニュースな存在とな ったのである。 「猫は後で俺が連れて帰る」 「どこへ?」 「家だ、決まってるだろう」 シュナイダーは真面目な顔できっぱりとそう言った。マリーが寄宿学校に入っ た年にシュナイダー家が手放した家は確かずっと空き家のままだったとは聞いて いるが…とカルツがいぶかっている間に、病室から看護婦さんが顔を出す。 「シュナイダーさん、どうぞ」 呼ばれて入っていくとマリーはベッドの中で猫と遊んでいるところだったが、 兄を見てぱっと顔を輝かせる。 「ああ、カール、ほんとなの、ほんとに本当?」 「本当だ」 さっぱりわからない会話だが、マリーは兄を抱きしめて最高の笑顔を見せた。 「父さんも、ちゃんと帰ってくるのね、みんな、今度こそ一緒なのね!」 「一緒だ。やっとな」 シュナイダーの笑い顔などめったに見られるものではない。カルツは本当に 久々にそれを目撃して驚いた。 「おい、どういうことなんだ、シュナイダー。まさか、おまえハンブルクに …?」 「まだ秘密だぞ」 マリーに抱きつかれながらシュナイダーはちらりとこちらを見やる。 「親父もこれでブンデスリーガ復帰だ。スイスのほうが暮らしやすいのになんて 冗談言ってたがな」 「嬉しい、幸せよ、カール」 「先週は電話であんなにふくれてたくせに、現金だな」 「あら、だって」 マリーはやっとシュナイダーを離してもじもじする。 「ゲンゾーを代わりにとっちゃうなんて言うから」 「な、なんだって?」 兄と妹の会話にどんどん置き去りにされていくカルツであった。 「ハンブルガーはおまえを買うためにワカバヤシを売りに出すつもりだったぁ? じゃあ、値を釣り上げるためにマスコミに移籍話をリークしたって言うのか?」 「そこまでは俺は関知しないぞ」 シュナイダーはあくまで超然としている。 「ひどいわよね。私、ゲンゾーが自分からよそに行きたがってるのかって思って ショックだったのに」 「――おい、そう言えばそのワカバヤシはどうなってんだ? 今朝練習には来て なかったぜ」 「やっぱりそうなの?」 マリーは目を丸くして振り向いた。 「私がこの子を助けに飛び出したでしょ。で、マンホールに落ちちゃったんだけ ど、その後友達が私を探してる時にね、ゲンゾーが来てたって言うのよ。でもそ れきりゲンゾーまでいなくなったんだって。まさかまだあのあたりで探してるな んてないわよね」 「いや、わからないぜ。ワカバヤシっていつもはあんなふうに何が来てもふてぶ てしい顔してるけど、マリーちゃんみたいな子には全然弱かったりするんだぜ、 きっと」 「やめてよ、私がいじめてるみたいじゃない」 「…マリー」 話の横からぬっとシュナイダーが割り込む。 「まさかと思うが、ワカバヤシと何かあったり…してないな」 「さあ?」 「おい、マリー!」 「まあまあ、シュナイダー、落ち着いて」 目が完全にマジになっているのを見て、カルツが割って入る。この話題がシュ ナイダーの移籍によってまた再燃するのが目に見えるようだ…と思いつつ。 「何かあるくらいならまだいいがな」 こちらもベッドに入って頭を押さえている。 「こんな目に遭って、キス一つじゃ割に合わないって」 しかも猫になっている時ではどうしろと言うのだ。 「くそー、俺は爆弾人事の隠れ蓑かよ」 何年も離れ離れだった一家がまた揃って暮らせるようになる、というのはそれ はもう幸せな話だ。若林とて心から祝うつもりでいる。 しかし、その裏でこんな思いをしている人間もいるのだと少しはわかってほし い。 「ヘフナーの奴、知ってたんだ、シュナイダーが古巣に帰ってくる年を。マリー がまた家族で暮らせるようになるって、それもこれも全部」 それはそうだろう。10年後のヘフナーにとっては当たり前のことになる。 「もしかすると、マリーは俺の力のことなんてとうとう気づかずじまいだった、 とか言うんじゃないだろうな、あいつ、今になって」 まあ、それはもう確かめようがないことだが。 未来は予想できないところにある。 それを今回、身にしみて実感した若林だった。 「それとも、あいつも言えなかっただけかもな」 これから自分の身に起こることを知って、何ができるだろう。逆らおうとすれ ば、どうなるというのか。すべてがもう決まっているとしたら、身動きできなく なるかもしれない。 「とりあえず礼くらい言っておくか。代理に、今の奴に」 なぜ風邪をひいてしまったのか、周囲にはまったく謎のまま、若林はごそごそ とまたベッドに潜り込んだのだった。 「ズースちゃん、よかったわね。これでずっとうちで飼ってあげられるわね」 別れ際にマリーは猫をもう一度抱き上げた。顔と顔を突き合わせて嬉しそうに 笑う。 「なんだ、ズースって、その名前」 「だって甘口だったんだもの、キスした時」 「なに?」 シュナイダーはまだ新聞の写真を見ていないのだった。 「あのね、真っ暗な中でずっと待ってた時、ほんのちょっとだけど眠っちゃった みたいで夢を見たのよ。私、大人になってて、それで結婚式挙げてたの」 「……」 たとえ夢でも、そのマリーの表情についむっとしてしまうシュナイダーであ る。 「夢は夢だ。――で、相手はどんな奴だったんだ?」 「うーん、内緒だもん」 猫を兄に渡しながら、マリーは幸せそうににっこり笑ったのだった。 〔ENDE〕
|
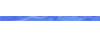 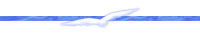 |
| 作者コメント: |
| これはキーパー達の設定が謎かもしれませんね。全員 が超能力を持っている、というのが前提なので。時代が 世紀末なのは原作初期設定に従った結果です。これで まだ19才…。 |
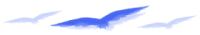 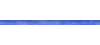 |