| |
| 「……ねえ」 僕は聞こえないふりをして、クッションに体を預けていた。僕の体の片側がゆらりと揺 れたけれど、僕は無視した。 何か、音楽のように耳に響くものがあって、僕はそれだけを聞いていたんだ。 時間が、わからなくなっていた。 日暮れにはまだ時間があるはずなのに、部屋の中はこのソファーのある位置だけを 残してすっかり影に包まれている。 そして、僕は気がついた。僕の聞いていたこのリズムが、鼓動であることに。 僕の下で、僕とは違う鼓動を響かせていたのは――。 「―― !! 」 僕は思わずクッションから顔を上げてしまった。 「岬くん、生きてた?」 「生きてたよっ! 君のほうこそ…」 僕はたぶん赤面してしまってたと思う。 「僕も、生きてるよ」 三杉くんはやっと僕の腕から自由になって、にっこりと笑い返してきた。 「ほんとに、手加減なしだったけど」 「君のほうが――引っ張り込んだんだからね! 勝手に死なれてたまるもんか」 「ねえ」 三杉くんは僕の抗議にも構わず、首を上に向けた。 「雨、降ってきたよ」 「――雨?」 そうか、それでこんなに暗くなっていたのか。 僕はソファーから滑り降りた。温もりが一気に吹き飛んで、僕は急いで服を拾い上げ た。 窓の外は確かに雨だった。古いアパートが互いに背を向け合っているその壁と壁の 間に、細かい雨が風にあおられていた。時々窓ガラスの表面をぽろぽろとこぼれる雨 粒が、微かな音を出しているような気がした。 このアパートは通りに面した間口が極端に狭く、敷地の奥へ奥へと増築を繰り返した ような複雑な形になっている。僕の部屋はその迷路の一番入り組んだ場所にあるか ら、表通りの音はもちろん、周囲のどの窓からも死角になっていた。 一応南に向いたこの窓も、見えるのは煉瓦壁とそして煙突が乱雑に重なる屋根ばか りだ。 初めて案内された時の不動産屋でさえ――フランス式の傲慢なユーモアを駆使して さえ――ここがお勧めだとは言わなかったんだ。古いわりに家賃は高いし、はっきり言 って空き部屋がけっこうある。これをいい部屋だ、なんて言ったのは、三杉くんくらいの ものなんだ。 いや、違う。 あの時、僕は答えたはずだ。その不動産屋に、いい部屋だ、って。 僕はこの部屋を、気に入って決めたんだ。一人で暮らし始める機会に、これ以上の 条件はなかったから。 風が窓ガラスをガタン、と鳴らして、僕ははっと我に返った。大きな声で、名前を呼ば れたような感じだった。 『僕は、何から逃げようとしたんだろう』 その言葉が、突然僕の頭に響いた。 まるで僕がもう一人いて、耳元でそうささやいたような感じに。 僕は、くるりと窓に背を向けた。窓枠が僕の背中とぶつかって鈍い音をたてた。 『三杉くんは――』 部屋の中の薄闇に、雨の揺らぎが反射したように見えた。 『どうしてここに来たの。なぜ僕を共犯者に選んだの?』 ソファーの背が僕のすぐ目の前にある。でもソファーは空だった。 「三杉くん――?」 クッションと一緒に、三杉くんのくしゃくしゃになった白いシャツが残されていた。 |
| 踏み段の真ん中が磨り減ってへこんだ階段を、僕は2段飛ばしで駆け下りた。途中
の階で「うるさい!」とか怒鳴る声が聞こえたけれど、無視して1階のホールに駆け込
む。 なぜ?――よりも、バカ!…という言葉が先に出た。 そんな言葉、三杉くん以外に聞かせられる相手はいないんだから。僕のまわりの人 はみんないい人間ばかりなんだよ。 それと、どうでもいい人間と――? ドアから外へ飛び出すと、雨が顔を打った。通りは既に夜の色に落ちていた。街灯が 黒ずんだ支柱の足元だけをぼんやりと照らしている。僕はその先をじっと見つめた。 「なんで僕がこんなことしなくちゃいけないの?」 共犯者だなんて。 からかってみせるのは、それが本音なのをごまかすためなんだ、いつだって。 僕はかあーっと顔に血が登るのを自分で感じていた。どっちへ向かえばいいのか、 いや、それより何をすればいいのか、それさえもわからないくらい、頭の中がぐるんぐる んしている。 「――おい!」 その僕の肩を、強い手ががっしりとつかんだ。そのままぐい、と引っ張って、そしてそ こに若林くんの顔があった。 「何やってんだ、雨ン中でバタバタして」 「――いなくなっちゃったんだ、さっきまで、ちゃんといたのに…」 「あ? 猫がか」 「若林くん」 僕はぽかんとした。一瞬、ほんの一瞬、三杉くんの温もりが指先に蘇ったような錯覚 に襲われて、僕は両手をぎゅっと握り締める。 「まあ大丈夫だろ。猫は雨の時は遠くまで行きっこないんだから。すぐに自分で戻って 来るさ、ひょっこりな。猫てのはそういうもんだ」 「それとも、ほんとの家に戻ったとか――」 「ああ、そうか、預かりモンだって言ってたな」 若林くんは勝手に僕を引っ張って、アパートの軒下に入った。 「俺はちょっとびっくりしたんだぞ。おまえがそういう気分になるなんて、聞いたことなか ったし」 「何が?」 「預かりモンだとしてもだ、猫を飼うなんてのは、信じられないって言うんだ。おまえが …」 若林くんはそこで口ごもって僕の顔を覗き込んだ。 「一人は寂しいんだ、って誰かに打ち明ける気になったんだ、ってな」 「誰がそんなこと!」 僕が抗議しようと詰め寄るのを、若林くんは両手で押さえた。ニヤニヤ笑いが口元に 浮かんでいる。 「まあまあ、図星だからって怒るな」 「僕を、からかいに来たんなら…」 「違うって。おまえんち電話もないからさ、連絡取るだけで一苦労だ、全く。俺は飛脚か よ」 「なに?」 玄関先の古い照明が、ちらちらと瞬く。風と一緒に雨粒がさあっと僕らの頭に降りか かってきた。 「三杉がな、見つかったって。俺のホテルに連絡があったんだ、日本から」 「――な、んだって?」 足元の感覚がふわりと消えたような気がした。 「自分から、居場所を知らせてきたらしいぞ。で、チームには現地合流するからって、 そう言ったらしい」 「どこ、に――いるって?」 僕はよほど間抜けな顔をしていたようだ。若林くんが、逆に驚いてしまった。 「いやそれは――詳しい話は聞いてないんだ。第一報ってーか、とにかく今度の遠征 は予定通りになるって話をだな……」 若林くんの話はもうその先はよく頭に入らなかった。 混乱。まさにそれだった。 「おまえの部屋に――入れてもらえんよな、相変わらず。飛脚はこれで退散するか。じ ゃあな、岬。ちゃんと電話つけるんだぞ」 「若林くん!」 本当はね…と、言い出しかけて、やっぱり後は続かなかった。振り返って怪訝そうな 顔をする若林くんに、僕は思い直してこう言っただけだった。 「電話は、つける。――そのうちね」 「じゃ、全日本で」 ジャケットの襟を引き寄せて、若林くんは小走りにメトロのほうへ向かって行った。 『猫でも、進歩だな、岬』 その別れ際の言葉を引っ張りながら、僕はのろのろと4階への階段を上がって行っ た。 「どうなってんの」 部屋の中は、がらんと冷えていた。 ソファーに近づいて、三杉くんのシャツを拾い上げ、目の前にかざしてみる。 思いついて振り返ると、壁のところに置きっぱなしだった革のトランクは消えていた。 靴もなかった。 「何考えてんだか…」 僕はぼやくくらいしかできなかったが、頭の中では新しい復讐のプランが動き始めて いた。 「まずは電話を引いて…」 シャツを握ったまま、ドアの横を見る。 「それから、いきなり掛けてやるんだ。時差なんて無視して」 いなくなった猫に電話する。 想像すると、なんだかおかしくなってきた。 ないはずの山が見える。そんな錯覚だって、けっこう楽しいものなんだ。 「共犯者の義務だよね」 そう、そして時々はひなたぼっこもしよう。 猫は、朝にやってくる。 〔おわり〕
|
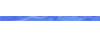 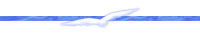 |
| 作者コメント: |
| 甘甘のみーみー。実力行使に出たのはこれが最初のだ ったかも。三杉くんの家出の原因は未だに判明しており ません(汗)パリって本当にこんな所なんでしょうか? |
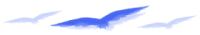 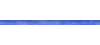 |