| 「――あ、配達、ですか」 「そう。夜まで非番なんだが、急ぎの配達が入ってね」 地上は見る見る眼下に遠ざかっていく。旧型のセスナは慣れた様子で 左右に翼を傾けながら方向を転じた。 「君も退屈してたみたいだったから」 説明はそれだけだった。だが、確かにこれはめったに経験できることで はない。空飛ぶ郵政嘱託職員、松山氏の仕事に付き合えるというのはラ ッキーなことかもしれなかった。 「うわあ、すごいな」 旋回すると、大地が斜めに視界にかぶさってくる。ゆったりと連なる緑 の農地が、鮮やかな色調を見せながら背後にスクロールしていく。 「でも、いいんですか? お仕事なのに、勝手に僕なんか乗せてしまっ て」 「気にしない、気にしない」 松山の父はちらっと三杉を振り向いた。 「それに、家族なら誰も文句は言えないさ」 「っと――」 三杉は首をすくめた。これはもう逃げ隠れできない。 「あいつも妙な奴だし、君も大変だろう」 「そんなこともないですけど…」 と言いかけた三杉をさえぎって、言葉は続く。 「でもまあ、その妙な奴と一緒に兄弟づきあいができるってことは、君も 相当妙な奴ってわけだな」 「はは、ははは――」 さすがは親の貫禄。蛙の親も蛙、であった。 そんな三杉をよそに、松山の父は気圧計を覗き込む。 「――ベルトを、しっかり締めておいたほうがいいぞ」 「えっ?」 と、声を出すより前に、前方が見る見る暗くなった。上からのしかかるよ うに黒い塊がセスナを取り囲む。 がくん、と機体が落ち込んだ。と同時に左右に大きく揺れ、フロントガラ スが一瞬にして滲む。激しい雨だった。雨雲はすぐ外の手の届きそうな 所に渦を巻いて、視界を完全に覆ってしまった。 機体は下から、前後左右から気紛れな力に引っ張られ、あるいは押さ れ、ぎしぎしと関節がきしむような音を立てた。外を見ると、両翼が雨に 霞みながら紙のようにはためいている。ふわっと浮き上がったかと思う と、ぐいっと沈み込み、さながら急流に放り出された笹舟だった。 気流にもまれて何度もエアポケットに落ち込む。何度目かの時に、強い 衝撃と共にエンジンが咳き込むような音をたて始めた。 松山の父は操縦桿を片手にしっかり押さえ、もう片方の手で計器類の ガラスカバーをごしごしこすっていた。なんということか、曇ってしまってメ ーターが読めないのだ。 「えーい、くそ!」 激しいローリングの中、ちらっと窓の外に視線を投げてから足元のパネ ルを蹴っ飛ばす。エンジンがひとしきりグルグル唸って一瞬黙り、そして 一気に息を吹き返した。 ぐん、と加速がついて、機体のきしみが一層激しくなる。横風にあおら れた形で機首を斜めに向けた後、松山氏はタコメーターを睨んで気合と 共にスロットルを引いた。 「心配はいらないよ」 突然松山の父が笑い声をたてたので、三杉はどきっと振り向いた。 「こいつは確かにオンボロだが、オンボロはオンボロなりに自分の生き延 び方は心得てるからね」 通り抜けてきた積乱雲は既に眼下にあった。機体もようやく安定してき たようだ。 三杉は座席に体を沈めた。詰めていた息を吐く。 「いえ、別に心配は…」 「こういうのはなまじ知識があると余計に気を張っちまうもんだからな。君 は操縦の心得があるんだろ」 「えっ?」 「離陸の時はさほどでもなかったが、あの雲を通る間じゅうさ、君の視線 がまるで正確に計器やスイッチ類をたどってるんだもんな、その場その 場の操作の手順通りにねぇ。相応の知識と経験がない限りそんな真似 はできっこないだろ」 三杉はその観察眼に内心舌を巻いた。あの緊張した場面で思い切りよ く危機を乗り越えたばかりか、その同乗者の小さな行動にまで注意が及 んでいたとは三杉にとっても信じられないことであった。 「免許は持ってますが、飛行経験はまだ3ケタですから…」 「おもしろい人だねえ、君は」 別段からかうような感じでもなく、松山の父はしみじみと言った。この人 にだけは言われたくない、と三杉は思う。 もう一度窓から見下ろすと、黒い雲はもうどこにもなく、一面に雲海が 広がっていた。素晴らしい眺めだった。 「ありきたりなイメージだとは思うが…」 しばらく沈黙が続いた後、松山の父が口を切った。 「雲海の上を飛んでいるとね、だんだん雲が羊に見えてくるんだ。羊が背 を寄せ合って目の下一面に広がっているみたいにね。ああ、ここは俺た ち人間の来る所じゃない、ここは羊にしか許されない世界なんだって思う んだ」 「羊…?」 「見えるのは羊の白い背だけのはずなのに、だんだん、その羊たちの世 界の構成物が見えてくるんだな。彼らが食んでいる草地、ゆるい起伏の 丘、その間を縫う小川…。あそこには何でもあるんだ」 操縦桿を握って目は前方に据えたまま、松山の父は語り続ける。光景 は意識に焼き付いているのだろう。 「どう思う? 完全な世界だ。すべて完結している。なのにその世界には 人間だけがいない。奇妙な気分だよ。俺はクリスチャンてわけじゃない が、あれを見てると最後の審判後の世界とはこんなかな、と思うね」 「羊の姿をした神さま、ってわけですか」 三杉はちらりと隣を盗み見したが、松山氏の表情は淡々としていた。 「神さまがどんな姿をしてるか、見た奴はないからね。羊だったとしてもあ ながち奇抜ではないかもしれんぞ」 セスナはまっすぐに飛び続け、雲海もやがて切れ始めた。 「そら、下を見てごらん。左のほうに変わった形の山が見えてくるだろう。 あれはね、アイヌの言葉で『神さまの沓脱ぎ石』って意味の名前を持って いるんだ」 松山の父は確かめるように、ひょいと窓の下に視線を落とした。三杉の 目にも、その山はすぐにとらえられた。 「だけど、わかるかい、その形に見なそうとしても地上からじゃわからな いはずなんだ。もちろん、こんな飛行機ができるずっと昔からの名前だ し、近くに高い山があるわけでもない。一体誰がどうやってそれに気づい たか、だがね」 先住民の文化は、だがこの日本において尊重されてきたとは言えな い。逆に蹂躙と征服の歴史の中に、既にその大半を葬り去ってしまった。 松山の父はゆっくりと首を振った。 「ある種の精神的な感応力かね。肉体は地上にありながら、空の上に神 さまの視点を飼っているんだ。一体、人間の身でそういう視点を持つため にはどれほどの精神の研ぎ澄ましが要求されるか…。伝統文化として継 承されるものが、情報よりもむしろそういった感応力そのものなんだとし たら、我々が失おうとしているものは計り知れないね」 誰かに聞かせるためというよりも、自分に言い聞かせているような松山 の父の饒舌ぶりだった。 三杉はその横顔をじっと眺める。毎日幾度となくその視点を神と共有す るというのは、どういう気分だろう…と、胸につぶやく。そう言えば、飛行 経験のある宇宙飛行士にはかなりの高率で精神的な治療を要する者が 出るという話を聞いたことがある。神の視点さえも超えた、地球のさらに 外側からこの地上を見てしまうことは、肉体に収まりきらない感応力との 破綻を意味するのかもしれない。 「そこには人間だけがいない…」 三杉は口の中で小さく繰り返した。 松山の父はそれに気づいたのか、三杉を見やってわずかに笑みを浮 かべた。 「20年前、空を選んだ時、これは一種の逃げだな、って思ったもんだよ、 我ながらね。初めて社会に出て、さまざまな悩みに直面して疲れ切って いたのは事実だったしね。でも実際そんな地上を離れて空に上がってみ るとどうだ、俺が一番苦しんでいた問題、悩んで悩んで悩み抜いていた 問題がより一層目の前にあるじゃないか。……空はね、結局天国に近い 分、人間にもより近くなる。空に来てみて、それがわかったんだな。悩み や苦痛がその人間の根源的なものであるほど、そいつはどこまでもつい て離れないんだ」 若い日の、そんな苦悩を語りながら、しかし松山の父はずいぶん愉快 そうにも見えた。 「でもお父さんは、今もこの仕事を続けてるんですね」 「そう。空に逃げ場はないって知った。結局、俺を地上に呼び戻したの は、かぐさんだったってわけでね」 ぬけぬけと、照れまくりながら、松山の父はそれ以上説明はしなかっ た。若い頃は、しなくてもいい遠回りをけっこうしちまうもんだ…と言い訳 して。 高度がゆっくりと下がり始める。地上はしかし、ほとんど動いて行かな い。セスナがこのスピードで飛んでいることが信じられないくらいに。 三杉はなぜか、その時松山の声を聞いた。昨日、夕暮れの道を歩きな がら、松山が投げつけてきた言葉だった。 『俺たちがおまえを必要としてるかじゃないんだ。おまえが、俺たちを必 要としているかどうか、だろ』 天は人間を必要としない。では人間は? 神の場所を得る代わりに、人間は地上に何を描こうとするのか。 『俺はおまえに何もしてやれない。だからおまえが自分でなんとかし ろ!』 何もかも一人で抱え込んで、一人で解決してきた。 それが自分のやり方だ、と告げる三杉に、松山はいつも容赦がなかっ た。 『おまえはジタバタみっともないところを絶対に他人に見せない。自分の 力を100%振り絞りながら、さらにプラスアルファの余力でもって、みっと もない所を隠してしまえる。おまえはそんなふうに全能(オールマイティ) だ。でも、それならなぜ、祈るんだ…?』 祈る――。 松山は本当にそう言っただろうか。あの時、三杉は訣別を告げたの だ。松山は納得しなかった。その声、その表情は、もっと別のことを語っ ていたはずだ。 叶わない夢は、それ自体、宗教に似ている。信仰は、叶わないことを悟 った地点から始まるのかもしれない。 「そら、札幌だよ」 唐突に声を掛けられて、三杉は思考を戻した。急いで窓の外を見ると、 山の稜線の向こう側に、なるほど都市らしい塊が紫に霞がかって見えて いる。セスナは機首をその方角に対してやや南に向けた。 空港が近づいている。無線交信のコールサインを出しながら、松山の 父は着陸準備にかかる。 降下とともに、窓の下、地上は現実感を帯びてきた。道路を行く車。住 宅の並び、木立ちの色。どれも見慣れた日常の構成物だった。 人間のいるはずのない場所から降りてきた。こここそが現実であり、逃 れられない行き止まりでもある。 「誘拐犯、ってとこかな」 「えっ?」 操縦桿をゆったりと操作しながら、松山の父は楽しそうにつぶやいた。 三杉が驚いて顔を見ると、同じように目を見返してくる。よりによってこん な時にわき見は…! 「逃げ場は上にはないんだ。わかるだろ、三杉くん」 ニッと笑いを浮かべて、背後を目で示す。そこには、松山氏のいつもの 黒いバッグが置かれている。他には何もない。配達すべき品は何も。 「かぐさんが一切がっさい詰め込んでたみたいだよ。君の、『貴重品』と か、パスポートとか、ね」 「まさか!」 滑走路が迫ってきた。白い大きな文字がその上に読める。天に向かっ て、その存在を示しながら。 「む、無理です、今から東京に飛んでもヨーロッパ行きの最終便は出た 後です。――明日の試合には絶対間に合いませんよ!」 松山の父は落ち着いて右前方の標識灯を見た。 「いいことを教えてあげるよ。札幌から新潟に飛ぶんだ。17時50分のが あるから。で、新潟に19時5分着。同じところから国際線のハバロフスク 行きが出てるよ。これが20時30分発だから悠々間に合うさ。ハバロフス クからはモスクワだろうがワルシャワだろうがヨーロッパ圏にはノンストッ プだ。ただしアエロフロートが素直にタイムテーブル通り飛んでくれるかど うかは君の普段の心がけ次第だが」 |
| 郵便のマークをつけたセスナは、滑走路から小型機専用の誘導路に
入った。夏の陽差しが傾いて、やがて夕暮れを迎えようとしている。 「配達っていうのは僕のことだったんですね…」 無駄な抵抗はしないのが、貴公子たるゆえんであった。まんまと乗せら れたことに対しても、今さらの抗議はしない。 エンジンはそのままで、松山の父は操縦席から腕を差し伸べた。握手 をして、笑顔になる。 「われもの注意、でなくてよかったよ。あの乱気流の中で気を揉むのは たまらんからな」 「ひどいなあ」 三杉は思わず笑い出してしまった。鎧も、飾りもつける必要のない相手 であることを、今また思い知る。この感覚は、数年前に松山に抱いたもの と同質だった。 「カード1枚とパスポートだけで飛んで行けって言うんですね。信じられな いな」 「それで十分だよ。君なら」 松山氏はこの先三杉が向かうはずの西の空を見やってうなづいた。 「本当の武装ってのは、もっと別のものさ。とにかく闘いは闘いだ。決着を つけて来るんだな。あいつは手強いぞ。頑固で、その上諦めがとことん 悪い」 「それは――僕も負けませんけどね。ワガママで意地っ張りなことにかけ ては」 松山の悪態を思い出して、三杉は苦笑した。 「僕は読み違えていました。彼は、正攻法しか通じない相手なんだって、 知っていたのに。――とにかく作戦変更です」 「健闘を祈るよ」 暮れていく空に機影が小さくなるのを見送りながら、三杉は考えた。松 山に会ったら、まず何と言おうかと。 それは最後の宣戦布告になるはずだ。おそらく、長い闘いになるだろ う。 「とりあえず、愛の告白から始めるか」 完全ではない、しかし人間であふれたこの地上。三杉はその住人の一 人であることを、密かに感謝した。 おわり ――愛すべきフライング・ポストマンと、その息子たちに捧ぐ |
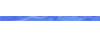 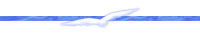 |
| 作者コメント: |
| 飛行機のこととか、見当で書いてあるので正確さは期待 しないでくださいね。フライトについても。三千春さんの経 歴はいつか明らかに…(笑)。 |
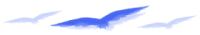 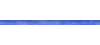 |