| 「どっかで間違っちまったんだ」 反町の言葉に俺は我に返った。試験期間は終わり、俺たちはクラブハウスにいた。話 題の当人は体育部長に呼び出されていてまだ姿を見せていない。 「ぜーったい、変だ。幽霊なんかとはこの世で一番縁のなさそうな人がこんなことになる なんて」 なるほど、それは確かだ。俺は着替えを終えて、自分のロッカーをバタン、と閉めた。 「お前ならともかく、さ」 「何が言いたい、反町」 誰より早くユニフォームに着替え終えていた反町は、パイプ椅子に逆にまたがってさっ きから俺をずっと観察していた。 「日向さんは恐れてる」 「おい…?」 脈絡のない唐突さはこいつのお家芸ではあるが、それにしては顔が完全にマジだ。 「お前だってわかってるだろ。日向さん、この春からあいつの名前をいっぺんだって口に してないんだぜ」 まるで意地張ってるみたいに、と反町は小さく付け加えた。俺は黙って反町を見る。何 を根拠にそういうことを言い出したのかは知らないが。 「この夏だって、決勝の相手が決まったあの時、日向さんはほんとにほっとした顔をした んだ。一瞬だったけどさ」 この夏、それははからずも再会の夏となった。インターハイのベスト4。見知った顔が 揃う中、日向さんはひときわ不機嫌な顔でいた。1年生ながら当然のようにレギュラーの 位置を得ていた日向さんは、しかし準決勝で勝ちをおさめると一人さっさと学校に引き上 げてしまった。第2試合の結果も見ずに。 「南葛と当たるのがそんなに嫌だったのか、ってあの時は思ったんだよね」 南葛はその準決勝第2試合で姿を消した。中学生大会決勝戦のカードの再現か、と周 囲が騒いだわりにそれはあっさりと空振りとなった。第一、再現などありえなかったの だ。夢のありかを示して、あいつは遠く旅立って行ったのだから――その残像だけをくっ きりと俺達に焼きつけて。 あいつが、いない。そのことが俺たちの胸のどこかで宙ぶらりんになっている。日向さ んがそれをどこまで意識しているかは別として。 「あの人は露骨だからな」 「そ。でもってお前は全然露骨じゃない」 反町は少し首をかしげるようにして俺をにらんでいた。そう、まるで宣戦布告をするよう に、だ。 「お前は知ってんだろ。日向さんが、何を恐れてるのか」 ああ、反町。そしてお前も、な。 俺はそう答えるかわりにしばらく反町と目を合わせていた。返事にじれて、反町はぐっ と身を乗り出しかけた。 その時だ。――俺の耳に、微かな音が届いた。いや、音ではない。もっと何か、淡い匂 いのような…。 そう思った途端、俺は駆け出していた。反町が、おい、と声を上げたのがわかったが、 俺の足は止まらなかった。 匂いが、身を切るような勢いで押し寄せてくる。その方向から…。部室の並ぶ廊下を 抜けて俺はクラブハウスのエントランスホールに飛び込んだ。 「わーかしまづ !! 」 背後から反町の声がしたその時、俺は目の前に日向さんを見た。少し背を丸めるよう に両手をジャージのポケットに突っ込み、ゆっくりこちらに歩いて来る。 「――日向さんっ !! 」 日向さんが俺に気づいたのと、俺が叫んだのと同時だった。匂いが――その強い気配 が俺達の足元から突き上げるように爆発した。視界が真っ白になり、どこか遠くで金属 的な衝撃音が聞こえたように思った。 俺は棒立ちになっている人影に飛びついて横っとびに転がった。身を起こそうとして、 はっと気づく。 「―― !? 」 日向さんじゃない。――俺が腕に抱えていたのは、頼りない重さの小さな体だった。ゆ っくりと顔を上げ、俺と黙って目を合わせる。 「ま、ぼろし… !? 」 声を上げようとした途端、俺は我に返った。ホールの壁際に俺は転がっていたのだっ た。周囲は細かく割れたガラスの破片で一面に埋めつくされている。 「若島津 !! 」 反町がどたどたと駆けつけてきた。 「だ、大丈夫っ? 日向さんも…!」 俺はぎくりと脇に目をやった。俺と一緒にそこに投げ出されていた日向さんがうなりな がら頭を振っていた。 「ち、きしょう…。何だってんだ、これは」 呆然と見下ろしている反町の背後から、何人もの声が集まり始めていた。 「偶然だ」 「へええ、そーなの」 反町は頭から信じていないという意思表示をその視線でしてみせた。俺は構わずバン ソーコーをはがし続ける。 「んじゃ、お前がたまたま急用を思い出して走って行ったとこへ日向さんの事故現場が ぶつかったって、そー言いたいわけ」 「そうだ」 「ホールの正面の窓ガラス、上から下まで全滅だったんだぜ。その真下にいて全然無傷 ってのはどう説明するのぉ」 俺はそこで手を止めて、ちょっと日向さんに目を落とした。 「俺のほうが少し運がよかったんだろう」 「悪かったな、俺ぁ運が悪くてよ!」 頭越しに交わされる――しゃべっているのはほとんど反町だったが――俺達の会話の 意味不明さにいらだった日向さんが大声を出した。例によってむき出しにしていた―― 冬だというのに――腕をはじめ、上半身のあちこちに切り傷を作ってしまった日向さんだ が、そういつまでも神妙に座っていられるものではない。 「俺が知りたいのはな、あんなとこにボールを蹴り込みやがったバカ野郎は誰だ、ってこ とだ」 「ボール…?」 反町は俺の顔を見た。俺は日向さんをのぞき込む。 「見たんですか」 「ああ、確か――俺の目の前を横切ってったと思ったが…」 眉を寄せながら、日向さんの語尾がちょっと怪しくなる。記憶があいまいになっている らしい。 「なんせ、いきなりお前が飛びかかってきたからよ」 人聞きの悪い。 「そうしなかったらあんたは今ごろバンソーコーくらいじゃすんでませんよ」 反町がちょっと考え込む表情になったのが目の端に入った。が、振り向こうとした時に はもうもとの軽さに戻っている。 「で、何の用事だったんです、原木せんせ」 「え、ああ、大会までのスケジュールとか、な」 日向さんはくいっと首を曲げて目だけを反町に向けた。 「なあんだ。女の子を怖がらせるな、って話じゃないのか」 「なんだと、反町。俺の顔に文句があるってのか!」 「や、やだなぁ、誤解だってば…」 にっこり笑顔を浮かべながら後ずさりをし、次の瞬間反町は部室を飛び出していった。 日向さんはそれを見送ってフン、と鼻を鳴らす。 「ああ、ほら、まだ動かないで」 「ええい、めんどくせえな。もういい!」 日向さんは俺の手を振り払うと、グラウンド目指して駆け出して行ってしまった。俺の手 に貼りかけのバンソーコーを残したまま。 日向さんは嘘をつけない。 なら、嘘をついてるのは俺のほうか。 |
| 俺はベッドからがばっと起き上がった。 幻が、呼んでいる。俺を。 そんなことは初めてだった。俺は妙に胸が騒ぐのを感じた。部屋の中は真っ暗で、窓 の外から向かいの棟の非常灯の明かりがこぼれているだけだ。 その、窓のそばに幻はいた。 ――若島津くん。 幻は、淡い光を浴びて青白い顔をこちらに向けていた。 ――お前はなぜ俺のところに来た。 それはあの日からずっと俺につきまとっていた疑問だった。寮の窓に日向さんの影が たたずむのを目撃した、あの日から。 ――お前を呼んだのは俺じゃない。 ――うん。 幻はいつもの微笑を浮かべた。胸が、痛むような。 ――でも、行っても無駄だから。 ――あの人は、お前が見えないのか。自分で呼んでおいて、お前が見えないのか。 その言葉を口にした瞬間、俺は後悔した。その答えは既に出ていたのではなかった か。そう、今日……助けた相手がすりかわっていたあの時に。 幻は表情を変えなかった。虚ろな、それでいて何かを訴えるような大きな目だけがじっ と俺を見ていた。 俺は、その時突然わかった。東邦に現われた「幽霊」の姿が俺であり日向さんであり、 そしてこいつであったのは…。 ――そうだよ、若島津くん。 幻は静かにうなづいた。髪にきらりと背後の光が反射した。 ――俺は俺のものじゃない。俺を呼んだ日向くんのものでもない。俺はずっとここにい た。誰かが俺に気づくまで。だから、俺を見た、君のものなんだ。 夜の闇が、異質な冷たさに変わり始めていた。俺はその闇に見覚えがあった。 ――無い、ってことはエネルギーなんだ。有る、って状態を求めて力を持つんだ。風にな って、流れになって、呼び寄せるんだ。 幻の言葉が、虚空に遠く、あるいは近く響いてくる。 ――今日の、あの事故か。 ――俺たち……俺と日向くんはどうやっても重なってしまう。俺は俺に帰れない。日向く んにも帰れない。俺は消えたくない。でも消えないといけない。 幻は、あの、笑顔を見せた。 ――君は気づいてしまったから…。消してくれるのは君しかいない。 俺は手を伸ばした。幻の、胸に、手が届いた。 幻の胸には鼓動があった。幻の体は熱かった。それ以上に俺の体も熱かったかもしれ ない。 幻は逃げなかった。 ――ごめんね。 俺の肩に顔を埋め、幻は、それだけ、言った。 あいつは今、夏にいる。 焦げるような太陽の下で、今ごろ汗にまみれて駆け回ってることだろう。 あいつの動きは軽い。あいつの動きは人を熱狂させる。 あいつの頭のてっぺんから足の先まで、体じゅうが弾けるようにその言葉を叫んでい る――「サッカーが好き!」と。 だからこそ皆があいつを愛するのだ。あいつのプレイを愛し、あいつの笑顔を愛し、あ いつの夢を愛している。 けれど、と俺は思う。 あいつは自分を愛しているだろうか。 俺はいつか、それをあいつに問いかけてみたいと思う。あいつはあのアッケラカンとし た顔で笑い飛ばすことだろう。 幻は消えてしまった。 あいつが、俺が、そして日向さんが――それと知らずに抱えている空白を結びつけた 幻は、もう、いない。 俺はまた変わりばえのしない毎日に戻った。日向さんは何事もなかったようにボール を追っている。いや、あの人には最初から何事もなかったのかもしれない。 反町は始末に負えない奴だが馬鹿ではない。出るべき答えが消えた今、あの好奇心 とやらは決して無駄な後追いはしないはずだ。時々、あの見えすぎる目で俺を無遠慮に 責め立て、そのつど俺はちょっぴり苦い思いを蘇らせるだろうが…。 そして俺は断じて日向さんに言ってやるんだ。――あんたは世界一のトーヘンボクだ、 ってね。 あいつの、まぼろしの、せめてもの代わりに。 〔終〕
|
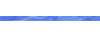 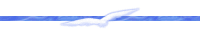 |
| 作者コメント: |
| このまぼろしはこの後もシリーズのようになぜか続いて います。いろんな組み合わせやシチュエーションで。オカ ルトというほどではないけど、まあ、青春は謎だらけとい うとで(笑)。 |
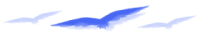 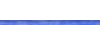 |