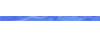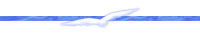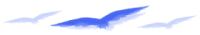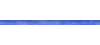| 「なんや蒸してきよったなぁ。かなわんわ」
通りすがりの中年サラリーマンの声が耳に届いた。早田はステッキチョークで路面に数字
を書き付けている先輩を待ちながら、ミニパトの運転席にいた。
「あれぇ? ミニパトにオトコが乗っとるでぇ」
「ホンマや。オトコのおまわりや。なんやぁ? ケッサクやな、はははは、は…」
行き過ぎかけながら車内を覗いた学生風の二人連れは、早田と目が合った途端笑いを凍
りつかせた。ビクン、と目を逸らしてぎくしゃく早足に姿を消す。
「アホか」
早田に自覚はないが、シチュエーション次第ではこの眼光、やはりその筋の人間にも負け
ない殺気があるのだ。
「…なんや?」
緊張をはらんだ人声が聞こえた気がして、早田は歩道の方へ首を回した。先輩も同時に
気づく。
バックファイアーのような重い音。続いてもう1回。
「事故 !? …いや、違うわ!」
「……先輩、無線、頼んます!」
「早田くんっ!」
夢中で車外に飛び出す。歩道を流れていた人々の足がこちらでは凍り付き、向こうでは
大きく乱れて波立っていた。悲鳴のような声が渦巻き、その中心がいきなり割れた。
「どけー、どかんかい! 見せモンやないぞ!」
早田が見たのは赤いアロハシャツを着た30前後の男だった。通行人を突き飛ばすように
しながら雑居ビルに駆け込んで行く。そしてもう一人、二十歳前のパンチパーマの少年がも
たもたとその後を追って行った。中型のボストンバッグを重そうに下げている。通りかかった
人々が悲鳴を上げながら逃げ惑っていた。
「…なんや、どうした!」
「あ、ケイサツや!」
駆けつけた早田を見て、人垣の中から声が上がる。それに気付いたのかどうか、男がビ
ルのステップの上でちらっと振り向いた。ちょうど、ブロックの向こうからパトカーのサイレン
が重なり合いながら響いてきたが、早田は応援が到着するのを待つ気はなかった。幅の狭
いエレベーターホールを奥に走って行く男たちの後姿を睨んで、ビルに飛び込む。
入れ違いのように中の飲食店などにいた客たちがわれ先に逃げ出して来た。その直後で
ある。ずーん、と足元から思い地響きがした瞬間、爆発音が耳をつんざいた。硝煙臭い熱い
風がビルの正面口を吹き飛ばし、道路まで一瞬砂ぼこりでもうもうとなった。
「どうしたんや…!」
悲鳴や怒鳴り声が渦巻く中を乗り越えるように駆け付けて来た制服の警官たちの先頭
に、開襟シャツ姿の刑事がいた。鴨池署の保安課長である。
「爆弾か! このビルの…奥か !? 」
「まだ、人質を取って、立てこもってるんです! 1階の奥のサラ金に、犯人らがいてて…」
交通課の制服姿のまま、先輩婦警は青ざめた顔で警笛を握り締めていた。無意識に汗が
じわりと噴き出してくる。早田は飛び込んで行ったまま、戻らないのだ。
「なんやて! 早田て、あの新人か !? 」
『あの』の意味は署内の人間なら即座に伝わる。少々髪の薄いその刑事は、ハンカチで
額をごしごしとこすった。
「人質はサラ金の事務員らか。客はおらんかったんやな?」
刑事は無線で署に連絡を取ると、警官たちにビルを包囲するよう指示した。パトカーが
次々と到着する。
「爆弾仕掛けたて、続けて3本、電話があってな…」
「最初の1件は結局なんにも見つからんと、カラブリでした。イタズラの線で済ませかけたん
ですどなぁ…」
合流した捜査1課の刑事と、低い声で情報を交換する。その間にも、ばたばたと周囲の動
きは慌ただしい。テロなどの線が絡むならさらに公安とも連動しなくてはならないし、強盗の
線だけなら刑事部が中心になる。
「ここの、犯人の一人が爆弾らしいものをちらつかせとったそうです。ビルの前でちょっとも
み合いになって、その時に目撃されてます」
「強盗の居直りにしては小道具が派手やなあ…。このあっつい時に、しんきくさいこっちゃ」
刑事は難しい顔で腕を組んだ。
「交通整理の丸腰の警官が一人で飛び込むやて、ホンマ無茶しよるわ」
「警部、あきません、ホールのほうから様子窺ってみましたけど、犯人からはどう行っても丸
見えですわ! 来たらもう1発火ィつけるて、わめいとりました」
機動隊員と戻って来た若い刑事が顔をしかめて報告した。
「裏手のほうも回らせてみましたけど、向こうは何人か手分けしとるようです。威嚇射撃して
きよりました」
「なんや、左翼とヤクザがまとめて来よったゆうんか…」
保安課長はいよいよ顔を赤くして無線にかかる。
「あの…」
交通課の先輩婦警が横からそっとその刑事に手を上げた。
「早田くんは…早田巡査はどうでした? 中にいてませんか?」
「いや、それがな、ホールのほん口のあたりは一番爆発がひどうてグチャグチャなんや。人
がおるようには見えんかったな…」
「えー!」
婦警さんは白い手袋を開いたり握ったりして泣き顔になった。早く係長が来てくれないと。
「何が目的なんや。要求は何なんや…」
ビルの正面をぐるりと囲んで待機している機動隊員たちの列がざわざわと動き出した。
|
「……しもたなぁ」
早田は姿勢を変えて足を伸ばしてみた。靴先がコンクリートの小さなカケラを弾いて、乾い
た音を響かせた。
思ったより記憶ははっきりしていた。時間の感覚もある。耳だけは爆発音の残響にワンワ
ンしていたが、痛みに類するものは体のどこにもない。
首を回して周囲を見ると、すぐ横に制帽が落ちていた。
「ここやと、動けへんな」
早田の位置からはサラ金の入り口付近が斜めに見えている。ドアのガラス越しに人影が
動いているのもはっきりわかった。それはつまり犯人側からも早田が見えるということにな
る。
「人質がおるみたいやし、弱ったな…」
1対1なら、あるいは数のハンデが多少あっても、突っ込む自信はあった。しかし人質がい
るならそうもいかない。こちらが警官であるということは、それだけで犯人を刺激する度合い
が高いのである。
早田はそーっと手を伸ばして制帽を引き寄せ、ガレキの間にうまく隠した。このまましばらく
様子を見るしかない。
「外は大騒ぎしとるやろな…」
さっき聞こえていたサイレンの音は、集まっている府警の応援の多さを物語っていた。な
んとかうまくいくだろうとは思う。だがそれがいつになるか、被害が最小限に食い止められる
か、問題はそれだった。
「俺一人やと、こんなもんや。なっさけないなぁ」
早田は上を振り仰いだ。コンクリート壁の崩れた中から黒い鉄骨が半分むき出しになって
ぶら下がっている。そのさらに上に、吹き抜けの高い窓がガラスを半分以上吹き飛ばされて
ぽかんと開いていた。
「だいぶ、暗なってきたな」
早田は反射的に腕時計に目を落とした。が、針は数時間前の時刻をさしたまま動いていな
かった。あきらめてまた犯人のほうを窺う。中で男の悲鳴のような声が響いていた。人質は
何人だろう。注意をそちらに集中しながらそろそろと体を起こしきり、より安全なように壁側
に身を寄せた。もたれて大きく息をつく。
「持久戦かもしれんな。延長戦…あれは嫌なもんや」
とりわけ自分は手出しのできない状態で、勝負の決着だけが先延ばしにされる。早田は
遠い昔の、忘れられない経験を思った。
「…ああ」
早田は制服の胸ポケットから、小さいマイクのようなものを取り出した。親指でスイッチを
入れ、小さな電源ランプが赤くついたのを確かめる。これは無事だったらしい。
「小野田」
マイクに向かって早田はささやいた。
「俺は動けん。一人や。こんな、待つだけしかできんのは嫌や。…小野田、おまえ、なんとか
してくれ」
早田は返事を待つかのように言葉を切った。かわりに、不気味なまでの静寂が周囲に広
がる。
「おまえは約束したやろ。今は仕事をやる。やらなならん仕事がある。けどそれが済んだら、
俺と、またサッカーやるて。そやろ、小野田…」
重いため息だった。一度目を閉じ、それからまた機械を睨む。
「こら、返事せえ。おまえはスッコイで。俺にばっかりしゃべらせて、自分は何にも返事せえ
へんやないか。うん、でもええ、そや、でもええ。いっぺん、俺にちゃんと返事してみい!
…俺、アホみたいやないか。おまえが約束やゆうたからて、赤んぼみたいに、おとなしゅう
待っとるだけや。俺は気ィ短いねんで! これ以上返事せんのやったら、仕事やろうがなん
やろうが、そっから引っ張り出したるからな!」
「誰や… !? 」
ドアがばたん、と開いた。赤いシャツの男が首を突き出して見回している。
「ケイサツか? 近づいたら人質ごと吹っ飛ばすてゆうたやろ! おかしな真似したら、さっ
きの警官みたいになるで!」
「…なんや、俺のことか。俺、殺されたんか?」
早田は壁に張り付いたまま目を丸くした。再びドアは閉まり、また中で言い争う声が響き始
める。一体何を交渉しているのやら、相当えげつないやりとりのようだ。
「…ちょっと、あんた!」
「えっ?」
早田は突然降ってきた声にびっくりして上を見た。
「おまわりさん、こっちです…」
さっきの吹き抜けの窓とは向かい側にあたる梁材のへりから、老人の顔が小さく覗いてい
た。こういう場にまったくそぐわないような、人の良さそうな顔だった。
「ちょっと、上がって来られませんかいな…」
早田は老人とドアのほうを交互に見やった。それからそろそろと立ち上がって手袋を取り、
ぼろぼろに焼け焦げた制服を脱いだ。壁の陰から出ないよう気を配りながら、せっ、と気合
いを入れて梁に取り付く。
「すんませんな、声が聞こえたもんですさかい…」
「おじいさん、出られんかったんですか」
身なりの良い、60から70才くらいの老人だった。よじ登ってみるとそこはエレベーターのシ
ャフト内である。老人はその床にぺったりと座り込んでいた。
「騒ぎが聞こえて、逃げようとしたんですけど、私だけ乗り遅れましてなあ、次のに乗ったら、
すぐ途中で何や爆発してエレベーターがこないになってしまいましてな…」
お年寄りを押しのけて逃げるとは…、と早田が一人憤って黙っていると、老人はほわん、と
笑顔を見せた。
「私も腰が抜けてしもて、動けんとおったんですわ。すんませんけどな、連れて出てくれしま
せんやろか」
早田はちょっとあわてた。
「…い、いや、そうしてあげたいんですけど、今まだ犯人がこの下にいてるんです。見つかっ
たらこっちもしまいやし、中の人質も危ないんです」
「そら、難儀ですなぁ」
のんきな反応に面食らいながら、とりあえず早田は老人と並んで座った。怪我がないか大
ざっぱに調べたが、外傷はないようで、言葉通り腰が抜けただけらしい。
「おまわりさん、それ、無線ですか? 外のケイサツの人らに助けてくれ言えしませんの
か?」
老人が、ベルトに付け替えた小さな機械を指して尋ねた。
「さっき、誰どーと話してはったん違いますか」
「ああ、これは…違うんです」
早田は苦笑した。どうやら小野田への愚痴を聞かれていたらしい。
「電話の発信だけ、できる機械で、伝言ダイアルとかポケベルに似てて、向こうの受信ステ
ーションに自動録音してくれるもんなんです。ナマで会話はできんのです」
「はー、そないでっか」
老人はキツネにつままれたような顔でうなづいた。早田も実はメカニズムまでは詳しく理解
していないのだ。これは小野田が自分で作って早田に渡したオリジナルの小型通信ユニッ
トだった。NTT回線に仲介させているものの、受信自体は小野田のパソコン環境で処理し
ていて、既成の通信サービスとは一切関係がない。
「俺がこれで言うたことが向こうで記録されて、たまったとこを相手が受け取るいうやり方や
から、今言うてすぐどうこうはできんし…」
そう、唯一の可能性としては、小野田がたまたま受信記録を聞くタイミングが合う、というこ
ともなくはないが…。
「なんかややこしい連絡の仕方しはりますんやなあ。普通に電話か手紙ではあきませんの
か?」
「あいつは、仕事が忙しいて、自分でも今どこにいてるんかいつ何をしてるんかわからんくら
い閉じこもっとる男なんです。嫁さんもおるのに、普通の人間らしい場所には全然出てこー
へんから、こっちで一方的に言うこと言うとくしかないんです」
早田は自分に言い聞かせるようにつぶやいた。手を、ベルトのその機械に当て、ちょっと
ため息をつく。小野田のことを考えると、何度でも出てしまういつものため息だった。
「ほな、自分でなんとかするよりないですな」
老人がいきなりぽん、と早田の手をたたいた。驚いて老人の顔を覗き込む。
「なあ、おまわりさん、私にはとても無理ですけど、あんたさんなら身が軽いでっしゃろ」
老人は向かい側の窓の外を見ていた。
「このビルはちょっと外からはわからしませんやろけど、裏手の別のビルとうまいこと背中合
わせになってましてな。このビルの3階の張り出しが、そのまま裏のビルのパーキング棟と
つながるように設計してあるんですわ」
「…おじいさん?」
早田はあっけにとられた。
「よろしいか、ここが肝心やな。裏のビルの最上階は、××組の若頭が事業の隠し事務所
に使こてるんですな。おまわりさん、あんた、そこへ行って話を通してきてほしいんですわ」
早田はごくりと唾を飲み込んだ。この老人、一体…?
「ここのサラ金は××組のもんがやってて、その筋の融資に手広う顔をきかせとったんです
けどな、ある議員のせんせへの資金を動かす時にこげつきをやらかしてしもたんですな。ま
あ、内輪もめの一種ですわな。今日のこれも、言うたら打ち上げ花火ですわ。示しがつか
ん、いう意思表示に、脅しをかけるのが目的でっしゃろ。血の気の多い若いもん使こたせい
で余計な騒ぎになってしもてますけどな」
「え、えと、ほな、話を通すて…俺は、どないしたら…」
老人は懐から袱紗に包んだものを取り出した。早田の手にゆっくりとそれを持たせ、また
柔らかい笑顔を見せる。
「これを若頭に見せるだけでよろしいわ。それでちゃんとわかりますやろ」
早田は手にしたずしりと重いそれをじっと眺め、老人に目を戻した。
「やってくれはりますな。あんたさんなら、行けますわ」
「……」
早田はしばらく黙って老人と目を合わせていた。早田にはその時、違う光景が見えていた
のだ。
『…俺は一人ではどうにもでけへんことばっかりや。自分で一番ええ思う通りやってるつもり
でも、知らん間に行き止まりの道に入ってしもたりする。安心なことは一つもあらへん、わか
らんことばっかりや!』
「おまわりさん」
老人が言った。
「あんた、ええ場所知ってはるみたいですな。あんたが言うてはった約束の相手も、あんた
自身も、その場所のこと、よう知ってはる。そこへ行かはったらええやないか。行けるか行
けんか、そればっかり考えてる者と、まずその場所を知ってる者との違いですわな。…あん
たさんなら、行けますわ」
早田ははっと我に返った。老人の言葉はすぐに現実の笑顔に収まった。どこまでが本当
で、どこまでが幻覚だったのか。
「わかりました。ほな、行ってきます」
預かった物を尻ポケットに突っ込んで、早田はシャフトの上にさらによじ登った。3階のフロ
アに立つともう遠慮なく駆け出す。言われたように裏手のバルコニーに立つと、下から熱い
風がもあっと吹き上げた。
「…そうか、あのおじいさん、エレベーターで下へ逃げるつもりやのうて、3階へ行くとこやっ
たんや!」
街はすっかり暮れて、ビル街にはいつもと変わらないネオンの海が広がっていた。見下ろ
すと、ビルのまわりを点滅するパトカーのサインや警官の群れがものものしく囲んでいた
が、手を振るわけにもいかず、早田は目の前に黒くそびえる大きなマンションに向かって駆
け出した。
その時、早田の目をちらっとかすめたものがあった。
「…!」
ネオンに縁取られた四角いビルのシルエットの向こうに、駅前の電光ニュースの帯が浮か
んでいた。
「アホ、小野田! おまえは…」
大阪の熱帯夜は、まさにこれから始まる。電光ニュースの黄色い文字は、ぐるぐる回りな
がらこう告げていたのだ。
『うん。そや』
そや、早田。オレはいつでもおるで。
|
「ああ〜、早田くん! よかった、よかったわぁ!」 真っ先に駆け寄って来たのはずっと警笛を握り続けていた先輩婦警さんだった。丸山係長 もすぐ走って来る。 「すみません、えらい面倒かけました」 係長に、先輩に、ぺこりと頭を下げる。ランニングシャツに制服のズボンだけ、という姿なの で、係長も泣き笑いみたいな顔になってしまった。 「2階に取り残されてた最後のケガ人のおじいさん…?」 「はい」 「そんな人、いてました?」 丸山係長は背後を振り返って確認を取った。 「人質の事務員4人は保護されて病院に送って行ったけど、そういう人は一人もなかった て、いうことやけど」 「そうですか。それなら、いいんです」 早田はもう一度電光ニュースのビルを見上げた。もちろん、通常のニュースが流れている だけだ。ほどなくこの立てこもり犯の事件も流されることだろう。 「ええことないわ! こら、早田!」 人だかりから猛然と抜け出してきたのは鴨池署署長である。 「おまえはなんでそうムチャばっかり起こすんや! おまえのボロボロの制服があっちで見 つかって、みんなビビったんやぞ!」 「すいません、署長」 早田はまた素直に頭を下げた。それから思い直して背を伸ばし、きちんと敬礼する。 「な、なんや、いきなり…」 警官が上官に敬礼して驚かれるようでは困りものかもしれない。早田はまたくるっと向き 直り、丸山係長にささやいた。 「俺、やっぱり代表に行かしてもらいます。署長、怒らはるかな」 「さあ…」 係長は早田の肩に手を回してささやき返した。 「案外、寂しがらはるかもしれへんね」 そう、早田はそんな悪徳警官であった。 〔END〕
|