悪徳弁護士シリーズ・2
NEUTRAL
| 「で、では、彼は切り捨てろと !? 」
「誤解なさっては困ります。私は可能性の一つとして挙げただけです。その中からどれを選択する
かはあなたのお気持ち次第でしょう」 「う、うぬぅ…」
思わず椅子から浮かしかけた体をまた重く沈み込ませる。額に滲み出す汗をハンカチで何度も
こすり、会長は言葉を絞り出した。 富士山を間近に望む広大な敷地に、その洋館造りの別邸はあった。都心から車で1時間少々
とは信じがたいほど、緑の自然は手付かずのまま残されている。ハイウェイのインターチェンジは 近いものの、ここの主の意向で別荘地やカントリークラブ等の開発は巧みに遠ざけられていたか らだ。 だが屋敷の一室では、その高原の清澄な風とも隔てられた重く暗い空気が澱んでいた。
「しかし、それではリスクが大き過ぎやせんかな」
「こうなった以上はいずれにしてもリスクを避けることはできません。ご自身も多少泥を被ることは
覚悟なさらないと」 「た、多少って君…。多少で済むと言うのかね」
どこか魚のそれに似た大きな目がぎょろりと動いた。だがそれは長年に渡って強大な力をふる
ってきた権力者の象徴では既になかった。 「…幸い彼は有能な男です。各方面でその実力を発揮していましたからね、それだけあなたの選
択の幅も広がるわけです。最も遠く、最も影響の少ない対象を選ぶことです」 指が静かにチャートの一点を指した。
「ぐっ、しかし、井沢君、これは…!」
「政治資金のルートというものは元来不透明なものと決まっています。暴露すればまわりまわっ
て自分が困ることになる連中ばかりですからね。取り立ててあなたの銀行だけに矛先が向くわけ ではありません。融資先についてはあくまで書類上の名義で通せばいいでしょう。国税局のほう は私から手を回しておきます」 「…」
青ざめた顔で声もなく見つめる相手に、井沢はまっすぐ視線を留めた。
「名を残すか実を残すか、です。もちろんそれを選ぶのはあなたご自身というわけですが」
彼は文字通り震え上がった。強制はしない、という柔和な笑みの中に底知れぬ威圧感がある。
「う…、そ、そうだな。わかった。すぐ手を打とう」 細かく震える指で電話のボタンを押す。別室で待機していた秘書はすぐに出たようだ。鬱血した
ような色の唇がわなわなと動き、短い言葉を低く取り交わす。井沢はそれには背を向けて庭を見 下ろす窓辺に立った。 重く垂れこめていた雲間からわずかに陽光がこぼれ始めている。その光を呼び込むような楽し
げな笑い声が遠くで弾けていた。子供の声らしい。確か会長は子供もみな独立して、夫人との二 人暮らしだったはずだが。井沢がそう思った時、背後から声が掛かった。 「折り返し、東京から電話が入る。い、いや、単なる形式だが一応理事会を通したということにし
ておかんと…」 「お立場はお察ししますよ」
笑顔で応じられて会長の顔がさらに青ざめた。言葉に詰まり、それから落ち着きなく視線を背後
に投げる。 「…さ、まあこちらに掛けたまえ。どうだね、一杯喉を潤しては…」
「いえ、せっかくですが、そろそろ失礼する時間ですので」
棚に手を伸ばしてブランデーの瓶を下ろしかけた会長が、ぎくりと井沢を振り返った。
「や、まさか、井沢君。冗談だろう。まだ状況がどう動き始めるか見守っておらんと…。せめて今
夜一晩はうちで…」 「これ以上私で役に立てるようなことはありませんよ。既に開幕ベルは鳴ったんです。あとは座っ
てご覧になっていてください」 「き、君…!」
コートを取って袖を通しかける井沢に、会長はあわてて声を掛けた。
「じゃ、どうだろう。また日を改めて一緒にゴルフにでも…」
「あいにくですが、私はゴルフには興味がなくて…」
会長の意図は明らかだった。非常事態だったとはいえ、内情を見せ過ぎたのだ。そんな相手を
むざむざ手放すような真似は、今後のことを考えても危険極まりない。とにかく内部に取り込むこ とだ。そう考えたのは無理もない。これまでも何度となく顧問弁護士として迎える話を断られてい るだけに。 「では早いうちに一席設けよう。閣僚の歴々も揃うんだ、君も顔を通しておいて損はあるまい。あ
あ?」 ゴルフ、料亭での接待。いずれも財界の中枢と政治権力を結ぶパイプの確認作業である。そこ
に顔を通させる、というのだから断る理由はないはずだ。 「お気遣いは有り難いですが、所定の報酬さえいただければそれ以上のことをしていただく必要
はありませんよ。口が固いのは弁護士の職分ですから、ご心配なく」 井沢は胸ポケットから手帳を取り出した。
「今回の相談料ですが、例の債権の名義書き換えという形で手を打ちましょう。あちらの団体に
顔を立てたいとお考えならこちらが得策かと思いますが」 「君ぃ…」
渡された振り込み先のメモを呆然と見下ろして会長はうなった。が、井沢の姿は厚いドアの向こ
うに消えた後だった。 「か、会長…!」
隣室から秘書が青い顔で飛び込んできた。
「どうします。あれは…!」
外部に洩れるはずのない極秘の一件であった。露見を恐れて数年間の凍結を図り、いわゆる
ほとぼりの冷めるのを密かに待っていたのである。 「現在の評価額は !? 」
「変動相場での概算ですが…」
メモの走り書きを渡す秘書の手が震えた。その桁数を一瞥して、会長は息をのむ。
「これを…渡さないなら…というわけか」
今度こそ、選択の余地はないようだった。
|
| 「あの、お帰りですか?」
吹き抜けの階段をひとりで降りてきた井沢を見て、執事が目を丸くした。 「ああ、駅までのバスの時間を教えてほしいんだが」 「バス、でございますか?」 主人の指示を待たずに客を帰してよいものか…という当惑ぶりが明らかだった。しかもバスとは …。 「いいんだ。会長は今取り込んでおられるから、私はお邪魔にならないよう、先に帰る」 「はあ…」 怪訝な顔のまま執事は備忘録を取り出した。 「門をお出になって左に坂を下りますと、三本松の向かいにバス停がございます。ただ、このあた り本数が少ないものでして、あと30分程お待ちいただくことに…」 「構わないよ」 井沢は安心させるように笑顔でうなづいた。と、横のドアが開いて和服姿の30代半ばの女性が 顔を見せた。会長の末娘である。夫はグループの海外支社の一つを任されている。なるほど、今 回の内部抗争で一族に緊急招集がかかったということか、と井沢はすばやく考えた。 「蔡野さん、お父様はどちらかしら? あら、すみません、お客様でしたの」 「いいえ、お構いなく。今失礼するところですから」 背を伸ばして向き直り、静かに会釈する。その紳士的な物腰に、父親譲りの大きな目がさらに 見開かれた。 「どなた…?」 ドアが閉じると同時に執事にささやく。 「弁護士さんですよ。本社の顧問弁護士さんではなく、と旦那様がわざわざご指名だったんです。 それ相応の方だと思いますが」 「あんなに若くてらっしゃるのに…?」 まだ少しポーッとしながらため息をつきかけた時、ホールの吹き抜けの階段から鋭い声が響い た。 「蔡野さん! すぐ来てくれ、会長が気分が悪いとおっしゃって…! あ、お嬢様、大変です、また 血圧が上がってしまわれたらしくて…」 手摺から身を乗り出している秘書の取り乱した様子に執事と末娘が顔色を変えた頃、その騒ぎ はもちろん届かない場所で井沢はゆっくりと歩を進めていた。 車寄せから門のほうへ向かう途中に小さな築山が左手に見え、その向こうに芝生の庭園が 広々と続いていた。そこに元気な声が駆け回っていたのだ。 「ヒロー! 次、ボレーやるからこのへんにパスな!」 「オッケー、行くぞ、そらっ!」 さっき会長の部屋から聞こえていた声だ。小学生の男の子が二人、大きな声を上げながらボー ルを追っている。 「けっこううまいもんだな」 そこはさすがに外国育ちのゆえんかもしれない。井沢はなんとなく足を止めた。が、それは不幸 を呼び込む元となってしまった。 「わー、おじさん! 気をつけて!」 いきなりコースが狂って襲って来た流れ球でも、それに反応できない彼ではない。高さとスピー ドを瞬時に計算して軽くジャンプすると、胸でストップした。反射的に動いてしまったことに少々自 己嫌悪を感じたが、気がつけばボールはしっかり右足の下に押さえられている。 「すっごーい! おじさん、今の今のすごいなぁ!」 「おじさんおじさん、もう一回見せて! ねっ」 二人の男の子は勢い込んで走り寄ってきた。興奮して目を輝かせている二人にちょっとたじろ ぎ、それから自分の胸元に目を落とす。アクアスキュータムのコートの真ん中に、丸くくっきり跡が ついているのを見てから、井沢は顔を上げた。 「ま、いいけど…」 トウでぽんと球を浮かせ、足で数回、膝から胸に1回ずつリフティングでヘッドまで繋ぐ。 子供たちはわーわー叫びながら手を伸ばしてそれを取ろうとするが、井沢は平然とヘディング で前に打ち出した。 「こら、サッカーは手を出しちゃファウルだぞ」 二人は争ってボールに追いつくと、井沢に向かってぽーんと高く蹴り上げた。 「おじさん! ボレー、ボレーだよ!」 「なに?」 それにしてもボールが高すぎる。このままではオーバーヘッドでもしろというのか、と井沢が一 瞬迷ったその時、背後からぬっと手が伸びた。 「へへ、ナイスキーパー、だろ」 カットしたボールを抱え、反町は親指を立ててみせた。井沢の姿勢が一気に警戒の構えに入 る。 「遠慮せずにさ、オーバーヘッドを見せてやればよかったのに、井沢」 「ひどーい、ひどいよぉ! なんで邪魔すんのぉ?」 「ボレーをしてもらおうと思ったのにー!」 抗議の声を上げながら突進してきた二人の男の子にくるりと向き直ると、反町はボールを持っ たまま派手に両手を広げた。 「ねえ、君たち、このおじさんが誰だか知らないだろ」 「おいっ…!」 井沢が割り込もうとしても、熱心にうなづく子供たちと反町はそれを完全に無視して話を続けて いた。 「でもすごくうまいんだよ、この人!」 「そりゃそうさ。だって日本代表だぜ」 反町の言葉に、二人は歓声を上げた。「元」だ、「元」!…とさえぎりかける井沢を押しのけて、 反町は兄のほうにボールを渡す。 「で、提案なんだけど、もっと大勢で練習したくない? このおじさんにコーチしてもらってさ」 「えっ、いいの? 今?」 「そうだよ。一緒に行こう」 当人の意思などそっちのけで話が進んでいく。反町ひとりが相手ならまだしも、第三者、しかも 子供を前にしては井沢は強く出られないのだ。むろん、反町はそのへんの井沢の性格は計算済 みである。 「反町っ、何の真似だ、これは…! それにどうしてこんなとこに…」 両方から子供たちにはさまれて門の外に引きずられながら声をひそめて叫ぶ。 「おまえを助けに来てやったんじゃないか。感謝しろよな」 「えっ?」 門柱の脇に停めてあったオフロードバイクのエンジンをかけると、反町はにっと笑った。 「いいか、道のあっちからは検察庁の連中がこっちに向かってる。で、こっちからはプレス関係の 皆さんが総動員で押しかけて来る。ま、どっちもあと15分以内、だな」 「なんだって…?」 井沢はぱたりと足を止めた。男の子たちが不思議そうに見上げる。 「三ツ石スキャンダルに新展開、検察庁ついに重い腰を上げる!…ってとこかな。ちょっとしたス クープ記事が引き金になったみたいだよ」 「…まさか、おまえが !? 」 絶句する井沢に笑顔を返しておいて、反町は少年たちを見下ろした。 「君たちのおじいちゃんは今からすっごく忙しくなるんだ。だから、しばらく好きに遊んでても叱ら れないよ」 「フーン、でもどっちでもいいや。だっておじいちゃん、サッカー一緒にやってくれないもん、どー せ」 「うん、早く行こう行こう!」 反町はそれを聞くと笑いながら二人をバイクに乗せた。 「よし、じゃ、近道するぞ! つかまってろー!」 「わーい!」 「反町っ… !! 」 ひとり取り残された井沢は、道を外れて藪の中を下り始めたバイクを追う。 「この下にさ、少年サッカーの合宿所があるんだ。さっき寄ってコーチを連れて来る約束をしとい たからな。早いとこそんなスーツ脱いでジャージ姿になれば、どっかの悪名高い弁護士だなんて 誰にもわかりゃしないって」 「…おまえはな、なんだってそう無理にこじつけて俺にサッカーをやらせるんだ!」 「いいからいいから」 反町の言った通り、ほどなく広いグラウンドが目の前に開けた。40人ばかりの少年たちがめい めいボールを追っている。 「な、東京から来たジュニアのクラブだ。おまえの名前を出したら感激してたぜ。変な話だよな、こ っちのやつらは今のおまえの仕事には興味がない。向こうの連中はおまえのウラの正体に気が つかない。何でも自分の専門中心に見てるから、肝心のとこがわかんないのさ」 「おい、正体って、どういう意味だ!」 急な斜面を駆け下りて追いついてきた井沢は、反町の肩を後ろからつかまえた。あまり息を切 らせていないのはさすがと言うか。 「安心しろよ。おまえが残した導火線は知られちゃいないから。俺だってあれに触るのは怖いも んね」 反町は手を伸ばすと井沢の髪をぎゅっと引っ張った。 「じゃ、俺はここらで消えるよ。取材の旅の資金も十分うるおったし、しばらく帰って来ないと思う けど…」 「おまえはな…!」 「愛してるよ、いざわ」 耳に一言ささやいておいてぱっと身を翻すと、反町はエンジンをふかした。 「待てって言うんだ! …おい、反町!」 「しっかりコーチしろよー! 若いやつに負けないよーにねー!」 練習している横をバイクで抜けながら声を掛けたらしく、クラブのコーチたちがこちらを振り返っ て手を振った。もうしかたがない。 「ね、ノブ、あのおじさん、キスしてったよ」 「挨拶だよ。さよならの。ね?」 目撃者が外国育ちでよかった。井沢はなんとか笑顔を見せてから、もう一度反町が消えていっ た方を眺めた。 「結局、返事をしてやらなかったな。あれはあれであいつの本音だったんだろうに」 待っているうちは現われず、忘れた頃に襲ってくる騒ぎの元凶。きっとまた降って湧いたように 姿を見せるに違いない。井沢は脱いだコートを腕に掛けると、某大手銀行会長の孫たちの背をぽ んとたたいた。 「さあ、行って仲間に入れてもらおう。えっと、ボレーだっけ? 今度はうまくボールを送るんだぞ」 「わー、やったぁ! 俺、一番だもんね!」 「ずるーい! さっきはヒロだったんだから今度は僕だよ!」 合宿所前の県道に、その時すさまじい勢いで騒音が押し寄せて来た。黒塗りの乗用車が何台 も連なり、パラボラをつけた中継車まで猛スピードで走り過ぎて行くのを、サッカー少年たちとコー チは呆然と見送る。 が、一人それに背を向け、井沢は借りたジャージに悠然と袖を通していた。 「あいつ、外務省経由で手配が回ってるのを知らないみたいだな。出入国管理局にマークされて るって教えてやろうと思ってたのに。…ま、でも大丈夫か。あのはしっこさなら」 ボールが高く上がった。まぶしそうにそれを見上げながら井沢はもう一度大きく深呼吸する。 「無事に帰って来いよ、反町。今度は俺がおまえをフィールドに引きずり込んでやるからな」 そう、点は取られるものではなく狙うものだ。 井沢はその意味で、もちろんプロだった。 〔おわり〕
|
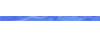 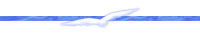 |
| 作者コメント: |
| この二人以外は全員オリジナルで、もはやC翼とは思え ない話になっております。二人ともどういう仕事をやって いるのかよくわからない状況ですが、要はそんな中で二 人はこんな関係ですよ…という話でもあります。だからわ からないままです、この先も(笑)。 |
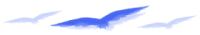 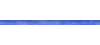 |