悪徳弁護士シリーズ・4
HOLD ME IN YOUR ARMS
| 国内でも有数の総合商社、その最上階に密かにうごめく影があった。警備員が常駐している
セキュリティセンターは1階にあるが、その監視カメラは侵入時にしっかり寝かしつけてある。
反町は慎重に進路を探りながら、フロアの一番奥にある役員室に足を踏み入れた。 室内は真っ暗である。窓すらない。このビルの中でもっとも堅固に守りを固めた密室だった。反 町がここを突き止めたのは、例のクリスマスメッセージがこの部屋の端末から送られていたこと を確認したからだ。 が、この部屋はただの密室ではなかった。 定石通りまずは金庫から…とばかりに作業にかかろうとした反町は、いきなり思いも寄らない 不意打ちをくらってしまったのである。 「探し物はこれじゃねえのか?」 何かが空を切る気配がして、脇の屑入れがガサッと大きな音をたてた。 「う……」 反町の手足に凍るような緊張が走った。ペンライトがその指先からポロリと落ちる。カーペット 敷きの床から斜めに、不自然な焦点の光の輪が広がった。 「まさか…」 忘れるはずのない声だった。たとえ何年のブランクがあったとしても。 そーっと顔を巡らせて背後の闇に目を凝らす。反対側の壁を背にしてサイドデスクが大きな影 の塊となっている。そのちょうど中央で、チェアが微かな軋みを響かせてくるりと回った。 「相変わらず夜目のきかねえとこは同じだな、反町」 「ひゅ、日向さんっ… !? 」 ぱっと跳ね起きて向き直る。低めたままの声で叫んだ反町は、その闇の一番深いあたりに、声 の主のシルエットを認めた。 「どーしてここにっ!」 「おまえが今夜来るのはわかってたからな。先回りして待ってたんだ」 反町を見返している闇の深さに、微かな冷笑が灯ったようだった。 「すっ飛んでくると思ったのに、けっこう慎重だったな。おまえも少しは分別がついたらしい」 「…まさか、日向さん、あの脅迫状よこしたの、あんた? い、井沢をどーしたんだよっ!」 「人聞きが悪いな。あれは言葉通り、クリスマスの挨拶がわりだぞ。俺はな、欲しいものは手に 入れる。それだけだ。知ってるだろうが」 知ってる。嫌になるくらいに。 反町は今すぐ明かりをつけたいという衝動を抑えねばならなかった。この暗闇の中で対して話 すには最悪の相手だったが、なにしろ内緒でお邪魔している身ではそう勝手に目立つわけには いかない。 「なら、日向さん…、まさかあのコンベンションセンター建設に関わってたわけ? だってだって、 設計は公開コンペで、全然別の設計事務所の名前になってたし…!」 「俺は最初からコンペに加わる必要がなかったのさ。公表してあるのはダミーだ。受注先からの 依頼は1年も前に俺のとこに届いてたからな」 「ひっでー!」 「俺のギャラは高いんだ。並のやり方じゃ追い付かねえよ」 ヨーロッパを活動の拠点にして、日向は目下新進気鋭の建築家という肩書きを持つ。だが、地 道にキャリアを積み上げるような性格も時間の余裕も持ち合わせていなかった日向は、その強 引な突破力で様々な伝説を造り上げてきた。 つい先年のこと、中世スペインの宮殿移築プロジェクトを請け負った日向は、移築先のフランス の文化省の青写真をまったく無視した大胆なアレンジを加えて、移築はほとんど改築と化してし まった。無論、文化省の機嫌はよろしくなかったが、結果完成した南フランスのオペラハウスの 評判は、「ハリケーン!」と大見出しが躍った有力紙をはじめ熱狂的とも言えるものとなり、結局 日向の名声はさらに高まったのであった。 『ただの怖いもの知らずですよ』 と言ったのは若島津であるが、そのオペラハウスのこけら落としとなった去年の映画祭で外国語 部門のグランプリを取り、今年も特別招待作品を携えて参加することとなったのは実に皮肉な偶 然である。 「俺はな、施工主がどっからどうやって金を用意するかには興味はねえ。結果、金がきちんと用 意されてればいいんだ。だが、あいつらはそれを渋りやがった。俺を値踏みするとどうなるか、じ っくり教えてやろうってわけよ」 「あいつらって…ここの、会社?」 「ああ。それと、日本政府だ」 平然と、日向の声は続いた。 「華僑シンジケートはその点、俺の取り分を保証してくれたからな。俺としては味方につけとかね えとな」 「げげ!」 某国での自分の行状がすっかりバレているのを反町は悟った。幹部の情婦に近づいて手に入 れた1枚のフロッピー。日向の狙いはまさにそれだったのだ。 「さっき投げてやったのがおまえが欲しがってたここの融資リストだ。交換ってことなら文句はね えよな、反町」 「駄目だよ! 俺はね、両方揃ってないと意味ないんだから!」 日向はその返答を十分予測していたはずである。無言のままデスクのあたりから気配が動い て、そしてゆっくりと近づいて来た。 「どうやら利害が一致しないようだな、俺たち」 重い風のような圧迫感が反町の前に立った。 日向は床に転がったままのペンライトを拾い上げると反町に向き直った。淡い光に浮かび上が った表情は、かつての燃え上がるような若さがそぎ落とされた分だけ、逆に底知れぬ凄みを見 せている。それは、年月を隔てても決して変わることのない研ぎ澄まされた野生の牙だった。 が、次の瞬間にその姿は闇に掻き消えた。にっと笑う日向の顔がその一瞬に閃いて、反町の 心臓は跳ね上がる。ペンライトを背後に投げたのだろう。部屋のどこか遠い片隅で小さな落下音 が聞こえた。 「冗談なしだよ、日向さん…」 反町は思わず一歩後退る。だが、腕が伸びてきて、その肩をがっしりと捕らえた。 「大声は出すなよ。警備員がすっ飛んで来るぞ」 「そ、そんなぁ」 暗闇の中で反町は迷った。逃げるが勝ち…。これが一番なのはわかっているが、なにしろ相 手は凶暴な夜行性動物である。闇の中というハンデがある以上、果たして逃げ切れるかどうか。 そしてもう一つ、置いて行けないものもあったのだ。 「ごめんよっ、日向さん!」 体を反転させるようにひねって腕を振りほどくと、反町は床に伏せた。手を伸ばすとその先にさ っきの屑入れがあるはずだった。 「え、とぉ…。あった!」 日向が蹴りこんだ小さな革製ポーチを拾い上げて、反町は胸元にぐいっと捩じ込んだ。このま まドアまで走れば…。 「あっ…!」 廊下の非常灯がドアの下からほの白く漏れているのを視界の端に捕らえたとたん、反町は壁 に叩きつけられた。両肩を強い力で押さえ込まれたまま身動きが取れなくなる。 「は、放せよっ!」 叫ぼうとしたその唇に暖かい圧力が伝わって、反町はそのまま抱きすくめられた。一瞬、びくっ とすくみあがり、それからゆっくりと抵抗が止まる。 闇の中に静寂が渦巻いて、そして吐息が絞り出された。 「ばーか、もっと早く気づけよ」 「う…井沢ぁ〜」 顔を埋めたまま、反町は情けない声を上げた。 「だってだって、日向さんが思いっきり脅すんだからぁ」 「嘘つけ、そこまで見えないわけねえだろが」 確かに、身長はほぼ同じくらいの日向と井沢だが、しかし普通なら間違えることはない。第一、 触り心地ってものがあるだろうに。 「せっかく日向と旧交を温め合ってたとこに割り込んで、お邪魔だったかな?」 「わかったよ、がんばってビタミンAをとって目を鍛えるから、もう脅かしっこなしだってば」 「でも本気で怖がってたようだけど?」 井沢はまだ面白がっているらしかった。 「日向さんが野獣なんだよー。食われちゃいそうだっただから」 「俺は紳士だぜ。おまえらに比べればずっとな」 日向はドアを開けると、二人を振り返ってにやりと笑いを見せた。 「井沢は返すよ。この3日間で十分やってくれたから、日本の手強い官僚対策ももう心配ねえ。 あとの根回しは好きにやっといてくれ」 「井沢…、日向さんに仕事、依頼されてたわけ?」 日向の言葉に妙な顔をしている反町に、井沢はただ肩をすくめた。それから日向に声を掛け る。 「こういう仕事はもう勘弁してくれよ。カンヅメにしてこき使うだけこき使っておいて、現地解散は ないだろう? 成功報酬にもう少し色をつけてくれきゃ」 「タイムチャージ分はしっかり払ったつもりだぜ。ま、次はねえだろうから安心しな。おまえのギャ ラも俺に負けずに高いってことがわかったからな」 「有り難いね」 それは井沢の心からの本音だったようだ。 |
| 「盗聴器?」
シャワーを浴びて髪をほどき、井沢はソファーに深く沈み込んだ。置時計のデジタル表示がカチ リという微かな音をさせて、そろそろ未明という時間になろうとしていた。 「俺のオフィスにか。失敬なやつだな」 「なんかさ、ほっとしたよ」 反町は手を後ろに組んで、井沢の前に立つ。 「井沢も、女の子にはけっこう紳士なんだってわかったからさ。真弓ちゃんもかわいいけど、八鹿 さんも人妻の魅力がなかなかだね」 「それは抗議のつもりか」 「わかる?」 井沢の濡れた髪を一筋指にとって、反町はにんまり笑った。 「あんなに仕事熱心でおまえのこと信頼してる女の子たちをさ、おまえは平気で見捨てて行ける んだ、伝言一つ残しただけで」 「嬉しそうじゃないか、反町」 その手をうるさそうに振り払いながら、井沢は目を上げた。反町はしかしめげずに隣に滑り込 む。 「だから、ほっとしたって言っただろ。俺のほうには伝言がなかった。俺が帰ってくることを考えて なかったってことだ。俺が真剣になって探しに来るなんてことも、ね。俺はそれが嬉しい。井沢が 俺を信用してないってことがさ」 「なるほどな…」 井沢はちょっと考え込み、そして苦笑した。 「日向が言ってたのはそのことか。今、納得したよ」 「えっ、日向さんが何言ったって?」 「おまえの弱点」 ぎくりと手を止めて、反町は探るように井沢の顔を覗き込んだ。日向と一緒だったという3日 間。そこに疑念がふつふつと湧き上がって…来ることはないにしても。 「なんだよ、それー!」 「クリスマスプレゼントに、弁護士を…だろ?」 驚いた顔を下から捕らえながら、井沢はゆっくりと体を引き寄せた。 「もらってくれるよな、反町」 「やだよ」 自分から頬に顔を寄せて、反町はくすくす笑いを始めた。 「エサをさ、もらうだけで人間には近づかない。野良がしみついてしまってて、飼い猫にはなれな い。…日向さん、まだそんなこと言ってたわけ?」 「おまえのこと、外猫だって」 「うん」 飼い猫にはなれない、外猫。かつて日向は反町をそう決め付けてはばからなかった。あれか ら十数年。自分は変わったのか、それとも変わらなかったのか。 「二人で俺の弱点を議論してたなんて、えっち!」 「さあ、それはどうかな」 あくまで弁護士の守秘義務をかざす井沢であった。 「日向さんにせっかくのスクープをつぶされたんだ、絶対復讐してやる。だいたい日向さんこそ自 分がスクープの塊なんだ。突っつき回してネタを見つけるのなんて、簡単なんだから…」 「ほら、もう黙れよ」 熱の高まりが二人を包み始めていた。おしゃべりを封印しておいて、井沢はそのまま流れに深 く身を任せていく。 まるで音を立てて流れ落ちるように、夜明けの色が外の闇を溶かし始めていた。時間は、そん なふうに、目に見えない審判を下し続けるのだ。 冬のさなかにも、また夏の陽の下でも。 「…井沢?」 「ああ」 もうそこは夢の中だった。 「クリスマス、だよな」 そんなメリークリスマスが、どこかの空の高みで響いていた。 《END》
|
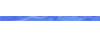 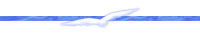 |
| 作者コメント: |
| あまりクリスマスっぽくならなくてすみません。日向さん が出てきた時点で、作者までなんだか動揺してしまった みたいで。例によって「仕事」の詳細は何も考えずに書 いていますので、雰囲気だけお楽しみいただければ… (笑)。 |
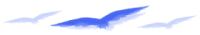 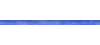 |