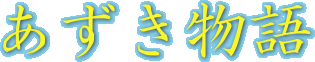
| Scene 1 ___ 立ち枯れた木が乾いた地面に色濃い影を投げていた。 朝早く隣村へ向かうジープが1台立ち寄ったきり、今日もこの街道には何の気 配もない。2日前、50kmほど離れた村で小規模な武力衝突があったばかりだか らそれも無理はないのかもしれなかったが。 エミリオは店の前のかしいだ椅子にかけて、もう詰めるタバコもないパイプを横 っちょにくわえていた。ここからは赤茶けたカルタヘナ渓谷がよく見渡せる。どこ までも雄大でどこまでも不毛なその光景を、エミリオは空を行くコンドルになった 気分で見るともなしに見やっていた。その時――。 何かが動いた気がした。 老店主はパイプを片手に受け、背筋を伸ばした。頭上でガソリン会社の剥げた 看板が風にあおられ、ガタン、と乾いた音を立てた。 思い出したように熱い土煙を舞い上げている道の向こうに、ぽつんと人影が見 えた。 エミリオは赤銅色に焼けた鼻の上にしわを寄せた。自分の目が信じられなかっ たのだ。が、その人影は静かに彼のほうに向かって近づいてくる。 それは女性だった。彼が今まで見たこともないような女性だった。全身に異世 界の空気をまとって、音もなく歩いて来る。エミリオはだらしなく口をぽかんと開け た。 「暑いお日和ですことね」 不思議な響きを持つ異国の言葉だった。白いレースのパラソルをくるりと回し て、その女性はエミリオに微笑みかけた。 「ブエノス・ディアス、シニョール」 エミリオは生まれてこのかたこれほどあわてたことがないという顔でホコリだら けの帽子をあたふたと取り、胸に押しつけた。返事をしているつもりで口を動かし たが、声は出てこない。 「お尋ねしたいのですけれど…」 女性はそんなエミリオの態度には構わず、道の行く手にゆったりと目を向ける。 上品に結い上げたつややかな黒髪がパラソルの淡い日陰の下で夢のように揺 らいだ。エミリオには想像もつかないほど繊細な色合いの衣装が足元まで流れ ている。まさかこの炎天下、このいでたちでずっと歩いて来たと言うのだろうか。 この一帯は非武装地帯とは言え、土地の男でも移動には細心の注意を払わね ばならないのだ。この異国の女性がどうやってここまでやって来られたのか、エ ミリオは幻を見ているとしか思えなかった。 「この先の村に、若い日本人が住んでいたと聞いたのですけれど、この道でよろ しいのかしら?」 エミリオに通じるはずのない言葉で彼女は続けた。それから少し微笑んで一言 「ハポネス」と付け加える。 ――ハポネス(日本人)! 瞬間、エミリオの中で現実と非現実が激しく交差した。頭の中でその言葉がグ ルグルと舞う。そう、まるで熱風にあおられるコンドルのように。 |
Scene 2 ___ 「待ちなさい、亮!」 ドアが大きく開き、一瞬の間に小さな白い影が走り抜けた。 「服を着なさいと言うのに! こらっ!」 続いて腕に服を一抱えにした三杉が走り出てくる。 「うわーい!」 さらにその後を追って、2人の裸の男の子がもつれるようにしながら走って来 た。大小の足音が縦横に駆け巡り、三杉邸のドアというドアがあっちでもこっちで も派手な音をたてる。 「きゃーっ!! 」 それを締めくくったのは、台所から上がった悲鳴であった。急いで駆けつけた 三杉はその惨状に胸を押さえてしまう。 「坊ちゃま、坊ちゃま、坊ちゃまーっ!」 台所でおやつのマドレーヌを作っていたメイドが、棒立ちになったままご丁寧に 人数分の悲鳴を上げていた。その足元には真っ白な粉の塊が3つ、楽しそうな 笑い声を立てながら転げ回っている。 「こうなってはいくら僕でも見分けはつかないね…」 三杉は大きくため息を一つつくと、小麦粉の海の中から一つずつゆっくりと塊を 拾い上げた。 「何のためにバスを使ったんだろうね、本当に」 「まったくでございます、淳坊ちゃま」 この家で、いや、日本中でもその呼び方をするのは今やただ一人である。慣れ たつもりでもしばしば心臓を止めてしまうその不意打ちは、本人に言わせると、 「お仕えする者の心得でございます」 とのことで、別に悪趣味で気配を殺しているのではないそうだが、できることなら もう少し人間らしい環境にいたいと思う三杉であった。 「……幸さん」 三杉は息を整え直すと、振り返って塊の一つを手渡した。 「そう思うなら子供達の入浴を僕一人に任せるようなことはしないでほしいんだ が」 「それは申し訳ありませんでした」 ばあやさんは両手に一人ずつ塊を抱え、こちらは一つだけ腕に抱いた三杉の 前をすたすたと手近のバスルームに向かう。 「わたくし、外出しておりましたもので」 バスタブの栓は抜いたままでシャワーをひねり、手際よく3人の子供達のコロモ を洗い流す。 「でも淳坊ちゃまも運動不足解消にちょうどよろしいかと存じますが」 「誰が運動不足だって?」 三杉がじろりと視線を投げた。もちろんばあやさんの表情はぴくりとも動かな い。 「光様がご出立なさって以来、毎週末のトレーニングにあまり身が入っておいで でないようですから」 「……」 スポーツ医学の国際シンポジウムへの準備、全日本 Jr ユースチーム合宿開 始に伴うアドバイザーとしての雑務、それに彼自身の医師としての勤務……と、 言い訳はいくつも浮かんできた。が、たとえ時間が半分しか取れなくてもその分 密度を高めて補うことなど自在なはずの彼が、もっぱら精神的な空白のゆえに それを怠っていたことは事実であったし、それをこのばあやさんに隠しおおせるも のでないことは誰より彼自身が一番よく知っていた。 「日ノ丸坊ちゃま、無駄でございますよ」 一番に解放された日ノ丸が、ばあやさんの背後に回ってポンプ式のシャンプー を一心に押そうとしていた。この中では2番目に3歳の誕生日を迎えた日ノ丸だ が、活動量では常に一番を誇っている。そう、全ての行動において。 「さあ、その水鉄砲はそちらに片付けましょうね、小太郎坊ちゃま」 引き寄せた日ノ丸を三杉の広げたタオルに放り込んでおいてから、小太郎に ふわりとバスタオルを巻きつけ、さらにバスタブの底でクロールもどきをやってい た亮を有無を言わせず抱き上げた。 「亮坊ちゃま、続きはまた夜になさいませね」 その鮮やかなまでの手際に、三杉は改めて賞賛のまなざしを送る。ばあやさん はそれに気づいているのかいないのか、 「で、お嬢さま方はどちらですか?」 などと無表情に尋ねる。もちろんこの3人の男の子達の他にまだ娘がいるわけ ではない。ばあやさんはこの子供達の母を今なお「お嬢さま」と呼んではばから ない。もっとも呼ばれる当人達は単純に喜んでいるようだったからお互いさまで ある。 「昼過ぎに出かけてそれきり消息不明だ」 小太郎の母が現在遠いパリの空の下にいることは両人とも了解済みであるか ら、この場合指しているのは日ノ丸の母と亮の母の2人ということになる。 小太郎の母、岬葉月は、1年の大半――合計8ヶ月ほど――を出張という形で日 本に滞在するが、その残りの数ヶ月間、息子をこの三杉家に預けていく。そうで なくても三杉家の長男、亮と瓜二つのこの小太郎を正確に見分けられる者がそ う多くいるはずもなく、初めて日本に来て以来、各方面で混乱を起こしているの であった。 一方、日ノ丸の母、松山美子はこの三杉家から3駅離れた所でマンション住ま いをしているが、夫が長期に留守をする間、幼い子供と2人では物騒だし寂しい だろう、との三杉の奥様の言葉に従ってこの家の住人になる。ひょっとすると日 ノ丸は自分の家よりここ三杉家で過ごした時間のほうが上回っているかもしれな かった。 「さようでございますか」 いつものことであるからばあやさんも特にコメントすることはないらしい。 「では、淳坊ちゃまにはしばらく家庭内トレーニングに励んでいただくことになりそ うでございますね」 「何だって…?」 三杉は不吉な予感にとらわれた。 「わたくし、明日からしばらく休暇をいただくことになっておりますので」 「休暇―― !? 」 不覚にも絶句してしまう。彼が物心ついて以来、このばあやさんがたとえ半日 でも休暇をとるなどということが果たしてあっただろうか。 「か、母さんは何て…?」 「もちろんご許可はいただいております。と申しますより、これは奥様のお達しな のです」 また邸内のどこかで大きな音が響き、若いメイドの悲鳴が聞こえた。が、三杉 の足は動かなかった。異常事態の匂いがぷんぷん漂っている。そう言えば昨夜 遅く久しぶりの自宅に戻って以来、今朝も母親の姿を見ていない。いったいいつ から母はいないのか…? 「母さんは――」 「ご旅行中でございます。お一人では何かとご不自由だと存じますので、わたく し、これから奥様のお召し替えの物など用意してお側に参らせていただくことに いたしました」 あくまで落ち着いた態度でバスルームに散乱するタオルを畳みながら、ばあや さんはそうのたまったのだった。 |
| Scene 3 ___ 「本当に、なんてことでしょう」 母上はその美しい眉をそっとひそめて小さく息をついた。 陽は既に落ちて、崩れた建物を残照が赤く染めている。村の老婆が一人、そ の異国からの客のそばで、わからないはずの言葉に力なくうなづいた。 「もう2日早ければ、この子の母親ともお会いになれたんじゃが…」 老婆は目をしばたたいて、数日前まで平和に暮らしていた村の、今はただの 土くれになってしまった家々の跡をじっと見やった。避難命令もわずかに遅く、こ の小さな谷あいの村はあっという間に政府軍とゲリラ軍の衝突に巻き込まれた のだった。 母上は静かに膝を落として、目の前に突っ立っている小さな子供にまっすぐ向 き合った。粗末な服を1枚着たきりのやせっぽちの子供だった。鼻の頭を少しす りむいているが、あの爆撃の中で生き永らえ、しかもほとんど怪我すら負わずに 済んだのは奇跡とも言えた。たまたま遠出していて難を逃れた老婆と、村でたっ た2人きりの生存者だった。 「ああ、覚えておるとも。ちょうど内戦が始まった年での。巻き込まれて怪我をし ていたのを拾って来たんじゃ。この子の母親が面倒を見ての」 父親、日本人、というたった二言で老婆は質問を理解した。子供は無表情に ただじっと母上を見ている。母上は優しい微笑を浮かべて声をかけた。 「お名前は…?(コモ・セ・ヤーマ・ウステ)」 少し間があった。 「――あずき」 子供は抑揚のない声で、しかしはっきりと答えた。 「年はおいくつ?」 指を3本なんとか立てる。母上はにっこりして子供を抱きしめた。 「そう、あずきちゃん。いい子ね」 それから立ち上がる。 「お顔を見て間違いないって、すぐわかったわ。さあ、お祖母ちゃんと日本に帰り ましょうね」 その言葉が日本語であっても問題ではなかったようだ。少年は母の死が理解 できているのかいないのか、やはり無表情のまま「お祖母ちゃん」の手を素直に とった。 老婆が呆然と見送る中、こうして二人は荒野へと歩み去って行ったのだった。 |