| Scene 5 ___ 「軍部の動きがおかしいって?」 「ああ、ある意味ではマヒ状態と言っていい」 サングラスをあわてて外した反町に、アメリカ人記者は真面目な顔でうなづい てみせた。 「いつから…?」 「うちに情報が入ったのは昨夜遅くだ。だが逆算すると昨日の日没頃から、って とこだな」 中庭のテラス席にはブーゲンビリアの葉陰が濃く落ちていた。日曜の午後、首 都郊外のこのホテルには内戦など無関係、といった顔の白人観光客たちが気だ るく時を過ごしている。スタウトの小瓶を前に、二人のジャーナリストは一瞬無言 で目を合わせた。 「なら、政府内の反軍部勢力は…」 「もちろん千載一遇のチャンス、になるはずだが」 反町は眉を上げた。 「そうはなってない、ってーことは」 「ああ、妙なことに混乱してるのは政府軍だけじゃないんだ。ゲリラ側もかなり …」 「またガセかもしれないぜ。互いにポイント稼ぎの情報で足を引っ張ってるとか」 「うーん、その確率が一番高いのは確かなんだが…」 アメリカ人が頭を振った。軍隊仕様のごつい腕時計をした手で、自分のグラス にスタウトを注ぐ。 現政権を握る軍部と、少数民族の独立運動を旗印にしている反政府ゲリラとの 長い内戦は、つまるところその双方のバックにつく第三国の利害でコントロール されているに過ぎず、したがってこの国においては情報も戦略の小道具だった。 彼らジャーナリストの役目はその一つ一つをいかに的確に選り分けるかにある。 「ま、自分の目で確かめるしかないかな」 自分のスタウトをトンと相手の前に置いて、反町は立ち上がった。足元のカメラ ケースをひょいと肩に掛ける。 「え、ソリマチ? 行くのか、やっぱり」 「そのつもりで来たんだ。予定は変えないよ」 アメリカ人はオーバーに顔をしかめてみせた。 「俺は勧めんぞ。そうでなくてもあの一帯は先週から衝突が続いてる。もう3年前 の二の舞はごめんだからな」 反町はニヤッと笑った。彼らが初めて会ったのは、やはりこんな騒ぎのさなか だった。激しい戦闘のあった内陸部で、反町は1ヶ月もの間行方不明になったの だ。その時手を尽くして捜し回った仲間の一人がこの米国S紙の記者だったので ある。 「大丈夫、一度死にそこねたら二度は死なないって」 「まったく…。懲りん奴ってなお前のことだ」 アメリカ人記者はテーブルに置いてあったタブロイド版の新聞を乱暴に投げつ ける。不意を突かれた反町はそれを片手で受け止めると目を丸くした。 「読んだぜ。ひでえ野郎だ。オリンピック代表だと? なんで黙ってた。第一こん なとこでウロウロしてる場合か?」 あまり鮮明とは言えない白黒の写真だが、予選の時の大騒ぎを思い出すには 十分だった。もちろんこの大空翼の笑顔を見てそういうウラの部分に気づく一般 読者もまずあるまいが。 「本番はまだ半年先だって。それにこれがすんだら帰国するつもりだしさ」 「つもり、ね」 こちらは本社おかかえ、こちらは気ままに飛び回るフリーのフォトジャーナリス ト、と立場は違っても、好んでこういうキナ臭い場所に飛び込んでしまう点では同 じ穴のムジナ、である。思考回路も行動パタンもお見通しであった。 「おまえの首にゃ、金メダルより迷子札がお似合いだよ!」 反町は笑った。笑って肩越しに指を立ててみせる。 「アトランタへの道で迷っちまったらあんたに聞くよ。それまでにスポーツ部に転 属しておきなよ、ジェニングス!」 そうして反町は南に向かったのだった。 |
| エミリオはまだ悪夢から覚めていなかったようだ。今日もまた快晴の空の下、
彼の住む世界はその風景に何の変化も見せないままではあったが、そこにまた
いきなり災厄が立っていたのだ。――人間の姿をして。 「やあ、おやじさん。元気でやってるかい」 反町は赤土まみれのクルーザーから降り立つと帽子をひょいと上げて白い歯を 見せた。が、椅子に深くもたれた老人はパイプに添えた手もそのままに、全く動 かなかった。濃い眉の下から視線だけがじっとこちらに向いている。 「エミリオ、俺を忘れたのか? ほら、3年前…」 「――忘れるものかい」 エミリオがいきなり腕を振り上げた。 「よくもおめおめと現われたな! おまえさんを拾ったせいであの後どんな騒ぎに なったと思っとるんじゃ…!」 なぐり倒されそうな抱擁に笑って応えながら、反町は肩のザックを下ろした。 「わかった、わかったよ。ほら、これで勘弁な。約束のだぜ」 エミリオは反町が差し出した皮袋を疑わしそうな目で眺めてからくんくんと匂い をかいだ。目が満足そうに輝く。 「よかろう。3年分の利子もついているようだしな」 エミリオはさっそくパイプに一つまみタバコの葉を押し込むと火をつけた。 「だがよくわしの好みがわかったな、ソリマチ」 「自分じゃ吸わないけど、鼻はいいんだぜ。『村』で同じの吸ってた奴に聞いてお いたんだ」 「……」 エミリオはパイプを口から離した。睨みつけるように空を見つめ、フーッと煙を吐 き出す。鼻の上に刻まれたしわがさらに深くなった。 「『村』はやられちまったよ。4日前だ。みんなやられた。何も、誰も残っとらん…」 「何だって !? 」 二人の沈黙の背後で、つむじ風がまた道路に赤い渦を巻き上げた。 3年前この街道沿いの町に派手な空爆があった時、ちょうど取材活動をしてい た反町はその巻き添えをくったのだ。ケガから高い熱を出し動けなくなっていた 彼を発見したエミリオは、身内が住む小さな村に反町を託したのだったが、この 日本人の撮影したフィルムをめぐって政府軍の追及の手がしつこく伸びてきたの である。 しかしエミリオはあくまでしらを切りとおし、反町は隠れ里のような『村』で手厚 い看護を受けた。その約1ヶ月の滞在は反町にとって色々な意味で得難い経験 となった。 はるか過去から変わることのない生活――厳しい自然環境にしがみつくように して細々と続けてきた素朴な自給自足の生活は、この国のもう一つの現実だっ た。荒野の中の雄大な風景、温かく迎えてくれた村人たち――そして、今は名さ えも忘れたあの女…。その全てが一瞬に消え去ったと言うのか。 「…愚かなことだ。殺し合って何が残ると言うんだ。新しい憎しみだけじゃないか」 「エミリオ…」 反町は老人の肩に手を置いた。 南北アメリカ大陸を背骨のように貫く山脈の懐に隠れるようにして、先住民族 の人々は毎日の暮らしを荒野と砂漠の連なりに刻み続けてきた。何千年も前に ユーラシア大陸から渡って来たと言われる彼らは日本人と同じ血をくむモンゴロ イド人種で、その面差しもかなり似通ったものがある。だが彼らの歴史は常に侵 略者の手で脅かされ、圧迫され、そして血塗られてきた。彼ら自身の国家はつい に成立せず、その血すらも侵略者の持ち込んだ社会、文化に吸収され分解して いった。 エミリオはこの街道の前に腰掛けて、そんな時の影の往来を眺めて来たのだ ろうか。反町がふとそんな想いに駆られた時、いきなりエミリオがぽん、と自分の 両膝を叩いた。 「ま、それもひとまず終わりじゃ。いつまでもつか知らんがとりあえずは祝うとする か」 「え、何を…?」 立ち上がったエミリオはじろりと反町を睨みつけた。 「何を寝ぼけとる。戦争が終わったんだろうが!」 「えっ、ええええーっ! 知らない、知らないよぉ!」 反町は頭を抱えてわめいた。エミリオは呆れたようにそれを見てから椅子のす ぐ後ろに置いてある古ぼけたトランジスタラジオのスイッチを入れた。流れ出てき たのは間違いなく国歌である。演奏が終わってアナウンサーの声がそれにかぶ さった。 「国連の調停案に――国連さえ忘れてたくらい昔の調停案に両方とも調印した だとぉ !? いきなり何なんだっ!」 反町の叫びはまた始まった国歌の荘厳なメロディーにかき消される。エミリオ は肩をすくめた。 「記者のくせに抜けたやつだな。おい、ソリマチ、おまえさん酒は持って来なかっ たのか?」 「え? …あ、いや酒はあいにく…」 「ふん、まあいい。そのうち誰か通りかかったらそいつから取り上げるさ」 家のスイングドアに手を掛けて、エミリオが振り返った。 「そうだ、忘れとった。おとといな、ここに日本人が来たんだ」 「――え、日本人?」 「ああ、スペイン語を話さんのでよくわからなかったが、おまえさんを訪ねて来た みたいだったな、あの女は」 「お、女ぁ !? 」 反町は絶句した。エミリオからその時の状況を詳しく聞いてますます血の気が 引く。 「まさか…、そんなはず――!」 エミリオの言葉に該当する人物が一人あるにはあった。…が、世間の騒がしさ から完全に切り離されたような邸宅の奥でゆったり穏やかに暮らしているあのご 婦人の姿と、今この目の前の過酷な現実とが、どこをどうねじ曲げても結びつか ないのだ。 「どうやって――いや、何しにこんなとこに現われたんだ !? 」 「帰りもアルフォンソのトラックをつかまえて便乗して行ったらしいぞ。帰りは3人 連れだったそうだがな」 エミリオの話はもう反町の頭上を通り過ぎて行くばかりであった。ここで注意深 く聞いていなかったことが後日彼の不幸を倍増させることになったのだったが。 |
| 「奥様、そちらは危のうございますよ」 首都の人々は浮き立っていた。下町の一角にあるこの市場にもそんな雰囲気 がいっぱいに漂って、売り買いの声も弾んで聞こえるようだった。 「あずきちゃん、ほら、行きましょう」 先を行く幸さんの注意が聞こえたのか聞こえなかったのか、三杉夫人はひょい と頭を下げた。そのすぐ上をかすめて魚入りの木箱が勢いよく通過する。 「欲しいものがあるの?」 今朝早く着いた首都の街並みに、あずきは目を丸くしどおしだった。生まれてこ のかた村を離れたことがなかったのだろうから無理はない。こんなにたくさんの 人、こんなにたくさんの物、こんなにたくさんの家! ――あずきは無言のままそ の全てに驚嘆の目を注ぎ続けた。 「まあ…」 あずきが足を止めた場所に一緒にしゃがんで、母上はにっこりした。野菜や果 物がとりどりに積まれたカゴの間に数個のレモンが置かれていたのだ。 「こいつは輸入もんだよ。この国にゃレモンの木はまだないからね」 大きな胴回りのおかみさんが身振りを交えて教えてくれた。母上は不思議そう な顔になる。 「あら、それじゃあずきちゃんのあの木は、もしかして…」 「さようでございますね」 買ってもらったレモンを嬉しそうに胸に抱きしめながら、あずきはさっさと先を歩 いて行く。 「外から持ち込まれたもの、ということでございましょう」 誰によって、という点はもう疑う余地はないようだった。 「でもあの時あずきちゃんは『あずきの木』って言ったわ。じゃ、あずきって名前 は…」 幸さんは先を行くあずきの背に暖かい視線を投げながらうなづいた。 「おそらくは、覚え間違えたまま同じ名をつけたのではないでしょうか」 「ま…!」 母上の目がきらきらと輝いた。 「早く帰って一樹さんに会わせてあげたいわね。一樹さん、どんなに喜ぶかしら」 幸さんは……何も答えなかった。 Epilogue ___ 「子供っていいわね。すぐ仲良くなっちゃって」 「日ノ丸ってば、すっかり兄貴気取りだわ、もう」 「それよりお母さまよ。とっても幸せそう」 うふふ、と笑い合う二人の母親だった。居間続きのサンルームでのアフタヌー ンティーに、今のところ三杉家の大奥様が加わる気配はまったくない。4人の孫 息子に囲まれて、それはもう楽しそうに微笑んでらっしゃるのだ。中庭の芝の上 に白レースのすそを見事に広げて。さあ、幸さんがこれを見たらさぞ小言が出る ことだろう。 あずきは初めての国、初めての環境にもさして違和感はなかったらしい。言葉 の壁と言っても4人の3歳児にそれが大きな意味を持つはずもなく、それよりもむ しろパニックは三杉家の使用人たちの間にじわじわと広がりつつあった。これま でいた3人だけでも十分混乱の元であったのに、同じ顔がまた一人増えたの だ。せめて名札でも、と幸さんに直訴したメイドもいたらしい。 「で、あずきくんのパパはいつ帰国するの?」 「さあねぇ、そればっかりはあの人たちのことだから…」 なぜ複数になるのだろう。 「とりあえず淳が『迷子広告』を出してたみたい」 「まあ、さすがね!」 「――すまない、もう一度、ゆっくり繰り返してくれないか」 その広告主は二階の書斎で電話口にいた。端正な横顔が心なしか青ざめて 見える。 「ああ、そのヘッドラインはさっき届いたよ。…しかし、えー、確認しておきたくて ね」 彼の目はデスクの上のファクシミリ用紙にとまっていた。それは米国のネットワ ークサービスから送られてきたS紙のコラム記事であった。 『謎の女ゲリラ、内戦終了に暗躍か!』 「筆者のウォルター・ジェニングスって記者と直接コンタクトは無理なのかい? ど うしても聞いておきたいことが…」 三杉とて実の母親の行状をそうは疑いたくはない。ただ昨日帰宅した彼女とば あやさんが連れ帰った少年は――そのパスポートは、まぎれもなくその話題の 国のものなのである。 「そうか、それなら無理だな。…ああ、また何かわかったら頼むよ。ありがとう」 三杉は受話器を置くと、開いた窓から中庭を見下ろした。緑陰を通って来る風 がその柔らかな手で彼の前髪にそっと触れて行く。 「僕も心配性だな、いい加減。光から便りもあったことだし、もう少し楽観的にな るほうがいいかな」 明るい笑い声をまぜこぜにしながら、4人の子供達が転げ回っていた。一人に 抱きつき、その足元をすくい、かと思うと別の一人に飛びかかる。始まりもなけれ ば終わりもない、それはまさに羽根をつけずに生まれてきた天使たちの時間だっ た。 「じゅーん! そんな所にいないであなたも下りていらっしゃーい! お日さまが 気持ちいいわよー!」 いつのまにか彼の妻も庭に出て手を振っていた。のどかな昼下がり、三杉は笑 って手を振り返すと階下へ向かった。 もちろん、反町一樹の帰還が目前に迫っていることも、それが彼の楽観を ――ついでに反町自身をも――一気に踏み潰すものだということも知らないまま …。 《END》 |
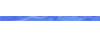 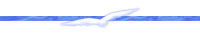 |
|
| 作者コメント: | |
| 四つ子たちが20代後半から30代にかけてのお話。み んな勝手に世界中に散らばってますが、まだ現役の代 表選手です。詳しい設定は「四つ子ナビ」でどうぞ。 | |
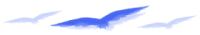 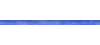 |